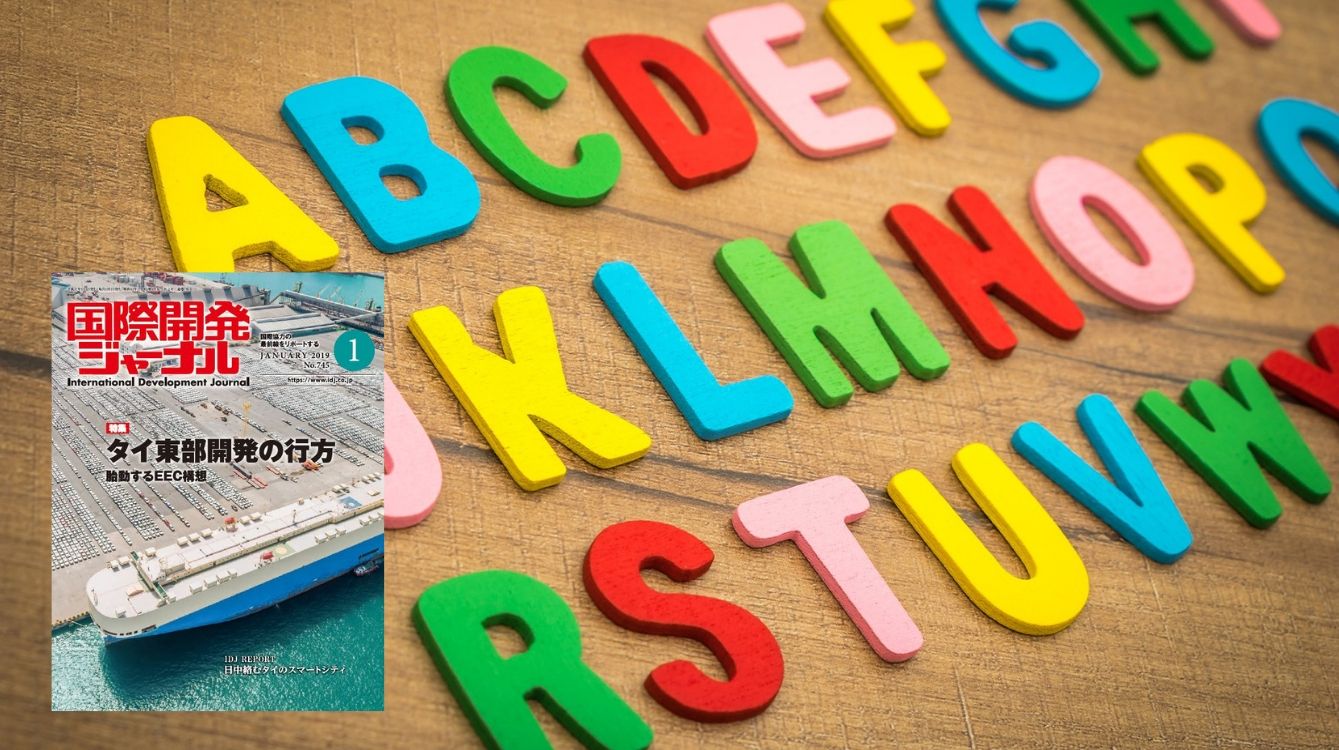国際移住機関(IOM)アフガン事務所に勤務する
茅 和伊 (かや かつい)さんからの現地レポート
『国際開発ジャーナル』2008年月号特集「どこに向かうアフガニスタン支援」でもお伝えしたとおり、復興の現場では、常に危険と背中合わせの状況のなか、復興支援に奮闘する人たちがいる。
2008年1月14日、この日は取り立てて慌しくもなく、どちらかというとのんびりした朝から始まった。世界でも有数の安全大国、日本での正月休暇を終えカブールに戻ってきてから約一週間が経ったところであった休暇に出る前にアフガン軍などを狙ったテロ攻撃が続いたため、軍の車が事務所の前を通る午前8時半までの間は国際移住機関(IOM)の車をゲートから出さないという規則ができた。冬は毎年テロ活動も「冬眠」に入り多少沈静化すると言われているので、休暇から帰った極寒の1月には、“この規則も解除されているはず”と高をくくっていたが、あいにく治安状況に変化はないとのことだ。ゲート開閉の時間制限を設けているのはIOMだけであったため、家をシェアしていたハウス・メイトの一人である国連開発計画(UNDP)職員のダルコが先に出勤するのを見送った。
「なぜ私だけ面倒な規則を守らなければならないのだろう」と、帰国後の平和ボケが覚めやらぬ自分にはいまいち納得が行かないまま、テレビを見たり紅茶を飲んだりしながら車が来るまで一人で時間を潰した。十数時間後に国際社会を震撼させる事件が起こるとはつゆも知らずに・・・。
事務所で仕事をしているといつの間にか4時を回り、そろそろ日も沈み始めようかという頃となっていた。家の中にある食料などが大分不足していることにふと気が付き、ダルコにEメールを送り一緒にスーパーに行かないかと誘った。すぐに返信があったが、これからセレナホテルのジムに行って運動するつもりなので、今日は難しいという内容だった。一人で買い物に行くことに抵抗はなかったので、「ノー・プロブレム、運動を楽しんできてね」と伝えた。
その後、仕事の片付けや雑用を済ませていると、ちょうど6時13分に“ドン!”と、重みのある音が響いた。この種の音を聞き慣れている私は、どこかで爆発があったのだとすぐにわかった。カブールで生活していると、コントロール・エクスプロージョン(回収した地雷を集めて意図的に爆発させること)などを含めて爆発音を聞くことはほぼ日常茶飯事であるため、とくに慌てる訳でもなく、「具体的な情報が入るまで様子を見よう」という程度の気持ちで雑用を続けていた。
数分後に隣のオフィスに行くと、先程の爆発はセレナホテルの入り口で起きたものだと同僚が言う。
セレナホテルといえば、ダルコ!
ちょうど彼がジムに行くと言っていたことを思い出したが、セレナの警備が非常に厳重な上に敷地も広く、仮に入り口に爆弾が仕掛けられていたことが本当であっても、ダルコがそこに出くわして巻き込まれた可能性は非常に低いはずだと自分に言い聞かせた。念のためにと思って電話してみると、こともあろうが彼の携帯電話は圏外になっていた。もしや爆発で電話が吹き飛ばされたのでは・・・」という思いを振り払うように数分後にもう一度かけてみると、少なくとも今度は呼び出し音がした。電話が鳴るということは、爆弾で吹き飛ばされた訳ではないということ。ダルコはきっとジムでのん気に運動を続けており、「ロッカーのなかにある携帯電話が聞こえないだけ」と自分に説明をしてみると、一応、つじつまが合うような気がした。
しばらくしてユネスコで働く友達から電話があった。「大丈夫か?」という安全確認が目的だった。自分は無事だけれどダルコが心配だと伝えると、彼が知る限りではセレナの入り口で自爆テロがあり、警備員が犠牲になったとのことだった。新しい情報が入り次第連絡するのでとにかく落ち着いて、定期的にダルコに電話し続けてというアドバイスを受けた。
そうこうしている間に7時近くになったので、ダルコの様子がわからずに、すっきりとしないまま事務所を離れた。セレナホテル方面以外は特に行動規制は敷かれていなかったため、予定通り帰り道にあるスーパーに向った。もう一度ダルコに電話してみたが、相変わらず呼び出し音がなるだけ。不安を掻き消すために「ずいぶんのん気なものだ」と半ば呆れながら買い物リストを頭のなかで確認した。スーパーの中に入った頃、再び友達からの電話が鳴った。新しい情報によると、タリバンが犯行声明を出しており、4人の仲間がセレナホテルの中に侵入することに成功したと発表しているという。どうやらホテル内でも手榴弾などが爆発したらしい。この情報だけでは何も断定できないが、心のなかに更なる不安がよぎる。大丈夫、そんなまさかと思いながらもなぜか落ち着かない。
部屋に戻った私は簡単な食事をとりながら、「何という夜だろうか」と考えていた。時間はすでに9時近く。ダルコが普段ジムから帰ってくる時間はとうに過ぎており、私の立てた「のん気に運動を続けているため電話の音が聞こえないだけ」という仮説はすでに説得力を失っていた。自分に何ができるかわからず、藁にもすがる思いでIOMのセキュリティー・オフィサーに電話をした。状況を伝えると、彼はまだパニックに陥る必要はないと言う。つまり何百人という客が現在ホテル内に待機しており、そのような事件の直後にテロリストの通信を妨害するために国際治安支援部隊(ISAF)が携帯電話の電波を切るのは普通であり、電話に出ないことがイコール緊急事態ではないというわけだ。
10時半くらいだったか、もう一人のハウス・メイト、ハニフェと共にリビングでテレビをつけた。その直前にハニフェが友達から得た情報によると、4人の潜入者はセレナの中で手榴弾を投げただけでなく、銃を乱射したという。
それを聞いて返す言葉を失っていた矢先にBBCのニュースが始まり、ハニフェと私はテレビに釘付けとなった。始めのニュースはどこかの大統領が会議でこういう発言をしたというようなもの。今では内容すら思い出せないが、「こんな重大事件が起こっているのに世界はなぜどうでもよい話をヘッドラインにするのだろうか」と苛立ちを覚えた。すると画面はセレナ付近の見慣れた光景に変わり、やっとセレナ事件についてのニュースが流れ始めた。キャスターはビジネスライクな早口で、「セレナが襲撃された」「4人のタリバンが潜入し、中で発砲した」「その内の一人はジムの男性ロッカールームで発砲」「今のところ死者6人、負傷者10人(注:結果的には死者8人、負傷者9人であった。)」という要点のみ説明した。たった2分くらいのレポートだった。ハニフェと私は顔を見合わせ、どちらからともなく発した言葉はMy God!!!」の一言だけ。
私自身セレナのロッカールームを利用したことは何度もあるが、それほど大きい訳でもなく、人がたくさんいたとしてもせいぜい10人くらいだろうか。そのロッカールームで、まさにダルコがいたジムの横にあるロッカールームで6人死亡・・・。もう慰めの言葉は効かない。私の心の中で少しずつ覚悟が固まった。友達を一人失ったかもしれない可能性がじわじわと体に突き刺さった。混乱と不安が頂点に登りつつあるなか、心臓の鼓動が激しくなるのが感じられた。
その数分後、突如として表の道路に車が止まる音がし、呼び出し音が鳴った。絶望の淵に突き落とされたようなハニフェと私が、「帰って来たのがダルコでありますように」という祈りを胸に家を飛び出すと、本人がそこに立っているではないか。
抱き合って無事帰宅したことを喜び合った後リビングに移動した。改めてよく見てみると、そこにいたダルコは冗談好きのいつものダルコとは別人のようで、目が充血し、頬が硬直し、ただ事ならぬ緊張感を漂わせていた。
「僕の人生は今日で終わりだと思った。ここにこうして生きて帰って来たのは奇跡的な幸運だけど、本当に死ぬ寸前だったよ」
彼の話を要約するとその夜起こった出来事は次のような内容である。
ダルコは6時13分の最初の爆発があった時、ジムでいつも通りの運動をしていた。かなり大きな音ではあったが、まさか敷地内で爆発が起こったとは思わずそのまま運動を続けていた。数秒経ってからもう一発、爆発音がした。やはり爆心地からの距離感ははっきりしなかったが、立て続けに起こる爆発に恐怖を感じ、運動していた人びとは次々に荷物を取りにロッカールームに向った。ダルコがどうすれば良いか決めかねジムの中でもたもたしていると、すかさずに三発目の爆発音が鳴り響いた。さすがに行動に移さない訳にはいかず、ダルコも他の人に続いてロッカールームの方へ走った。
ドアを開けて中に入ってから僅か一秒。銃弾の音と共にダルコの横1メートルくらいの場所に立っていた男性がお腹を抱え、そのまま床に倒れた。同時に飛び散った血を前に、頭のなかは真っ白に。周りを見ることも、考えることも、呼吸することすらままならなかったが、「この部屋を出なければならない」という直感だけがダルコの体を瞬時に突き動かした。部屋を出ようとする自分のすぐそばで銃弾の音がした。遠くで鳴る音ではなく、体のすぐ横をかすめる音。その時は無我夢中だったが、後になって考えてみるとテロリストは自分を狙って撃っていたに違いないという。この時彼の生死を分けたのはたった数十センチ、または数センチの幅だけ。
もしテロリストの指が一ミリ傾いていたら?引き金を引くのが一秒早かったら?ひじの角度が一度でもずれていたら?そのような些細なことで銃弾はダルコに命中していたかもしれない。むしろ死をかけて訓練してきたテロリストが狙いをはずしたことの方が不思議なくらいだ。
ジムに戻ったダルコは向かい側に隣接している女性専用ロッカールームに駆け込んだ。幸いこちらにはテロリストの手は及んでおらず、なかにいた女性客は状況がわからずに混乱していた。ダルコが男性ロッカールーム内で今現在起こっている惨事について告げると、女性客は一気にパニックに陥った。男性の「始末」がついたら今度は女性の番だろうか。テロリストはいつ女性ロッカールームに入ってくるのだろうか。皆殺し?それともその前にレイプ・・・?そう思って皆恐怖に震え上がった。恐怖感の表現は人それぞれで、泣き叫ぶ人もいれば、動き回る人もいれば、冷静さを保ちながら大使館に電話して助けを呼ぶ人もいた。
5分くらいすると銃弾の音もすべて収まり、不気味な静けさが広がった。叫んでいた人も声を潜め、息を呑んで様子を伺った。テロリストが男性サイドの殺戮を終え、次の獲物を狙って入ってくるか、それとも軍隊か警備員によって捕らえられたかどちらかであった。ダルコはここで自分の人生は終わるのだ、と覚悟を決めた。
どうぞ助かりますように、と必死に祈りを唱えること約15分。この永遠に匹敵する15分の静けさは、ついに遠くから聞こえるホテルの警備員の声によって破られた。警備員は女性ロッカールームに辿り着くと、そこにいた客を全員速やかに地下に誘導した。移動の際にロッカールームとロビーの間にあるジム専用のレセプションを通ったが、そこにはマッサージ士の死体が血まみれになって通り道を塞ぐ形で横たわっており、ダルコを始めとする客は全員彼女の体をまたいで進まざるを得なかった。つい数十分前まで笑顔で客に応対していた明るい女性の面影はもうそこには無かった。
それからの数日はあっと言う間に過ぎた。上司から海外に出て静養するよう指示されたばかりか、連日、多くの人びとにセレナ事件について聞かれたのがこたえたとダルコは言う。自分の体験について何度も繰り返し話すうちにその時の光景や感覚が甦り、徐々に恐怖感が増してきたのだ。同じ環境下にある限り、回復するどころか再びトラウマに遭うのではないかと感じたダルコは、三日目の朝、ついにスーツケースをまとめて家を出た。さよならでもない、でもいつまた会えるかわからない不思議な別れだった。アフガンに戻ってくるかどうかはもう少し落ち着いてから決めるというが、たった数週間で癒えるような心のダメージではないという気がする。
カブールに別れを告げることがダルコにとって本当の意味で恐怖体験の終わりではないのと同じように、セレナ事件以降、残った私たち援助関係者にとって脅威が終わった訳ではない。むしろ状況は逆で、カブールの治安は悪化する一方だ。その証拠に事件の翌日タリバンは「これからは作戦を変え、外国人が出入りするレストランを攻撃の対象とする」と発表したが、これが潜在的に意味することは恐ろしい。つまり、それまでのタリバンの攻撃は外国軍、又はアフガン政府のなかでも軍と警察を狙ったものが多く、援助関係者が巻き込まれるとしたら、それはたまたま運悪く現場に居合わせたからというものがほとんどだった。
昨年の5月にタリバンの司令官ダウドゥッラが、「これからはアフガン政府、外国軍だけでなく国連もターゲットにする」と発表し、国際社会が震え上がった時期があった。カンダハールでUNHCRの現地職員が殺されたのはその頃だ。数週間後に外国軍の攻撃によりダウドゥッラが殺されて以来、幸いにも国連が直接的ターゲットからは外された様な印象があった。ところが、テロリストが国連職員を含めさまざまな外国人が利用するセレナのなかで無差別に発砲するという今回の事件によって、まさかの脅威が再び甦ったというわけだ。国家予算の約75パーセントを外国援助に頼っているアフガン政府にとって、治安の悪化により国連を始めとする援助機関が国外に脱出する事態となれば大いなる痛手だ。
また国際社会にとっては「テロとの戦い」における敗北を意味し、タリバンにとっては歓迎すべき結果となる。それに対抗するかのように、国連事務総長の播基文は「このような惨事があっても、国連は途中でコミットメントを投げ出したりするつもりはない。アフガニスタンの人々と一緒にこれからも復興活動に従事していく」と宣言した。まさに我慢くらべの幕開けである。
外出禁止という状態で毎日死に怯えながら生活している援助関係者の存在は、今では政治のコマと化し、実際の治安状況とは無関係にこうしてパワーゲームは続く。
少なくとも私たちのうち、誰か一人が殺されるまでは・・・。

パルワン県にあるプロジェクトサイトでコミュニティーの住人と撮影。
文化的理由のため、女性は子供も含めて写真に写りたがらず、ポーズしてくれるのは男性ばかり。

カブールの何気ない道端の光景。
舗装された道は非常に少なく、でこぼこ、泥だらけ、しかもごみが散乱という厳しい状況。
羊などの家畜もよく歩いている。