写真:実り始めたハトムギ
豊かな農村発展を目指して -新たな支援と市場につなげるための試み
農業支援における壁
農業を通じた農家の収益向上や地域の発展支援は、農家に対する技術指導が中心だ。だが、技術が向上し、作物の質や生産性を上げることができても、生産物を市場につなぎ、収益向上を達成するのは容易ではない。日本財団のこれまでの農業事業でも、同様の困難を抱えていた。そのような中、収益向上を目指し、技術指導から買い取りまでを事業の一環として、昨年ミャンマーにおいて実施した取り組みについて紹介したい。
農作物を確実に市場へ
対象は、ミャンマーのシャン州北部の2村だ。同州は、中国、ラオス、タイの3カ国と国境を接し、特に州北部では、中国の買付業者と農家の間で取引が行われている。現地農家によると、業者から種子や化学肥料、ホルモン剤が支給されるが、生産物は業者の言い値で買い取られてしまうことがあるそうだ。化学肥料を多用して同じ作物を繰り返し栽培していることで、土が痩せ、作物の生産性が落ちているという。中でも、農家にとって最大の懸念は、主要作物であるトウモロコシの価格の低迷だ。ある農家は、「価格が改善するまで、しばらく売らずに保管する予定だ」と語っていた。本事業では、このような状況に直面した12人の農家が各1エーカー(約4,047m2)の土地を利用し、現地の気候に適し、薬草として日本で需要の高いハトムギの栽培を行った。
本事業は、種まきから生育確認、収穫物の買い取りまでの一連のプロセスを、実際の栽培活動を通じてモデル化することが目的である。日本財団は、ハトムギを原料とした化粧品やサプリメントを製造している日本の製薬企業に業務を委託した。6月初旬に種まきを行い、専門家が月に1回、現地を訪問して生育状況の確認と技術指導を実施。ハトムギに限らず、広く作物に使用できる微生物活性酵素や堆肥づくりの指導も行った。微生物の力で、土壌環境を改善できることを説明し、化学肥料とのバランスの良い使用を農家に提案した。ハトムギは当初、生育状態にばらつきが見られたが、肥料の適正な追加や除草などの指導が実を結び、数カ月後には、どの農場でも順調な生育が見られた9月には実が付き始め、11月末に灰色に成熟。収穫物は製薬企業が買い取ったことで、農家は同じ作付面積でトウモロコシを栽培した場合に比べ、約3倍の収入を手にすることができた。
本事業が順調に推移した要因としては、主に2点が挙げられる。1点目は、実施地域に適性があり、市場性のある作物を選定したことだ。お茶や化粧品などに幅広く利用されるハトムギは、東南アジアが原産で、初めての農家でも簡単に栽培することができた。2点目は、企業と協働し、生産物の買取計画を事前に立てたことだ。これにより、確実な利益創出を図ることができた。しかし、企業の経済活動が関与する事業連携は、財団法人やNPOなど非営利組織の活動においてはあまり例を見ない。これには、非営利組織の実施する事業が、特定の企業の営利活動につながることに対する否定的な見方があることによるものと思われる。だが、農業とは、農家が生活をしていくための経済活動であってこそ成り立つ。だからこそ、技術指導のみでなく、必要に応じて作物を市場につなげる支援にまで踏み込むことに意味があると考える。また、市場経済の動きを無視していれば、支援活動の意味がなくなる。それゆえ、このような支援を営利活動に結び付けることは、支援目的を達成し、成果を持続させるために重要である。
そして、企業ならではのビジネス的視点は、支援する上で大いに有益になり得るという実感を得た。例えば、買い取りのためには、種の管理から適切な肥料の使用、無農薬であることや収穫後の水分含率の調整まで、農家はさまざまな品質面の条件をクリアする必要があったが、企業の技術指導でこれらを達成できた。このようなノウハウは、作物や買取先が変わっても活用できるだろう。また、市場で現実的な価格を定めることができたことも大きい。農家の収入向上はもちろん、同時に一般企業として黒字が見込める価格にすることは長期的な関係を維持するために不可欠だ。このように、利益と社会貢献の両方を求める企業との協働の幅を広げることで、事業成果の最大化を図ることができたと考える。
地域を支える人づくり、人を支える地域づくり
今回の事業を経て、今後の課題も浮き彫りになった。モデル作りと位置付けた本事業では、収益向上を達成し、農家は新たな作物の栽培法の習得や製薬企業との取引への意欲を強くした。だが、今後の鍵となるのは、新しい知識や技術ではなく、農家自身が生活や地域の未来を考えていくことができるかどうかだ。そのきっかけをつくることこそが、本事業が最終的なゴールだろう。
化学肥料は、作物に栄養素を補給し、すぐに効果が現れるという利点があるが、過剰に使用すると微生物を減らし、生産性の低い土壌を作り出してしまう危険性がある。一方、堆肥は、土壌に働き掛け、作物の生育環境そのものを改善できるが、効果が現れるのは遅い。支援する側として日本財団が目指すのは、即効性はあるが、一時的な栄養補給にすぎない化学肥料を農家に提供するような支援ではなく、作物の生育環境そのものにアプローチする、まさに堆肥のように、自身と地域に働き掛ける原動力を農家自身が発揮するための手伝いをすることだ。この点を今後のテーマとして、事業として何ができるかを考えていきたい。
-
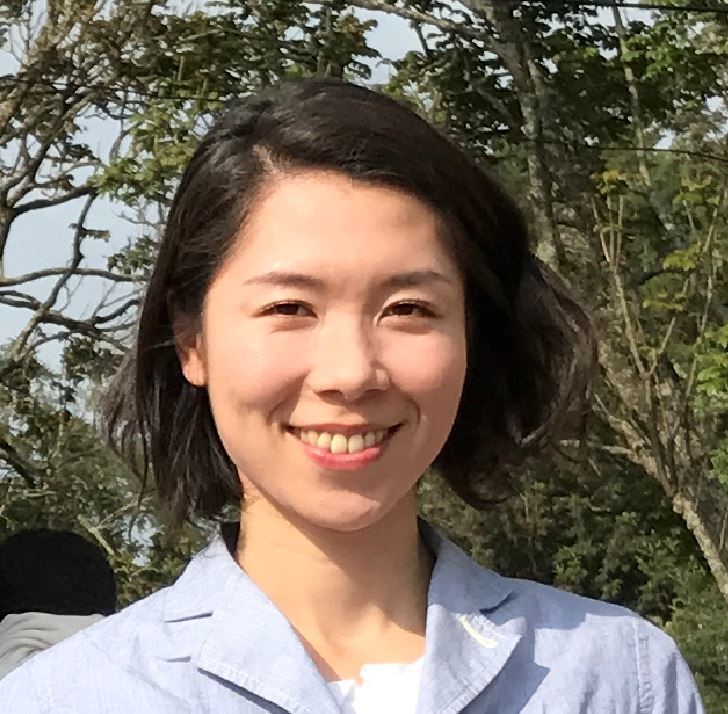
-
profile
日本財団 国際事業部 国際協力チーム 栗林 智子氏
山口大学農学部卒業。開発途上国の農業や畜産を通じた事業に関心が あり、2015年に日本財団に入職。主にミャンマーやアフリカの農業事業を 担当している。趣味は、ヒップホップダンスとハイキング









コメント