写真:インパール平和資料館。1994年に建立されたインド平和記念碑から数百メートル離れた所にある。八角形の建物が特徴
「インパール作戦」の記録と記憶を残す -インドで平和資料館の建設を支援
6月にセレモニーを開催
遠くに連なる山脈とその裾野にまで広がる畑。所々には農家の集落が見える―。東南アジアでよく目にする田園の風景を前に、私は「75年前もこの風景を日本兵は見ていたのだろうか」と考えた。ここはインド北東部にあるマニプール州の州都、インパール。第二次世界大戦中の1944年3月に日本軍が決行した「インパール作戦」で有名な場所だ。ビルマ(現在のミャンマー)から当時英国軍の拠点であったインパールの攻略を目指したこの作戦では、両軍の間で熾烈な戦闘が勃発した。多くの命が失われ、敗れた日本軍は筆舌に尽くしがたい敗走を強いられた。
そのインパールで戦争に関する資料館を建設する支援を行う案件を引き継ぎ、プロジェクトマネージャーに着任したのは、2017年6月のことだ。この案件は、(公財)笹川平和財団の中村唯主任研究員と高橋亜友子研究員、そして沖縄県の南風原町立南風原文化センターの元センター長である大城和喜氏が深く関わり、在インド日本国大使館の綾賢治一等書記官にもサポートいただいた。他方、私は歴史の専門家というわけでなく、これまで外国で資料館の立ち上げに携わったこともなかったが、試行錯誤を経て、「インパール平和資料館」は2019年6月22日、無事オープニングセレモニーの開催にまで辿り着くことができた。平和資料館はインパール中心部から11㎞程の所にあり、激戦区となった通称「レッド・ヒル」の麓にある。
日本での研修通じて現地の主体性を向上
資料館の建設はもともと、インパールの人々が有志として集まり、構想・企画していた。その後、マニプール観光協会がこの構想のとりまとめ役となり、2017年の夏、日本財団と助成契約を締結した。だが私が案件を引き継いだ時、展示内容の検討は有志の一人の男性に任せきりであった上、資料館の運営体制についてもほとんど考えられていなかった。このままいけば、たとえ開館しても1年と経たず閉館になるのではと強い危機感を抱いた。
そこで2018年10月、現地を訪問した際に関係者に対して、「誰か一人の案ではなく、皆さんが納得して地元から支えられるような資料館を作りませんか」と説得した。そして建設のために12人の委員で構成される組織を立ち上げ、戦中・戦後・文化風習の3つに分かれて展示内容を検討することとなった。しかし、委員の多くは本業を持っており、資料館を立ち上げた経験も無かったので、2019年2月25日~3月1日にわたり、委員の中心メンバー5人を日本に招聘し、東京と沖縄の資料館などを視察する機会を設けた。日本の事例を実際に目にすることにより、彼らは資料館の運営や展示、そして学芸員の育成などの課題に気づくことができた。こうした気づきは、彼らの主体性を生むきっかけになったほか、私としてもこの招聘を通じて委員の人となりや考え方を知ることができ、彼らとの関係を深めることができた。それまでもメールやコミュニケーションアプリを通じて連絡を取り合っていたとはいえ、直接会って話をすることの重要性を実感した。母国に帰国後、委員のコミットメントはさらに深くなり、事業のスピードは一気に加速した。
日本の遺族にも呼び掛け
ただ、インパール作戦では日本軍が敗走したため、現地には資料館に展示するための紙の資料や写真などはほとんど残されていなかった。そのため、日本国内に展示品の寄贈を呼び掛けた。これには、インパール作戦から75年を迎えるにあたり、ご遺族に寄贈を通じて故人に想いを寄せたり、作戦のことを思い出したりしてほしいという狙いもあった。全国から多くの資料や遺品などが送られ、「亡くなった父親もきっと喜ぶと思う」と涙を流して語ってくれたご遺族は一人や二人ではなかった。
また、親族などに復員兵がいない人たちにもこの歴史について考えてほしいと、資料館の運営を補助するための寄付も募っている。多額の寄付は望めないが、「日本財団だけではなく、多くの日本人が資料館を支えている」ことを現地に示すことは出来る。それによって、現地の人たちに大きな責任を感じてもらいたいと思っている。
円滑な運営のための側面支援
よく、日本の国際協力を揶揄する言葉として「箱物を作るのは得意だが、持続しない」と聞く。この資料館についても、民設民営となるため開館後の継続的な運営は大きな課題だ。もともと、建物の建設は日本財団が支援し、運営はマニプール観光協会が行う予定だったのだが、同協会は地元の経済界を代表する方々から成る団体であるが故、これまで資料館を運営した経験は無い。そんな彼らは、日本を訪問して各地の資料館の運営に関するヒアリングを行った際、自分たちの運営計画が十分に練られていないことに気づいたのだ。
このため、日本財団は開館前から運営の側面支援を行った。具体的には、インド北東部の文化交流事業などを実施している笹川平和財団を通じた専門家の派遣、学芸員の育成や戦争経験者の証言記録の収集である。無論、自立運営を促すことが望ましいが、現地の状況を鑑みずに突き放してしまうことで全てが無駄になる可能性が高ければ、支援のあり方は柔軟であるべきだと思う。
インパール作戦から75年。この出来事をどう解釈するかは難しい問題であるが、何もしなければ記録と記憶は消え去ってしまう。だからこそ、日本財団は資料館の建設と運営の側面支援を行っている。この責任を背負い、私はさまざまな関係者と連携・調整し、時には黒子となり、時には前面に立って事業を進行してきた。セレモニーを見届けた今は、資料館が末永く運営されることを期待している。そう遠くない将来、資料館を訪れた日本人がインパール作戦で亡くなった方々と資料館建設に携わったわれわれに思いを馳せてももらえれば、本望である。
-

-
profile
日本財団 特定事業部 特定事業推進チーム 和田 真氏
ワシントンDCにて国際関係学の修士号を取得後、2005年、日本財団入会。
海洋関係、広報部を経て、19年6月より特定事業推進チームにてハンセン病の制圧と差別撤廃、開発途上国の農業支援を所掌
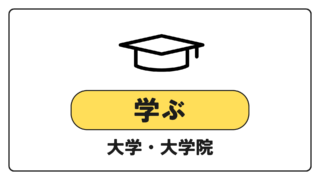
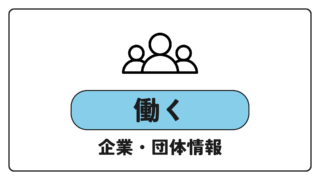
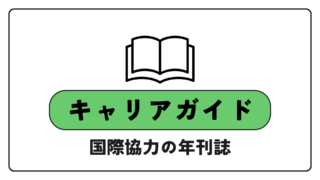
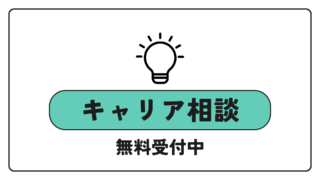





コメント