(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 代表取締役社長 米澤 栄二氏
1985年、(株)オリエンタルコンサルタンツに入社。執行役員GC事業本部道路交通事業部長、(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル代表取締役常務役員などを歴任後、2015年10月から現職。(一社)海外コンサルタンツ協会(ECFA)の副会長も務める
現地法人の活用進め、非ODAシェア拡大を目指す
連載「コンサルタントの展望」は、開発コンサルティング企業のトップに今後の戦略をはじめ、政府開発援助(ODA)への展望を語ってもらうリレー連載だ。第二回目は(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル代表取締役社長の米澤栄二氏に非ODA案件拡大への戦略を語ってもらった(聞き手:本誌社長・末森 満)
ソフト系の案件に注力
―政府開発援助(ODA)の現状をどう捉えていますか。
政府の方針もあり、インフラ輸出関連事業が主軸となっている。当社もフィリピン、インド、ミャンマーなどで鉄道関連の大型案件を手掛けており、2016年以降の受注額は増加傾向である。 一方で、ODAのみに依存していては企業の長期的な成長は難しい。これまでも非ODAへの取り組みを行ってきてはいたが、国際協力機構(JICA)の資金不足問題でODAへの偏重はリスクがあると再認識した。当社は円借款のハード系事業を多く手掛けているため影響は限定的であったが、ソフト系を主に手掛ける開発コンサルティング企業にとっては厳しい状況であっただろう。
―現在、売上高全体に占めるODAの割合はどのくらいですか。
9割程度だ。アジア圏の案件が主で、鉄道を中心とした運輸・交通分野が7割以上を占める。こうした業務における偏りが最大の課題だ。当面はODAの仕事を優先的に手掛けつつ、徐々に非ODA案件の受注も増やしていきたい。具体的には、売り上げのシェアをODAが6割、その他の事業が4割になるまで持っていき、「二本足」で事業を行える状態にしていくことを目指している。
―事業拡大の具体策は。
エネルギー、上下水、民間建築分野を強化するなど、分野の多角化を行う一方で、マスタープランの策定事業など、ソフト系の案件の受注も引き続き拡大したい。特にマスタープランの策定支援においては、派生案件であるインフラ整備案件に対して優位に取り組むことが可能となる。ミャンマーで当社は2012年に「ヤンゴン都市圏開発マスタープラン」、2014年に「ミャンマー国全国運輸交通プログラム」の作成に携わった。現在、「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業」「ヤンゴン環状線整備事業」に取り組んでいるが、これは全国運輸交通プログラムや都市圏開発マスタープランから派生した案件だ。 インドやアフリカには、まだマスタープラン策定支援へのニーズがあり、アジアでも既存のマスタープランの見直しがあらゆるところで必要になってくると見ている。これらを積極的に手掛けることにより、円借款の大型案件の受注につなげられる可能性は高い。
―非ODA案件の獲得に向けてはどのような施策をお持ちですか。
真っ先に取り組んだのが、現地法人の設立だ。これまでインド、インドネシア、ミャンマー、タイ、フィリピン、カタール、ウガンダの7カ国に現地法人を設立した。9月にはパナマに現地法人を設立し、中南米のシェアを拡大していく予定だ。これら現地法人を通じて、開発金融機関や各国政府、民間の案件へと裾野を広げていく。アジア開発銀行(ADB)や世界銀行、現地政府、民間等の大型案件を獲得したいと思っても、日本
のコンサルティング会社単独では価格面も含めて世界の競合たちに勝てない。現地法人の設立や他のコンサルティング会社との提携を介して、実績作りや価格を抑えるなどの対応が不可欠だ。
例えば、フィリピン国内外で、農業や医療をはじめとしたソフト分野の案件や、ADB案件を多く手掛けるフィリピンのコンサルティング会社PRIMEXの株を今年8月に40%取得し、連携強化を進めている。こうした取り組みを通して、上下水やエネルギー、建築などへと総合的に広げていきたい。 加えて、現状ではアジア中心だが、今後はアフリカや中南米、中東への取り組みも強化する。そのため、欧米の開発コンサルタントとの連携強化も進めている。すでに米AECOMや豪SMECと覚書(MOU)を交わし、定期的に情報交換を行っているほか、SMECとは人事交流も行っている。
―現地法人を数多く持っていますが、人材確保や運営面でどのような工夫をされているのでしょうか。
人材面では、主にローカルで採用・育成したエンジニアが活躍している。将来は、現地で育成した人材を別の第三国に派遣して事業展開をできるようにもしたい。専門性が高いエンジニアには、プロとして国際的に活躍してほしい。 ビジネスの形態は、国民性などによって変えている。例えば、タイの現地法人はデザインセンターとしての役割を果たしている。タイ人は高い技術力がある一方、国外に出たがらない傾向があるため、世界各国で発生した設計業務をタイで請け負っている。他方、フィリピンは国外に出ることを厭わない人が多く、フィリピンを拠点に世界各国のプロジェクトに人材を派遣するリソースセンターと位置付けている。日本からのトップダウンではなく、各法人がその特色を活かし、メタナショナルな形態をとりながら、共に成長してくことを目指している。
維持管理の経験生かせ
―今後の業界についてはどのような展望をお持ちですか。
日本の開発コンサルティング企業には、まだまだ世界的に活躍できる余地がある。EngineeringNews-Record(ENR)が今年7月に発表した開発コンサルティング企業の売上トップ225社の総売り上げは7.2兆円に上ったが、日本企業の売り上げはその1 %(720億円)に過ぎなかった。日
本が世界第三位のGDPを有する国であることを考えると、このシェアは非常に小さい。シェアを拡大させるためには、実績や価格面などでの競争力を強化する必要があると考える。
もう一つ、今後のために備えておくべきは、東南アジアで高まるインフラの維持管理に対する需要への対応だ。中でも、鉄道の運営・保守(O&M)に関するニーズが高まっていくだろうと見ている。今年3月、日本のODAを受けてインドネシア・ジャカルタで初の都市高速鉄道(地下鉄)が操業した。本事業は鉄道の建設と並行して、日本から運営維持管理コンサルティングサービスも提供されていることが特徴的である。今後も、多様な分野でO&Mといった維持管理は重要になっていくはずだ。
今までは「作る」ことばかりに一所懸命になっていたが、この先は「維持管理」で日本が培った経験を生かせる可能性がある。こうした日本の強みを生かして、海外に出ていけるだろう。来るべき時に備えて今からできることに取り組んでいくべきであろう。
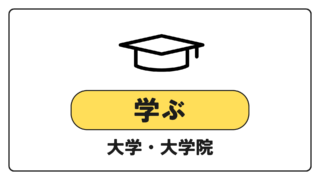
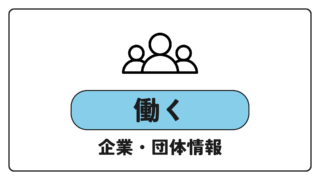
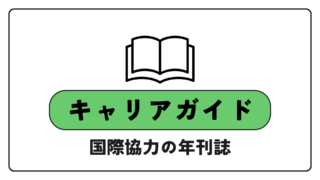
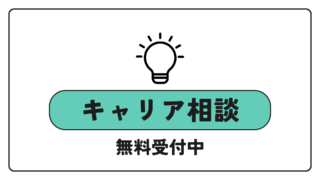


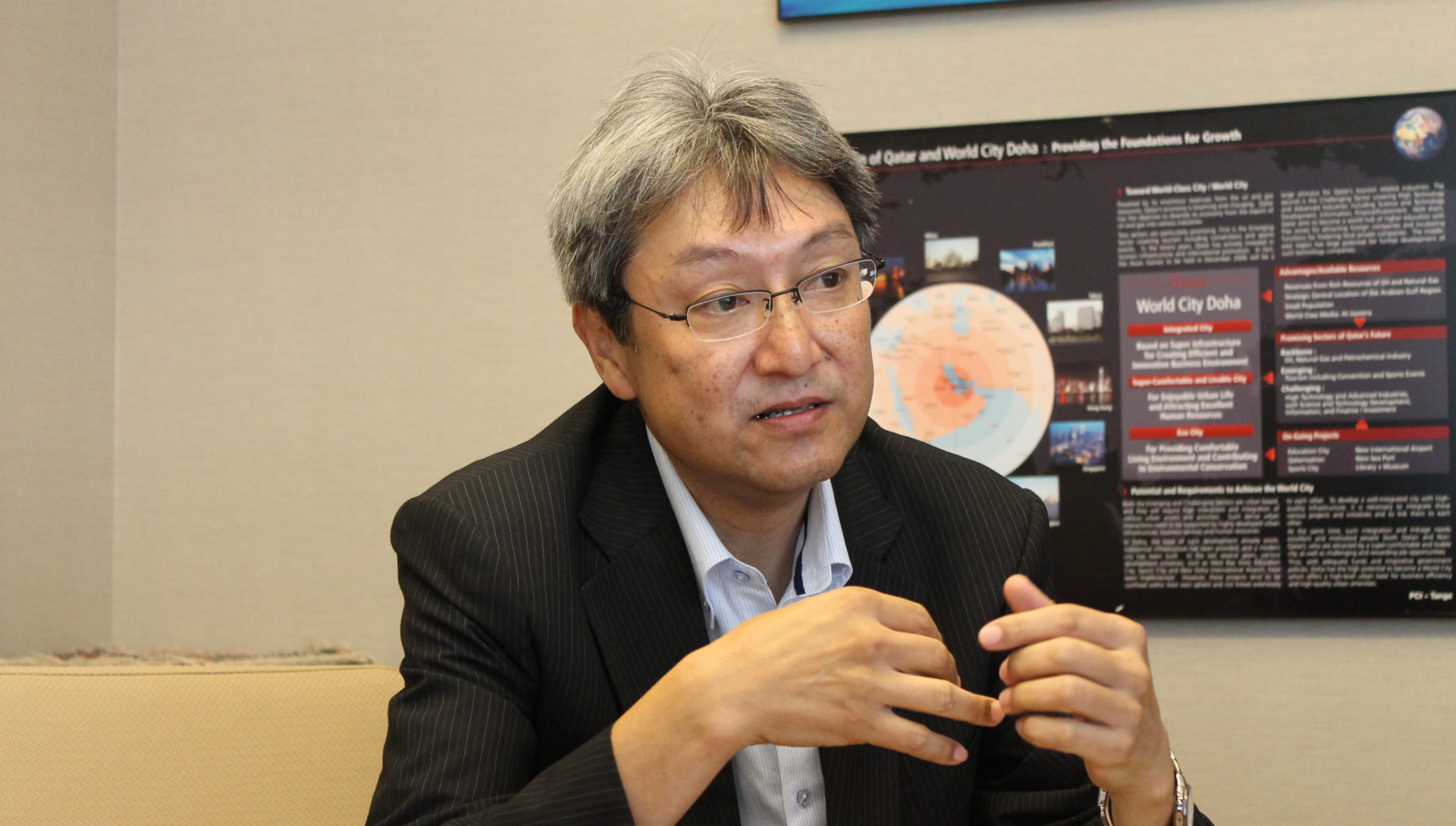


コメント