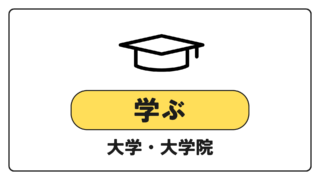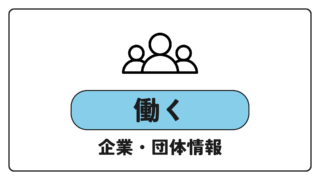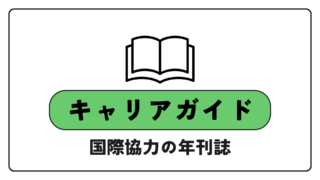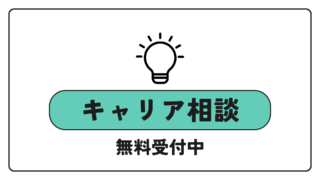アフリカと日本の双方向の交流を促し、共にSDGs達成に貢献
アフリカは「SDGs の最前線」
主専攻として 15 地域 28 言語の教育体制を備え、さらに授業で 53 言語を学べる東京外国語大学。世界の言語や文化に根差した多様性を追究し、「共生」のための力に変えることを目指す同学は今年、建学から 150 周年を迎えた。
日本で唯一、同学は学部レベルでアフリカ地域専攻を有し、ガーナ、ルワンダ、南アフリカ共和国などの13大学と連携協定を結んでいる。学部、大学院共に交換留学が活発に行われており、2024年度には、カメルーンの大学も連携に加わる予定だ。
長年のアフリカ研究の蓄積を生かすべく、2017 年4月に学内研究拠点として現代アフリカ地域研究センターを設立した。「アフリカでは持続可能な開発目標(SDGs)の 17 の課題すべてが重要で、まさに SDGs の最前線です。そうした諸課題はグローバルイシューとして先進国にも影響し、先進国が率先して解決に取り組むべきものです」と、武内進一センター長は話す。
同センターの目的は「人の往来をベースとして、研究と教育をつなぐ」(武内センター長)ことだ。今年はアフリカの協定校から交換留学生を合計 8人招き、東京外国語大学からは 11 人がアフリカへ渡っている。コロナ禍を乗り越えて、双方向の留学が再び始まった。
留学生交流会やセミナーで意見交換
アフリカから来る留学生は、日本の文化や第二次世界大戦後の復興経験に関心を持っていることが多いという。日本へ渡航する場合、高額な航空券代が障壁となっており、以前はクラウドファンディングや日本企業の支援だけが頼りだった。「2020 年に文部科学省の『大学の世界展開力強化事業』に採択されたため、補助金で航空券代を支援できるようになりました。母国から奨学金を得て本学の大学院に進み、より深く研究しようとする留学生も少なくありません」(武内センター長)
同センターは、コロナ禍の前から定期的に留学生交流会やオープンランチを開き、日本人学生やクラウドファンディングの出資者も参加して意見交換をしてきた。さらにガーナ、ルワンダ、南アフリカ共和国の大学との共同セミナーなどを通じて研究ネットワーク構築を進めるほか、アフリカ研究者を招いて頻繁にセミナー・シンポジウムを開催している。
武内センター長は「アフリカに関する報道が少ないこともあり、日本とアフリカのつながりを意識できない人が多くいます。そのためアフリカ各国と本学の双方向の交流を促し、発展に向けた課題について議論し合うことを目指しています」と語る。SDGs の最前線であるアフリカから、われわれが学ぶことも多いはずだ。
※グローバル化の時代、大学・大学院など高等教育の現場でも国際化が進んでいます。このコーナーでは、アジアをはじめ世界とのさまざまな「知的交流」に向けた取り組みや国際協力を学べる大学を紹介します。情報提供お待ちしています。
学校データ
・名称:東京外国語大学現代アフリカ地域研究センター
・所在地:〒183-8534 東京都府中市朝日町3-11-1東京外国語大学 研究講義棟 401E2
・連絡先 :T 042-330-5540/F 042-330-5884
・メール:asctufs.ac.jp