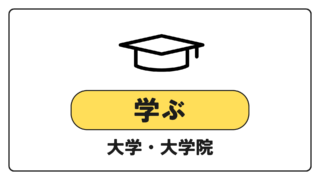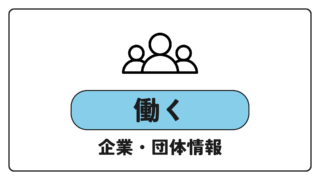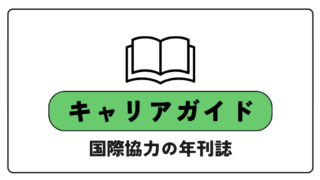開発途上国での研究機会を重ねて教育の専門家を育成
2019年度より新大学院を開始
8年連続教員就職率全国1位の実績を誇る教師教育の名門・鳴門教育大学は、開発途上国の人材育成にも豊富な実績を有する「大学の国際化」のフロントランナーだ。国際協力機構(JICA)と連携して、1999年に南アフリカの教員を研修員として初めて受け入れたのを皮切りに、2005年には「教員教育国際協力センター」を設置。途上国の教員研修に組織的な取り組みを展開してきた。現在まで62カ国1,000人を超える短期・長期のJICA研修員を受け入れている。
そんな同大学の大学院では、2019年度から新たに「グローバル教育コース」を開始する。研修員の受け入れ経験を生かして、2008年から「国際教育コース」で日本人学生・留学生双方を対象に途上国の教育開発の未来を担う国際教育協力の専門家育成に注力してきた同大学院だが、昨今の日本への留学生増加などを受けて、コースを進化させる形だ。
具体的には、従来の国際教育協力の分野に、日本語教育・日本文化分野、英語コミュニケーション・異文化理解分野、国際理数科教育分野を加えて再編する。「世界から学び、世界とともに考え、世界で教える人材」をスローガンに掲げ、より実践的な学びを提供し教育現場と海外で活躍できる専門家を育成する方針だ。
積極的に開発途上国の現場へ学生を
鳴門教育大学では、開発途上国から研修員を受け入れるにあたって学内予算も投入して相手国についての資料収集や現地調査を丹念に行い、研修内容の質を高めてきたほか、研修後もフォローアップとして現地調査などに出向くなど、「鳴門教育モデル」を確立させてきた。その結果、2017年にはモザンビーク教育大学と大学間交流協定を結ぶまでに至っている。
だが、興味深いのは、こうした現地調査に大学院生も同行させてフィールド研究の機会を提供している点だ。JICAの青年海外協力隊事業とも連携して、ジャマイカに短期ボランティアとしても学生を派遣したり、大学がボリビアで行っている草の根事業などにも学生を同行させたりしている。学生が開発途上国の現場に赴き、開発プロジェクトや相手国の教育関係者と接する機会を積極的に作りだしているのだ。
今後、「グローバル教育コース」ではこうした取り組みをさらに加速させる。小澤大成教授は「教育分野で国内外にこだわらず教室レベルの現場のことを理解しながら、大きな教育の枠組みの改善などに取り組めるグローバルな人材を輩出していきたい。大学の予算を割いてでも積極的に開発現場に学生を連れていくことには大きな価値がある」と思いを語ってくれた。
※グローバル化の時代、大学・大学院など高等教育の現場でも国際化が進んでいます。このコーナーでは、アジアをはじめ世界とのさまざまな「知的交流」に向けた取り組みや国際協力を学べる大学を紹介します。情報提供お待ちしています。
『国際開発ジャーナル2019年3月号』掲載
(本内容は、取材当時の情報です)