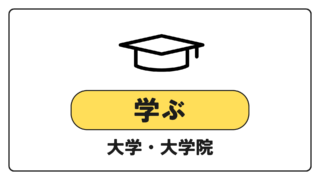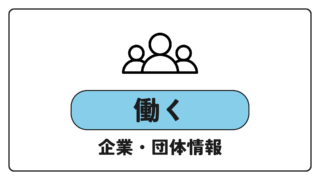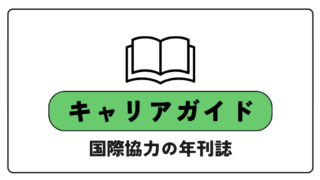国際平和協力に貢献する人材の育成魅力
国連平和維持活動(PKO)という言葉を聞くと、自衛隊を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、実際の現場では、各国の軍事要員と並んで、文民の専門家が平和のために汗を流している。
日本は1992年に制定された国際平和協力法に基づいて、世界各地の国連PKOに参加してきた。その中で、国際平和協力分野で活躍する文民の人材育成の必要性が高まったことを受けて、内閣官房長官主催の「国際平和協力懇談会(座長:明石康元国連事務次長)」の提言を受け2005年に内閣府国際平和協力本部事務局(以下、事務局という。)に設置されたのが、国際平和協力研究員制度だ。
その目的は、①国際平和協力分野の人材育成、②同事務局の機能強化の2つ。研究員の対象者となるのは、相応の関連業務経験があり、引き続き国際平和協力の分野に貢献する意志を持つ人とされている。
採用後は、非常勤の国家公務員として最長2年間、国際平和協力に関する調査・研究・実務と同事務局の支援業務に従事する。多様なバックグラウンドを有する同僚とともに、多分野の人脈形成や次の開拓を目指していく。研究発表や情報収集・分析に加えて、事務局が実施する一般向けイベントやさまざまな啓発活動に講師として参加するなど、業務の幅は広い。
退職者の多くが国連や国際機関など、平和構築の最前線で活躍するなど、キャリアアップの機会となっている。その活躍は、国際的な平和構築分野での日本のプレゼンス向上にも寄与している。
退職者の約半数が国際機関などに就職
2005年度の発足から2021年度まで、計71人が国際平和協力研究員として在籍しています。この約4分の3が女性です。なお、研究員着任時の平均年齢は34.5歳です。
退職者の進路をみると、国際機関などへ就職した人が48%と約半数に上り、大学・シンクタンクなど17%、日本などの政府関係12%、民間企業10%、NGO7%などとなっています。
具体的な進路では、国連・アフリカ連合合同平和維持活動部隊政務官、国連コソボ暫定行政ミッション政務官、国連スーダンミッション選挙担当官、国連アフガニスタン支援ミッションガバナンス担当官、国連難民高等弁務官事務所アフガニスタン事務所難民保護官などがある。
研究と実務、議論が魅力
ラジャイ麗良さん(国際平和協力研究員)
国際教育協力に関心を持ったきっかけは、アフガン難民の女性との出会いです。学校に通うことができず、また望まぬ結婚を余儀なくされた彼女は、「子どもには教育を受けさせたい」という夢を強く持っています。彼女との交流を通じ、国際的な教育支援に携わりたいと強く思うようになりましその後、スリランカの国連ボランティア計画事務所で、青年担当官として活動しました。
平和構築事業の一環として、民族間の和解を進めるために若者対象のワークショップなどを行い、異文化理解、平和につながる教育に興味を持ちました。
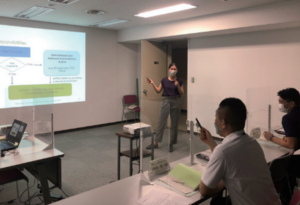
国連PKO派遣前の研修で説明するラジャイさん。
このような経験から、事務局では平和構築のための教育支援について研究しています。国際平和協力研究員は、研究と実務に携わることができることが非常に魅力的です。研究の他に、国際平和協力隊員の派遣前研修も担当しています。派遣隊員との交流や研究員同士で話し合う機会も、今後のキャリア構築において非常に有意義だと感じています。
略歴
愛知県立大学卒、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科修士課程修了。筑波大学教育開発国際協力研究センターにて勤務後、国連ボランティア計画(UNV)スリランカ事務所にて青年担当官として平和構築事業に従事。2021年4月より現職。
平和を作る舞台裏を知る
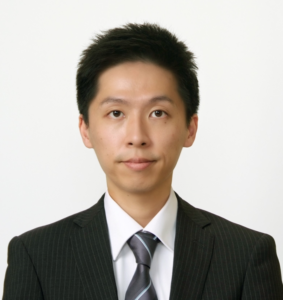
大瀧千輝さん(国際平和協力研究員)
フランスで災害や紛争から逃れてきた外国人に出会い、災害や紛争について勉強を始めました。ハイチで支援活動をした後、在ハイチ日本大使館にて勤務しているとき、市民が虐殺される事件が相次ぎましたが、それを止めることはできませんでした。これを機に「人権保障と平和構築」というテーマを考えるようになり、この研究員のことを知りました。
研究テーマの1つが、SNSや公開情報を使って人権侵害や虐殺などを調査する民間の動きです。オランダでは、こうした活動で集められた証拠が検察に提出され、検察が訴追するという連携も生まれています。一方で、こうした動きが拡大したとき、現場や国際関係にどのような影響があるか、まだ分かりません。

陸上自衛隊国際活動教育隊への許育訓練支援(右が大瀧さん)
過去の経験から文民が考える平和維持と軍人が考える平和維持には、マインドセットの違いを感じ、平和を作る現場の多様さを身を持って知りました。今後、研究もより深められると考えています。
略歴
京都外語大学フランス語学科卒。大阪大学大学院(言語文化)、アテネオ・デ・マニラ大学大学院(社会開発)、国連平和大学(国際法と人権)修士課程修了。ハイチでNGO活動の後、在ハイチ日本大使館専門調査員。2022年3月より現職。
問い合わせ先
内閣府国際平和協力本部事務局 人材育成担当
〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館8階
Tel:03-3581-2550 Fax:03-3581-0824
Mail: ホームページの「御意見等」欄から問い合わせが可能
『国際協力キャリアガイド22-23』掲載
(本内容は、取材当時の情報です)