国内で知識と実学を積み重ね
国際協力のリーダーを目指す
多様な「つながり」を国際協力へ
日本大学は、知的好奇心を持って学生自ら課 題に取り組み、新しい道を切り開いていく「自主創造」の理念を掲げ、1都4県に 16 学部を有する。実は、国内で初めて「国際関係学部」を 創設したのも同大学だ。グローバリゼーション の本格的な到来を見通し、1979 年に富士山を望 む静岡県三島市に創設した。
同学部は、国際総合政策学 科と国際教養学科で構成されている。国際総合政策学科の 鈴木和信教授は、「国際協力には先進国と開発途上国、国・ 企業・市民組織の連携、分野間の連携など多様な『つなが り』があります。こうしたつながりを自分ごととして捉え、 周囲に目配り・気配りをしな がら関係者を少しでも幸せに できる人材に育ってほしいです」と学生たちに期待を寄せる。さらに環境問題・人口問題・食料問題などを考える上での基礎となる社会科学の知識を習得し、日本を含めた各国の文化理解を深めることで、問題解決に向けて他国とコミュニケーションをとり、積極的に役割を果たせる人材の育成を目指すとも語っている。その上で海外留学も積極的に推進し、国 際関係学部でも「派遣交換留学・中期留学」のようなプログラムがある。
新型コロナウイルス感染拡大により、一時、 海外留学プログラムを中止していたが、2022 年から再開。現在は米国、オーストラリア、フィリピンなど5カ国に8人が留学している。
富士山ろくで環境保全体験もできる
鈴木教授の専門は環境学だ。「地球環境と持 続可能な開発」「都市環境論」「国際協力論」などの科目を担当し、プラスチックごみ問題や 国境を越えた環境汚染防止など、国際協力機構(JICA)の途上国支援について取り上げている。「JICA 事業を紹介する際 は、なぜ日本が支援するのか、 地域にどう貢献しているかに意識して触れています。また、 国際協力の実務につながる『実 学』は、日本のさまざまな地 域にあるというのが私の考え です。環境関連の企業訪問や富士山ろくでの環境保全体験 など、外部と交流する機会もつくっており、授業やゼミナー ル活動の中でコミュニケー ション能力や課題解決能力を高める工夫に取り組んでいます」(鈴木教授)
鈴木教授は、若いうちに身近な「実学」を学んでほしいと強調する。身近にある小さな課題を解決できなければ、時にシステムを変革したり、街全体を変えたりする国際協力に挑めない からだ。日本のキャンパスで知識を習得しなが ら、企業訪問などで身近な「実学」を積む機会も復活しており、そうした実学を活かして世界的な課題解決のリーダーになるという好循環を、同学部では推し進める。
※グローバル化の時代、大学・大学院など高等教育の現場でも国際化が進んでいます。このコーナーでは、アジアをはじめ世界とのさまざまな「知的交流」に向けた取り組みや国際協力を学べる大学を紹介します。情報提供お待ちしています。
『国際開発ジャーナル2023年3月号』掲載
(本内容は、取材当時の情報です)
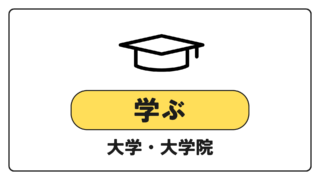
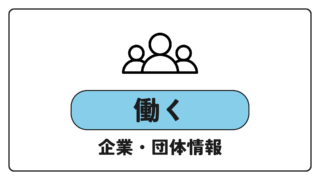
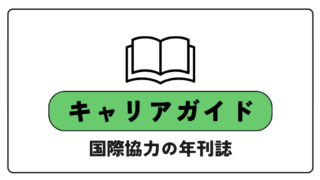




-120x68.jpg)