「東海大学 国際学部国際学科 *2022年新学部開設」
先生に聞きました!
教養学部国際学科 准教授 田辺 圭一先生

世界食糧計画(WFP)や国連PKOの職員として、ミャンマーやアフガニスタン、南スーダンで紛争後の復興を担う仕事をしました。現場での経験をもとに、世界の課題をよりリアルに実感し、立体的な理解につなげる教育を心掛けています。担当する授業「人間の安全保障」は、東西冷戦が終わって数年経った1994年に国連で取り上げられた言葉で、一人一人の人間に焦点を当て、現在の多様性を尊重する考え方に結び付いています。国際学科の学生は好奇心旺盛で、英語圏に限らず多様な国で海外研修やインターンに参加しています。国内の課題に目を向け、在日外国人の子どもたちに日本語を教えながら、日本語教師の資格取得を目指す学生もいます。東海大学は規模が大きいですが、少人数のクラスで学生と教員が密にコミュニケーションを取りながら学びを深めているのが特徴です。大使館や国連、NGOなどさまざまなバックグラウンドを持つ教授陣が全力でサポートします。さらに学びを深めたい学生のために大学院進学も推奨しています。
学生さんに聞きました!
教養学部 国際学科1年 アカンド ユキさん
 バングラデシュ人の両親の下に生まれ、小・中学生はバングラデシュで暮らしました。幼少期を日本で過ごしていたので、スラム街で生活する人々の存在に衝撃を受け、特に同世代の女の子が出産する姿に驚きました。生まれた環境によって人生が左右される不条理に戸惑い、なんとかしたいと思うようになりました。他方、日本に戻ってから高校の授業に付いていけず、外国人を支援するNPOの塾に通っていました。その時、日本語を教えてくれたのが、東海大学の学生です。その出会いをきっかけに東海大学のオープンキャンパスやボランティア活動に参加し、学生の挑戦を応援してくれる環境に惹かれて入学を決めました。現在、性的少数者「LGBTQIA」について勉強しています。バングラデシュで性的少数者は差別を受け、逮捕されるケースもあります。将来は国連や国際協力機構(JICA)の職員として、あるいは起業して社会の問題を解決したいです。日本で暮らす外国の子どもたちへの支援も続けたいし、習っているキックボクシングをマスターしてバングラデシュの女性たちに護身術を教えたい。他にも夢がたくさんあります。新型コロナウイルス感染症の影響で授業はオンラインが中心ですが、周囲の友人は皆やりたいことにチャレンジしています。放課後は一緒に宿題をしたり料理を作ったり、刺激を受けながら日々を過ごしています。
バングラデシュ人の両親の下に生まれ、小・中学生はバングラデシュで暮らしました。幼少期を日本で過ごしていたので、スラム街で生活する人々の存在に衝撃を受け、特に同世代の女の子が出産する姿に驚きました。生まれた環境によって人生が左右される不条理に戸惑い、なんとかしたいと思うようになりました。他方、日本に戻ってから高校の授業に付いていけず、外国人を支援するNPOの塾に通っていました。その時、日本語を教えてくれたのが、東海大学の学生です。その出会いをきっかけに東海大学のオープンキャンパスやボランティア活動に参加し、学生の挑戦を応援してくれる環境に惹かれて入学を決めました。現在、性的少数者「LGBTQIA」について勉強しています。バングラデシュで性的少数者は差別を受け、逮捕されるケースもあります。将来は国連や国際協力機構(JICA)の職員として、あるいは起業して社会の問題を解決したいです。日本で暮らす外国の子どもたちへの支援も続けたいし、習っているキックボクシングをマスターしてバングラデシュの女性たちに護身術を教えたい。他にも夢がたくさんあります。新型コロナウイルス感染症の影響で授業はオンラインが中心ですが、周囲の友人は皆やりたいことにチャレンジしています。放課後は一緒に宿題をしたり料理を作ったり、刺激を受けながら日々を過ごしています。
(本内容は、取材当時の情報です)
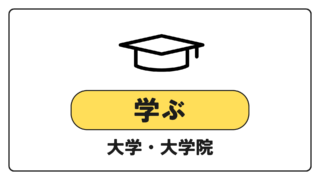
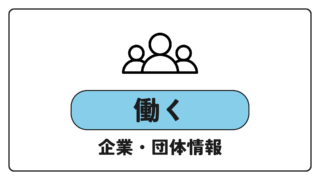
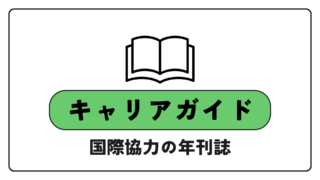
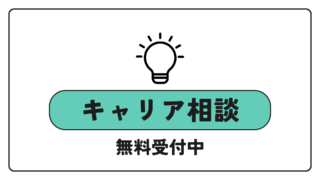



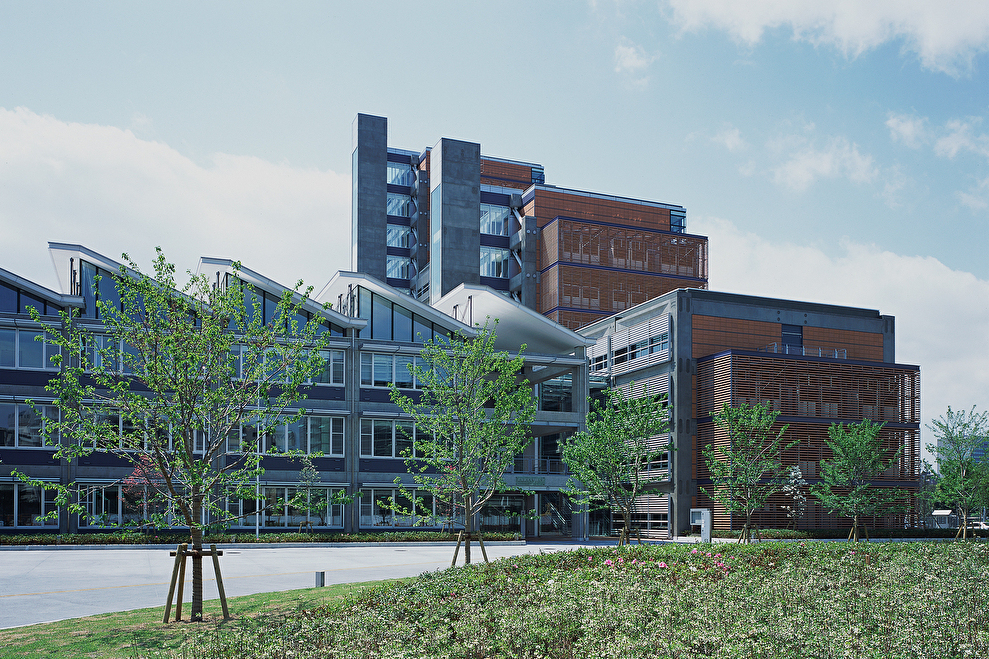

コメント