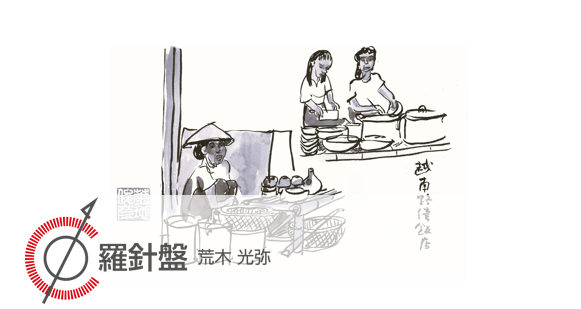グローバル・パワー
「日本の科学技術外交」という題名の講演会が、本田財団主催で開かれた。講演者は、最近話題の「国家の勢い-技術の“坂の上の雲”モデル」(NTT出版)を書いた薬師寺泰蔵氏である。
科学技術政策を論じると、すぐに談論風発する人物だが、氏は1968年慶應義塾大学工学部、70年東大教養学部を卒業してから、77年にマサチューセッツ工科大学政治学大学院博士課程を修了している。まさに文武両道ではないが、科学技術論と政治論との合体を目指している人物だと言える。
講演会に話を戻すと、私が最初に注目したのは提示されたデータである。それによると、日本が科学技術協定を結んでいる国は42カ国と多いが、途上国グループと結んでいる協定は16.7%と極めて少ない。米国の場合は48.6%、フランスは48.1%、ドイツは37.9%と、全協定の半分近くを占めている。
次に、日本は日頃からアジア諸国に対して“科学技術立国”と豪語していても、アジア諸国に対する科学技術協定の締結比率は11.9%で、米国の24.3%、ドイツの20.7%、フランスの14.8%に比べてみると、科学技術的な影響力、浸透力の小さいことが露呈されている。さらに、アフリカ諸国との締結比率をみると、日本の2.4%に対して米国13.5%、フランス11.1%、ドイツ3.4%と、これも桁違いである。
こうしたデータから何が見えてくるであろうか。日本は欧米に比べて決して劣らぬ科学技術レベルにありながら、いまだに明治以来の“舶来主義”から脱し切れていないように見える。よく知られている言葉に「キャッチアップ政策」(欧米に追い付く政策)がある。これは日本の明治以来の国家目標でもあった。そして、日本は経済大国として追い付いた。しかし、日本は追い付くだけでビジョン、政策を含めて欧米を追い越すことはできなかった。
他方、ODAの世界では1900年代末から2000年までの約10年間、欧米を抜いてトップドナー(世界一の援助国)に登りつめたものの、ただお金をバラ撒くだけで、日本としてのバラ撒く戦略もなく、世界の援助をリードする構想力もなく、淋しく一時代を終えてしまった。
薬師寺氏は著書の中で「日本はどうしたのか。これほど科学技術が強いのに、まだ先進国から何か得ようというのか。世界全体、とくにアジア・アフリカ諸国へ科学技術で貢献しようとする気持ちはないのか。こんなことでは、日本はグローバル・パワーになれるわけがないではないか」と訴えている。さらに、こう詰問している。「途上国は遅れているからトップノッチ(先端)の科学技術は必要ないというのは不遜な言い方である。このような考え方はいずれ途上国にもわかる。途上国にも優秀な研究者や学生がいる。米国で大学院生活を送った私はそう思っている」。
共同研究SATREPS
その上で、薬師寺氏は科学技術を新しい外交資源として活用すべきだと考え、こう主張する。(1)科学技術外交は相手国との相互受益を第一にすべきである、(2)科学技術と外交の相乗効果を発揮すべきである、(3)ODAと科学技術予算を結合して、アジア・アフリカ・中南米地域の科学技術基盤の高度化を助けるべきである。
つまり、環境問題、鳥インフルエンザ、SARSなどのケースを挙げるまでもなく、アジア・アフリカ諸国との科学技術面からの協力は、日本人の安心と安全にとって緊急の課題でもある。それは、環境や感染症など、私たちの生活に脅威を与えるものがグローバルに広がっており、アジア・アフリカの問題の解決が日本の問題解決に寄与することになるからだ。とにかく、問題解決の領域がグローバルになったために、新しい科学技術外交の強化が必要になっているのである。
薬師寺氏は、この持論を実行に移し、2008年に文科省所管の科学技術振興機構(JST)と外務省所管の国際協力機構(JICA)が共同して、略称SATREPS(サトレップス=地球規模課題対応の国際科学技術協力事業)を立ち上げ、今では途上国との共同研究(3~5年)は創設以来、33カ国において60の研究プロジェクトに達している。主な内訳はアジアが31、アフリカが18、その他が11である。
ところで、薬師寺氏は著書の中で、「ヘンリー・ダイアーの主張」を紹介しているが、ヘンリー・ダイアーが明治期に“お雇い外国人”として来日し、長期滞在した経験をもとに、母国の英国に向けて「発展途上の日本を学べ」と提唱したことに注視し、薬師寺氏は今の日本に対して、「途上国に学べ」と警鐘を鳴らしているのである。
ヘンリー・ダイアーは伊藤博文の要請で明治6年(1873)に来日したスコットランド人(グラスゴー)であった。伊藤はかつて英国へ密航した時にお世話になったジャーディン・マセソン社に自分の構想を伝え、それにふさわしい人材の紹介を依頼した。その構想とは、将来、日本が欧米の生産技術を導入したり、全国に鉄道を引いたり、艦船を造ったりする時の人材を教育する施設として工部大学校を創設したいが、その校長と教授陣を人選してほしい、というものであった。
そこで選ばれたのがスコットランドの名門グラスゴー大学の生徒ヘンリー・ダイアー(25歳)であった。彼は6年制のカリキュラムをつくった。その特徴は、今の医学部6年制のように、最終の2年間は工部省配下の企業での実習であった。彼は10年間日本に滞在した後、明治16年に日本を離れた。
帰国して「大日本」という本を書くが、エンジニアの地位の低い英国社会に向かって「英国は日本から学ぶことを恥じてはならない」と大胆に提言している。それによると、英国の国民生活の近代化は遅々として進んでいない。産業の発展は急速に消滅し、鉄鋼産業の原料生産は先細りし、製造業も時代遅れになっている。
それに比べ仏、独、日の教育は充実し、その成果を国家の事業に転換している。日本にいる時から英国の技術教育の改善を提言したが、相変わらず知識を詰め込む教育を行っていて、日本のような実習を入れたものになっていない、と嘆いている。
外交資産SEED-Net
日本ではたしかに明治以来、実習教育に力を入れてきた。それが工学系の教育に今も生きている。
たとえば、日本は40年以上にわたってタイの工学系の名門、モンクット王工科大学をODAで支援してきたが、実践を重視した教育指導が功を奏して、就職率の高い実践的大学へと発展し、タイ工業化の担い手を育ててきた。日本への留学でも、卒業後も1~2年間、日本の民間企業の研究所で学ばせている。つまり、実習を重んじた教育方針は明治のヘンリー・ダイアーという“お雇い外国人”の置き土産でもあるのだ。
最後に、私は科学技術外交という観点から重視しているODAプロジェクトのあることを紹介したい。
それは、今でもJICAが実施しているSEED-Netプロジェクト(ASEAN工学系高等教育ネットワーク)である。発足は1997年のアジア経済危機の時に構想されたもので、実際は2001年以来、今日も継続されている。狙いは大学教授陣の質の向上で、これにより質の高い卒業生を世に送り出すことである。
このプロジェクトで高学位(修士号、博士号)を取得した教授たちは約800にのぼり、今も教壇に立っている。そのネットワークはASEAN19大学、日本10大学に及んでおり、科学技術外交という日本の関心から見ると、その成果は実に大きい。共同研究数も700件に達している。
この構想の目指すところは、工学系の優秀な人材育成という点で、各国の大学レベルを日本の大学レベルに引き上げることだといわれているが、実は、日本の科学技術にとっての将来へのシード(種)がASEAN諸国大学との共同研究の中にわんさと存在していることに関心が集まっている。
先に述べたSATREPSの途上国との共同研究と同じく、環境問題、土木工学への貢献などの実用化への誘導など、ASEAN諸国の頭脳との共同研究で日本の得るものは大きい。こうしたことが日本の将来の「知力国家」(薬師寺氏提言)への礎になると思いたい。
※国際開発ジャーナル2011年11月号掲載