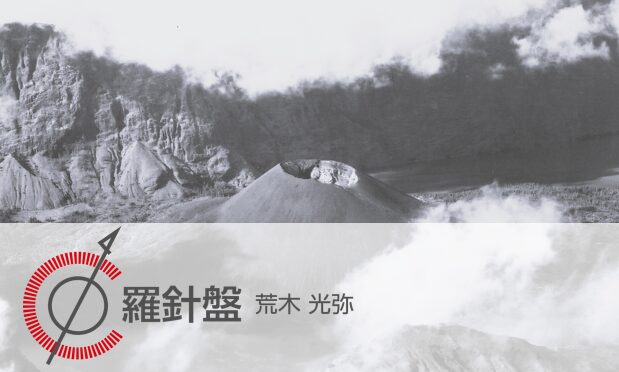太平楽からの脱出
今、私たちは日本人を太平の世から覚醒させ、残された日本人のエネルギーを海外に放出させようとしている。それは、まさに老成国家日本の歴史的な最後の戦いにも見える。
まず、政府はアジアなど更なる発展を遂げようとしている新興国に必要なインフラ(経済社会基礎部門)需要を取り込むために、首脳外交は言うまでもなく、民間活力を後押しする“官民連携”を政策的に強化しようとしている。一つの見方によれば、かつて日本経済を高度に押し上げた政府擁護の新たな“護送船団方式”と言えないこともない。どうも日本経済の実体は、“官民連携”どころか“官民一体化”でないと世界の諸勢力に対抗できないところにまで来ているのかもしれない。
政府は民間がリスクを懸念して海外進出を躊躇する時には、そのリスクをカバーすることも覚悟しているようだ。とにかく内向きで太平楽を決め込む日本人の活力を外向きに転換することが焦眉の急だと言えそうだ。
それは、経済再生だけの問題ではない。より根本的には次世代を担う若い世代が内向きで、沈みかかっている日本丸にしがみついていることが問題だ。政府が打ち出す“グローバル人材”の育成も、そうした危惧から生まれたものだと言える。
次いで、政府が着目している企業の外向き対策は、日本の各地に埋もれた中小企業レベルの優れた技術を発掘し、活用する道を開拓することである。戦後、日本製品、資本財などのブランド力を高めてきた精巧な部品生産技術力、その部品開発能力が今、見直されている。これまでは、自動車、エレクトロニクスなどを発展させた世界的な看板商法の下で見落とされてきた職人的で研磨された緻密な中小企業レベルの技術が注目されているのだ。
どうしたら日本の中小企業の技術を、日本に続いて次なる工業化を目指すアジアなどの途上国、さらには新興国に売り込むことができるかが重要な政策課題になっている。
その中で日本の政府開発援助(ODA)も途上国の工業化に貢献するというミッションの下で、日本各地で育った中小技術の海外展開を支援しようとしている。考えてみると、中小企業の技術力が途上国の工業化支援という開発課題に寄与することができれば、それは新しい援助モデルになり得る。
同時に、それは日本の中小技術力の海外進出という国益を後押しすることにもなる。こうしてWin-Win(互恵)の関係が日本と途上国との間で成り立つのである。一方通行的な援助は、そのうち援助するほうが疲れて長続きしないことが多い。それに比べて、Win-Win型援助は相互に恩恵を分かち合えるので長続きする。
裾野産業としての中小技術
昨年から始まったODAによる中小企業支援は、まず、日本各地に散在する中小技術の途上国市場(ニーズ)調査から始まり、その技術の市場化(普及)を支援する。それを手伝うのが、ODAベースで途上国の実態を把握し、多くの開発調査を手掛けてきたソフト系開発コンサルタントである。
彼らは技術の海外市場調査を手伝うだけでなく、中小企業の経営者に成り代わって政府への報告書作成も手伝う。途上国で技術の市場性が確認されると、場合によってはその地で生産、販売するという海外進出につながることも視野に入れている。
弊社では昨年から中小企業と開発コンサルタントとのマッチングを手伝っているが、応募してくる中小企業の技術の高さ、ユニークさを知るたびに、技術力を高める日本人の職人気質的な特性に感嘆することしきりである。ODAによって、そうした技術と汗と油まみれの技術開発魂が途上国に移植できれば、これ以上の技術協力はない。
例えば、ASEANでは加盟先発国のインドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイなど6カ国において、すでに域内関税がほぼゼロに引き下げられている。ただし、コメなどは国内事情が深くかかわっているので除外されている。残る後発の4カ国(ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー)も、2015年までに域内関税率をほぼゼロに引き下げる予定で事態が進行中だ。
ところが周知のように、日本ブランドの自動車、エレクトロニクス産業製品、時計製品などの輸出向け組み立て生産は、東南アジアに進出した日系企業の仕事である。東南アジアは日本経済の生命線と言われるほど、日本企業の海である。したがって、予定通りASEAN後発国の域内関税が撤廃されると、ASEAN全域での関税撤廃が完成する。そうなると、例えばベトナムに進出しているパナソニックとインドネシアに進出しているパナソニックの価格競争力が仲間内で問われることになりかねない。それはまた、域外への輸出競争力にもはね返ってくる。
では、各国での競争力を左右する問題は何かと言えば、それは輸出産業を支えるサポーティング・インダストリー(裾野産業)、つまり部品生産、それらに必要な素材産業などの発達状態である。それらが一定のレベルに達してないと、価格面での輸出競争力を落とすことになりかねないと言われる。
日系企業が多く押しかけているベトナムでは、昔も今も、輸出競争力を強める裾野産業群の育成が叫ばれてきた。歴代の日本のベトナム大使たちはベトナム政府にその重要性を進言してきた。しかし、実際はベトナム政府の理解不足が続き、かなりの歳月を空費している。2015年の域内関税撤廃が迫ってくる中で、ベトナム政府は今では日本の部品産業などをサポートする優秀な中小企業の誘致に積極的に乗り出している。
すでに、中小工業団地なども整備され、進出した大手企業の関連産業(下請け)などは、その後を追う形で進出完了している所も多い。しかし、部品の素材づくりが遅れていると、部品の品質のみならず、製品の価格体系にも大きな影響を与えるので、日本各地で健闘している素材づくりの中小企業の進出が望まれているところだ。
技術協力のブーメラン・パワー
もし、そうした中小企業のベトナムへの事業進出をODAで支援できれば、日本各地の優れた中小技術の保護、支援は言うまでもなく、ベトナムのみならず、広く途上国の開発ニーズ(課題)の解決を助けることにもなる。まさに、一石二鳥の援助効果と言える。
さらに、こうした日本の隠れた中小技術力は、時に世界の大きなマーケットを取り込むBOPビジネスへ発展する可能性も考えられる。ODAの中小企業支援は、日本各地に潜在する優秀な技術の再発見、再評価につながるビッグ・チャンスになるかもしれない。
それゆえに、ODAの実施機関・JICAは日本各地に散在している日本の優れた中小技術、あるいは伝統的技術・ノウハウを掘り起こして、実際の途上国への技術協力、技術移転に活用するアレンジメント、そのマネジメントに取り組むべきであろう。本来ならば、もっと早くに日本各地の技術・ノウハウを一つの技術協力の型に仕立てるべきであった。それは、日本の地域と途上国を結ぶ機会にもなったはずである。
そうしたことが実現できれば、日本各地の人々のODAへの関心も変わったはずである。それは一方でODAに対する国民理解、国民合意形成にとって非常に重要な意味を有している。
さらに付言すると、JICAは技術協力の一環として、文科省は言うまでもなく各地の大学とも連携して、中小企業の技術能力の発見、発掘、研究の活性化とその活用を手助けできれば、一つの「ODAの内外一体化」が陽の目を見ることになる。
日本の技術協力、技術移転は日本人や日本の企業、大学、研究機関などで開発された技術を援助の型にアレンジメントしなければならない。その調整能力(アレンジメント能力)が、今JICAに求められている。
途上国での日本の技術協力は、工業畑であれ農業畑であれ、いずれ日本の国益として戻ってくる“ブーメラン・パワー”を秘めている。そこにはスペックとして日本仕様の技術体系が組み込まれているからである。日本の技術協力で育てられた途上国人材は、必ず技術の源流に戻ってくると言う。そうしたODAによる技術協力効果を多くの人々にもっと理解してもらいたいものだ。
※国際開発ジャーナル2013年7月号掲載