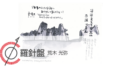原体験は難民救済と保護
JICA(国際協力機構)のトップがこの月をもって緒方貞子氏から東大副学長の田中明彦氏へ8年半ぶりに交代した。まずは、緒方貞子氏に心からご苦労さまでした、と申し上げたい。
キャリアからいうと、一見して国際公務員(UNHCR=国連難民高等弁務官)から学者へのバトンタッチのように見えるが、厳密にいうと、根っこのところでは緒方氏も田中氏と同様に学者(政治学)の領域に入る。
振り返ってみると緒方氏を、新しくスタートを切った独立行政法人のJICA理事長にお願いしようと、最初に動いたのはJICA職員グループだった。その背景には恒例化されていたトップ人事の天下りを阻止する狙いがあった。
ちょうどその頃、JICAを行政上監督しなければならない外務省では、職員の公金横領などの不祥事が起こり、社会的な批判を受けていた。外務省としても自前のJICAリーダーを用意できない状況下にあった。そうした中で、外務省も緒方氏を最適な人物だと考え、ニューヨークまで出向いて説得した。その意味で、リーダーを受け入れる側もリーダー人事を行う側も一体となって新理事長人事を行ったことになる。こうした人事は、極めて珍しいケースとして注目された。
緒方理事長は就任早々、JICA事業の背骨(バックボーン)となるべき「人間の安全保障」という考え方を打ち出した。人びとは、それまでODAの理念を「国家の安全保障」としてとらえてきたので、これには戸惑った。彼女が「人間の安全保障」を援助理念にした原体験は、難民の救済と保護を目的とするUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)での活動ではなかったかと思われる。
その援助の視点は、国家から見捨てられた個々人の自立を助けることにあるとみられるが、その考え方は1998年にノーベル経済学賞を受賞したインド人のアマルティア・セン教授の「人間の潜在能力アプローチ」という開発経済学に大いに刺激されていた。援助は貧しい人びとの本来持っている能力をどうしたら発芽させることができるかに立脚しなければならないとしている。つまり、開発の主体を国家ではなく、個々の人間に置いた考え方である。
援助の現場に立つと、理想とすべき最高の哲学である。援助の背骨となるべき思想である。現実にはこうした理念を掲げながら、途上国の国のあるべき姿、その政策などを考え、個々の援助プロジェクトのあり方にまで考えを深めるべきだと思う。
とにかくアフリカなどの若い民族国家は、自国民の潜在能力を開発する思想、また民族統合の規律を確立する余裕もなく、しっかりした国家の枠組みをつくることもできずに、自由になった政治権力を乱用して国民を幸せにする前に、一族郎党の利益確保に奔走し、最悪の場合は国家の利益配分を争奪する内戦を繰り返して、多くの難民を産み出すことになった。
その現実に日々直面してきた緒方氏は、JICAのリーダーになってみると、UNHCRでは実現できなかった難民の自立に向けての民生ノウハウ供与や職業訓練などの技術協力が視界に入ってきた。これからのJICA事業は途上国の国家から見放された貧しい人びとを救済し、自立させていくために、まずは人びとの能力開発が先決問題だと考えたに違いない。
ODAはチャリティーでない
ところが、緒方氏が「人間の安全保障」を単に一時的な難民支援だけでなく、援助する側のより根本的な理念として提示したにもかかわらず、理解不足の現場はついつい現場の人びとに目線を置きすぎてチャリティー感覚に陥る人も多くなった。無償資金協力では「人間の安全保障無償」という援助課題まで設け、「人間の安全保障」という理念が乱用された。こうして現場にはチャリティー的ムードが広がった。それに気がついたかどうか明らかではないが、緒方氏は途中でしきりに「ODAはチャリティーではない」と警告するようになった。
緒方氏の掲げた理念を、ODAの現場が正確に受け止めて、実施できなかったことは、外から見ていて歴然としていた。「人間の安全保障」という理念を援助行政に反映させるためには、その理念を念頭に置いて、ODA政策から実施政策までを見直して、制度設計する必要があったのではなかろうか。
筆者がJICAインフラ研究会の座長を務めたとき、インフラの定義について、緒方氏は「人びとのためのインフラ」を強調した。「人びとのためのインフラ」といわれてみると、何か忘れていたものに気付く感じがした。こうした気付きで、技術協力プロジェクトや円借款プロジェクトなどをチェックすることも「人間の安全保障」の実践に役立ったはずである。しかし、現実はそうではなかった。
一方、「人間の安全保障」論は「国家の安全保障」と対比される形で論じられるようになった。ところが、その論議は「援助される側」と「援助する側」にわかれてしばしば混線した。
つまり、「援助される側」に立った援助論では、「人間の安全保障」が当然ながら支持される。他方、資金を提供する「援助する側」に立てば、「人間の安全保障」の考え方は必ずしも支持されなかった。とくにわが国の政界、経済界は「国家の安全保障」を強調する。恐らく日本のマスコミ関係者も「ODAは外交の手段」という考え方を擦り込まれているので、ODAは「国家の安全保障」と深くリンクしていると思っているに違いない。
日本がニューヨークで国連の人間の安全保障委員会を立ち上げて、アマルティア・セン教授と緒方氏が共同議長を務めたときに行った記者会見でも、米国記者の間では「人間の安全保障は国家の安全保障の間違いではないのか」という会話が交わされたと伝えられている。
消化不良の人びと
援助という世界で「人間の安全保障」が正当性をもっていても、援助資金を提供する納税者側では一部の支持を得られても、多くの疑問を残した。多くの人びとは「人間の安全保障」という考え方に食あたりして消化不良に陥っていたといえないこともない。
「人間の安全保障」は日本人の安全、安心を保障する「国家の安全保障」につながるが、それが日本人以外の人びとまでをも広く包含する思想となれば、日本人には容認できない国民感情が働くのであろう。それは単一民族国家を長く続けてきた日本にとって大きな壁になっているのかもしれない。
とくに10年に及ぶ低成長の日本にあって、人びとの心のゆとりも失われつつあり、もし、ODAを支持するとすれば、「国家の安全保障」というコンテクスト(文脈)で支持する人たちが多くなろう。ODAに関係する人たちもこうした国民感情を考慮して、発言し行動しなければ、ODAの再興は難しいだろう。
美しく、理想に燃えた援助論だけでは国民の支持を得られず、結局は貧しい人びとを助ける援助資金も得られない、という状況に追い込まれることになる。
以上、緒方氏の足跡を追ってきたが、JICAの新理事長・田中明彦氏が緒方氏をどう継承するのか。ODA現場のスポークスマンとしての田中理事長の役割は大きい。言い方は厳しいが、それによってはODAの再興も不可能ではない。
田中氏は「外務省でも最近、“開かれた国益”という考え方を打ち出し、国益を明言するようになった。しかし、国益を無節操に乱用すると誤解を生む恐れがある」と本誌のインタビューで答えている。
筆者もその考え方には賛成だ。日本の国益を無理強いすると、相手の反発を呼んで逆に日本の国益を損することになる。有形、無形の国益追求は双方が納得する互恵(Win-Win)の関係を保つ必要がある。理想の援助とは日本人の経験、知恵、知識、技術、お金、熱意が生かされ、それが援助される側に政治的、経済的、社会的な恩恵とインパクトを与えることを指していよう。これからは、もう少し援助する側に立って、日本側のメリットを人びとに説いていく必要があろう。
※国際開発ジャーナル2012年5月号掲載