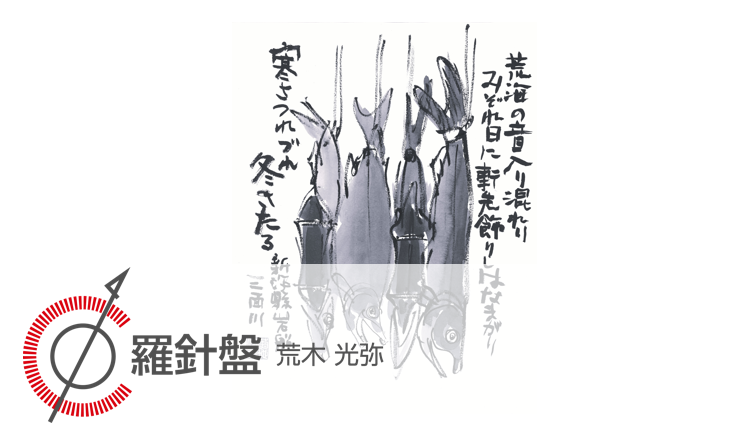債務帳消しの矛盾
ミャンマーへの政府開発援助(ODA)がいよいよ本格化してきた。
野田首相は4月21日のミャンマーのテイン・セイン大統領の訪日をとらえて、25年ぶりに円借款の再開を決めた。最大の問題である巨額債務の問題もこの機会に解決へのメドが見え始めている。
同22日付け「朝日新聞」によると、円借款の“延滞債権”として約5,000億円を計上し、うち約3,000億円を二段階で債権放棄する、としている。債務の計算は政府当局でないとよくわからない部分も多い。2003年の『海外経済協力基金史』によると、1970~87年までのミャンマー円借款案件一覧では、総計で約4,000億円が計上されている。
政府の“延滞債権”5,000億円には1998年3月の既往継続案件「ヤンゴン国際空港拡張事業」はじめ、約4,000億円に対する25年間のおそらく年金利2~3%も含めているものとみられる。
単純化してみると、4,000億円の元本債務に1,000億円(金利)を加算して5,000億円債権にしている。しかも、うち3,000億円を二段階にわけて債権放棄するという。よくわからない話だ。
そもそも途上国への債務帳消しは、1999年のケルン首脳会議で2000年からのミレニアム開発目標を掲げた国連開発計画に向けて決議された。日本の円借款を中心とする債務帳消しは約1兆円にも達したが、これは世界最大の帳消し金額であった。
こうした借金帳消しは、ヨーロッパの宗教行事の一環で始まった。つまり、皆さんご存知のモーゼの教えに従うと、50年ごとに貧しい人たちの借金は帳消しされ、奴隷たちは解放されなければならない。
一説によると、この宗教的、社会的運動はローマで組織され、全ヨーロッパを席捲し、米国まで巻き込んで世界現象にまで発展した。先進国の中で、独り仏教国の日本は孤立し、「借りたら返す」という日本独自の“自助努力思想”は通用しなかった。
この時、債務帳消しに際しての日本の原則として、「帳消しした国には新たな円借款(ニューマネー)は供与できない」を適用した。たとえば、ガーナは約800億円ほどの累積債務を抱えていた。日本はガーナを有望な国としていたので債務帳消しを求めず、一言「返済していく」と答えてもらいたかった。
そうすると、ガーナへの新規借款が続けられ、それなりに日本のインフルエンスを残すことができた。ところが、これは未確認情報だが、旧宗主国の英国が強力に対日債権放棄をアドバイスして、帳消しを決めた。当然ながら、英国は旧宗主国としてのインフルエンスをガーナに温存することができた。その後、日本はアフリカ開発基金などを通して、ジャパン・マネーを提供した。しかし、その時はジャパンの存在感は失われていた。
最大の問題は、債務帳消しすると新たな円借款を供与できないということだ。日本としてはミャンマーの新しい国造りに一石を投じ、日本の存在感を維持したいと考えている。大型インフラ整備には巨額の開発資金が必要だ。このニーズに応じられるのは低利、長期返済の円借款資金しかない。政府はこうした矛盾をどう解決するのだろうか。
一つ考えられるのは、かつて経験したインドネシア方式ともいうべき「リスケジュール」(債務返済繰り延べ)がある。ミャンマー側に一定の返済計画を立ててもらいながら、リスケジュールを継承して、新たな円借款を供与していく方法だ。そうしているうちに、経済が上向いてきたら、次は後を追うように返済を進めていくことができれば、新しい開発プロジェクトへの新しい円借款(ニューマネー)の提供がクリアされるかもしれない。
実は、1999年の時点でミャンマー債務帳消しも俎上にのぼった。
しかし、1988年にネ・ウィンのビルマ式社会主義を継承したソウ・マウン政権の混乱、それをクーデターで収拾しようとした軍事政権の登場、民主化への第一歩である総選挙を無視した軍事政権、そして民主化の旗印としてのアウン・サン・スー・チー女史の逮捕、自宅軟禁、欧米の厳しい制裁要求などの中で、ミャンマーの債務帳消しへの道は遠のいた。当時、たしか3,000億円が帳消し対象額だといわれていた。
ミャンマー支援の事始め
今回の債務帳消しで政府の一部には、ミャンマー民主化は予断を許されない、という欧米筋の情報に惑わされている人たちもいるようだ。だから、債務帳消しも段階を踏みながら、徐々に実施しようという判断が見え隠れしている。戦前、旧日本軍はインパール軍事作戦などで現地のビルマ人たちに多大の犠牲を強いた。2002年、筆者はマンダレーからの雲南省国境に近いシャン州北部のコーカン地区を取材した時、草むした旧日本軍人たちの墓標を目にした。ここまで日本軍は来ていた。
一方、日本はアウン・サン将軍を助けて植民地支配していた英国への独立戦争を応援するなど、ミャンマー人の独立国への悲願達成を助けている。
戦後、日本は多大の犠牲と迷惑をかけた東南アジア諸国への賠償を支払うことになったが、当時のビルマはその第1号になった。賠償協定は1954年(昭和29年)11月に調印され、1955年4月から65年4月までの10年間に総額720億円の財貨と役務を供与した。
その主な対象プロジェクトは、バルーチャン水力発電建設と工業化4プロジェクト(重車両、軽車両、農機具、家庭用電気器具の製造など)であった。工業化4プロジェクトは当初から多くの問題を抱えていたが、その後、1963年に結ばれた経済技術協力協定(1965年から10年間)で総額504億円の財貨、役務が無償供与されて、延命していた。
それでもビルマ政府は工業化4プロジェクトにこだわった。これに手持ち外貨もすべて投入するという意気込みだった。ところが、そのうち外貨不足に陥り、急きょ日本に無償支援の繰上げを求めてきた。
これに対し日本は無償でなく有償の円借款協力で対処することを決めた。1969年2月に総額108億円の借款協定がビルマ産業開発公社(工業化4プロジェクトの実施機関)との間で結ばれた。これが、ミャンマーへの円借款協力の始まりである。
先に述べた海外経済協力基金史のミャンマー円借款案件一覧によると、1970年の工業化4プロジェクト建設事業への36億円(タイド)から始まり、1987年のバルーチャン第2発電所改修事業への35億3,000万円(部分アンタイド)までの総額4,029億7,200万円を計上している。
タイドによる利益還元
注目すべきことは、全66案件のうち、タイド10件、部分アンタイド(LDCアンタイドでタイド効果が非常に高い)34件を合計すると44件にも達し、そのタイド型案件は全体の66%にも及んでいる。非常に高いタイド比率を占めていることになる。代表的な案件は工業化4プロジェクト事業とその関連部品を日本から調達する商業借款、石油開発関連、発電事業、輸送近代化事業、国際空港整備、パルプ事業、灌漑事業などである。
これらを総括すると、どう見ても日本のタイド効果、つまり日本側の経済効果の高いことが明白になってくる。つまり、経済協力の還元効果がいかに高かったかを物語っている。
政府としては、行政的に債務はあくまでも債務であって、債務を帳消しするとなれば、国民から預かっている資金(財投資金)に穴があくわけだから、それを一般会計で埋める形で債務帳消しをしなければならない。だから、結果的には国民の税金をこれに当てることになる。ただ、タイド効果として日本経済へのインパクトは大きい。そのタイド収益分はすでに日本企業群から税金として国庫に収めてもらっている。
そう考えてくると、4,000億円の大部分は日本企業を通じて日本へ還元されている、と見ても過言ではない。現在、日本の台所が苦しいことは十分承知の上で強調したいことだが、1999年の債務帳消しの国際的な決定に立ち戻って、ASEAN最貧国ミャンマーを救済し、新しい民主国家を建国するために、全額の債務帳消しと新たな円借款供与を政府に求めたい。
※国際開発ジャーナル2012年6月号掲載