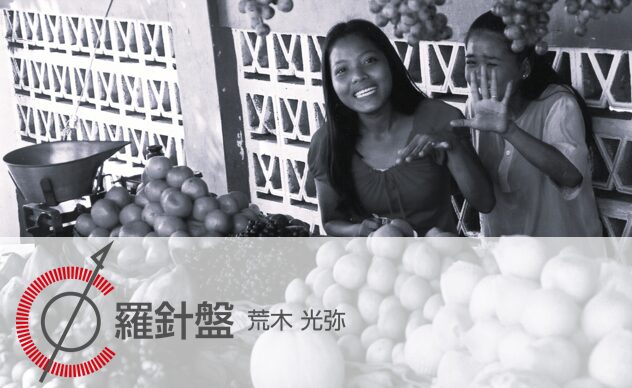政府開発援助と国益
政府開発援助(ODA)に対する世間の関心度は、この不況下でますます低下傾向にある。
岡田外相の意向をくんだ外務省のODA改革報告書「開かれた国益の増進」はこの際、これまで人びとに悪い印象を与えてきたODAという言葉を反故にして、「開発協力」という新しい言葉に統一したい意向のようだ。
その気持ちはよくわかる。今のODA予算が1980年代半ばぐらいのレベルにまで激減していては、ワラをもつかむ思いで開発協力の再生を図りたいのだろう。しかし、その程度では根本的な解決にはほど遠いとみたい。
外交当局を含む日本政府は、とくに90年代以降、果たしてODAを日本外交の唯一ともいえる手段として戦略的に活用してきただろうか。人によっては、国際社会の「応分の資金拠出を」という要請に応じてきたこと自体が立派な日本外交の成果だというかもしれない。だが、それはただ要請主義にもとづく単なる受身的な政府開発援助であって、そこには日本国としての能動的で戦略的な外交展開が見えてこない。
主要な先進国を見ると、軍事的な政策手段をも活用して諸外国との関係を維持し、かつ深化を図っている。その意味で、主要先進国にとってODAは複数ある対外政策の一つにすぎない。主要先進国はODA以外にも安全保障や貿易・投資など様々な政策手段を駆使し、またODAを他の政策手段と連携させながら一国の総合的な国益を追求している。
その場合は「国益重視」だけでなく「国際協調」も同時並行的にバランスさせている。それは、時にダブル・スタンダード(二重基準)、場合によってはトリプル・スタンダード(三重基準)に映ることもある。古い話かもしれないが、明治維新の殖産振興に大きな功績を残した大久保利通が欧米列強を視察し、帰国したとき、「欧米列強は“礼儀正しく”国益を追求している」と語った。礼儀正しくとは、つまり国際協調という大義名分の旗の下で、時に普遍的な理念を掲げながら、その国益を理念というオブラートでしっかりと包み込みながら探求している、と言いたかったのであろう。そこでは当然ながらダブル・スタンダードがまかり通っているのである。
欧米の援助戦略
現在、主要先進国は納税者へのアカウンタビリティ(説明責任)をどう考えているかといえば、国際協調としてのミレニアム開発目標の達成をといいながら「ODAの正当性は、自国の政策意図に沿った援助効果が援助される途上国において達成されることにある」と説明しているようである。彼らは伝統的ともいえる外交政策が援助政策、またはその推進過程において確保されるように工夫する。たとえば、フランスは海外領土をも含むフランス語圏への協力を第1の優先順位にしている。英国は表向きDfID(英国国際開発省)がミレニアム開発目標の達成を強調しながら、英国の歴史的なコモンウェルス(英連邦諸国)を支援する英連邦開発公社では、優秀な人材のスカウトと育成(とくに政治家、行政官志望者)、連邦下の途上国輸出産品の開発・輸入のための投資など、国益まる出しの政策を遂行している。ドイツは伝統的で比較優位にある幅広い機械技術(最近は環境技術)の途上国への浸透を援助政策の柱にしている。
一方、米国援助の大義名分は民主主義と人権の国際的普及であるが、これは冷戦時代からの一貫した米国の基本政策である。しかし、外交手段としての対外援助は、「米国への脅威の排除」を基本にしている。この考え方は民主党クリントン政権下でも共和党ブッシュ政権下でも変わらなかった。もちろん現在のオバマ政権下でもそのベースは同じだ。だから、今もイラクに続きアフガニスタンでもその考えの下で闘っている。表向きは民主化、人権支援でもその背景にはテロという自国への脅威の排除を目指している。アフリカ援助はそのためにある。
米国の対外援助戦略を要約すると、まず世界戦略を含む「貧困削減」に向けては、(1)民主化の促進、(2)経済成長、(3)制度改革、(4)人道救済、(5)脆弱国家の強化などが挙げられる。しかし、直接的な「国益追求」に向けては、(1)米国の地政学にもとづく戦略的利益擁護、(2)麻薬、エイズ、テロの脅威への対処、(3)貿易・投資のグローバル化などが挙げられる。
米国の地政学にもとづく戦略とは、やはりカリブ、中南米地域の社会・経済の安定が第1の優先順位になる。たとえば、中南米からの麻薬の密輸入阻止、地域的なテロ対策、さらにLAFTA(ラテンアメリカ自由貿易連合)の維持などが戦略対象になる。中南米に対してはケネディ大統領以来の「進歩のための同盟」が脈々と生きている。このように、米国は国際協調という大義名分の下で、「国益追求」を堂々と掲げている。私たちはこれをダブル・スタンダードと言っても米国はダブルでないと言い、政策は1つだと言い切る。
新成長戦略とASEAN
私は米国の対外援助のもう一つの顔、国益追求の第1の優先順位である「地政学にもとづく戦略的な利益擁護」が、今の日本のODA政策に必要なアジア政策ではないかと思う。民主党政権は、日本経済の建て直しに向けて、「経済のアジアとの一体化」を掲げた新成長戦略を展開しようと、必死に大型インフラ事業を受注すべく大臣自らアジアを飛び回っている。民主党議員との議論でも「新成長戦略にODAもベクトルを合わせられないか」と打診する。外務省も「開かれた国益の増進」を打ち出している。
最近、外務省はASEAN(東南アジア諸国連合)の本拠地であるインドネシアの首都ジャカルタに常設のASEAN大使を置いた。これまでASEAN大使は本省に待機し、ASEAN会合の時にだけ出席していた。自民党政権時代からASEAN+3(日中韓)、あるいはインドなども入れたASEAN+6が大いに議論されてきたが、残念ながら日・中・韓との協調が突出する形で議論されても、日本のアジア戦略の要になるASEANと日本との関係強化についてはあまり検討されてこなかった。とくにODAに関しては、ASEAN10カ国のうち経済成長が遅れ、ASEAN原加盟国のインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5カ国との経済格差、所得格差が大きく開いたベトナム、カンボジア、ラオスなどインドシナ諸国については、インドシナ域内物流などを盛んにして発展の基盤をつくるためにインドシナ半島の東西を横断する「東西回廊」づくりにアジア開銀と協力しながら積極的に対応している。
しかし、先に述べた原加盟国、とくにシンガポール、マレーシア、ブルネイ、これにタイも加わる形でDAC原則かどうか定かでないが、“ODA卒業国論”が当てはめられてODAが後退した。そもそもODAには、DACの援助論と同時に、日本の外交手段としての役割が存在しているはずである。日本のODAは90年代のトップ・ドナーになってから変に国際貢献熱に浮かされてグローバル化し、援助のバラ撒きが始まった。しかし、今の日本は厖大な借金国になった。それにもかかわらず、ODAはアフリカの貧困削減、アフガンの平和構築支援に偏りすぎていて、日本にとって地政学的に最も重要なASEAN、インド、中国などを含むアジア地域が手薄になっている。
ASEANは60年代の冷戦下の設立時から、70年代の福田ドクトリン外交による地域協力の歴史を振り返ってみても、インド、中国の谷間にあって極めて重要なバッファーゾーンである。先年、私はタイ、マレーシア、シンガポールの長い歴史を有する日本のODAプロジェクトを調べたが、いまだに日本の知見や人脈は立派に生きていた。
私は新しい形のASEAN協力として、「ネットワーク型協力」を重視し、科学技術の分野、社会政策の分野などでの共同研究をASEANネットワーク型で推進することを提言している。
※国際開発ジャーナル2010年10月号掲載