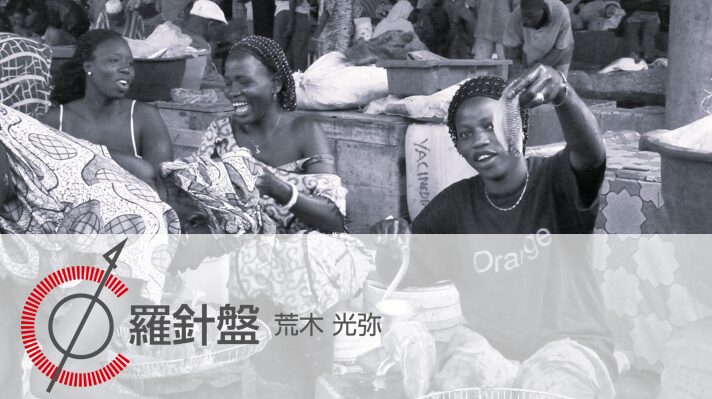アフリカとアジアを比べたら
初めてのアフリカは遠く広かった。西アフリカのセネガルの首都ダカールには東京―パリ経由で入る。次いで、ケニアの首都ナイロビにはダカールからニジェール経由で入る。その所要時間は9時間30分である。アフリカ大陸でも北部の一番幅広い所を飛ぶので、そのくらいの時間が必要だとしても、その距離感覚は成田発ハワイ通過、成田発ニュージーランドで余りあるものになってしまう。改めて、アフリカの広大さを実感したしだいである。
そのアフリカ大陸は54カ国もの国が国連加盟している。いかに多くの国々がアフリカ大陸にひしめいているかが感じられる。しかし、アジアに比べたら、その人口密度は小さく、それが国全体の開発を難しくしている点でもある。
その意味でも、アジアと同じ視点でアフリカの開発を考えることはできないだろう。そうした地理的条件の上に、アフリカの歴史は同じ植民地支配のアジアとは、その時間と本質において大いに異なっているように感じる。それは奴隷貿易だけでなく、ヨーロッパのアフリカ文明の破壊の仕方も、アジアに比べてより残酷で、アフリカ民族の根底を破壊し尽くしたと言っても過言ではない。
セネガルでは、「日本の発展を学ぶとともに、アジアの経済発展の経験を学びたい」と言われた。2月15日から3日間、ハノイで「都市開発にかかわるアジア・アフリカ経験共有セミナー」が国際協力機構(JICA)セネガル事務所の肝いりで開かれた。これは昨年11月のダカール国際セミナーに続くものである。参加国はセネガル、マリ、コートジボアール、ガーナなどで16人がハノイを訪ねた。
西アフリカの参加国は、名目GNI比で1,000ドル内外と、ベトナムと似たり寄ったりである。参加者はハノイ市内を視察して、ゴミの少ない街路、夜遅くまで働くベトナム人に驚いていたという。ベトナム側は、都市開発に関する夥しい数の「政府決定」を施行しつつ人口密集地での大規模インフラ整備を進めていったことを紹介する。すると、アフリカ側で溜息がもれてくる。アフリカではベトナムの「政府決定」と同じ効力をもつ「大統領令」が数多く発出されても、政府事務方(テクノクラート)の実施能力や開発ディスプリンが低く、実行が伴わず、大統領の「宣言」のような形でうやむやに終わってしまうケースが多いという。
難しいモノ造りの移転
アジアではベトナム、中国といった社会主義国だけでなく、インドネシア、タイ、マレーシアも、たとえ開発独裁という政治体制がとられていても治安は軍が、経済発展は海外留学のスジ金入りのテクノクラートが担当し、一国の経済、社会開発に励み、なんとか経済的にはテイクオフを遂げている。
一族が国を支配し、国家の権益を自由にしていたマルコス大統領のフィリピンも、またスハルト大統領のインドネシアも、長く混乱が続いたものの、徐々に本格的な民主化の道を歩んでいる。それは、ひとえにしっかりしたテクノクラート集団の育成、経済発展を支える民間のビジネスマン、実業家たちが健在だったからだと言われている。
しかし、実業の分野を育てた背景には、もともと東南アジアに根付いていた華商グループ、それに日本経済の発展をリードしてきた日本財界のアジアへの海外投資グループの存在があった。
自画自賛するわけではないが、ファー・イースト(極東)の一角に日本という経済発展、技術発展する貿易立国があって、その国づくりをモデルに隣の韓国や台湾が立ち上がり、続いて東南アジア諸国が日本からの輸入代替産業の投資でモノ造り産業を発展させる基盤をつくり、あわせて日本の経済協力で経済インフラ部門を整備し、海外への輸出力を強化していった。
なかでも最大の成功は中国で、日本の経済協力による港湾、鉄道などインフラ整備、日本からの投資や技術などをフル活用して、日本を抜いて世界第2の経済大国へのし上がった。それが今ではインドへ生産拠点を移す日系企業も現れ、アジアはまさに世界のモノ造り基地へと大きく変貌している。
そこで、南アを除くアフリカ諸国とアジア諸国を比較すると、アフリカがアジアのようにモノ造りの生産基地になれるとは思えない。まず、地理的に有利であるにもかかわらず、ヨーロッパがアフリカにモノ造りの拠点を移すとは思えないからである。ヨーロッパはあらゆる資源の収奪に専念しても、アフリカの地にモノ造り投資するとは考えられない。それでは、今の日本が生産基地をアジアからアフリカへ移転させるかといえば、資源関連、農業関連などの一部の動きは別にして、大きな流れにはならないだろう。
その大きな原因はアジアに比べて労働賃金が高いからである。つまり、労働集約的な産業を育てられない環境がそこにある。なぜ賃金が高いかといえば、エンゲル係数と言うべき食料費が異常に高い。
たとえば、セネガルではタイ米の輸入比率が70%にも達し、その分の貴重な外貨をはき出している。それどころか、セネガル農民が自立する道を閉ざしている。先進国はグローバリゼーションを謳歌する一方で、弱いアフリカの自立農業を破壊している。そうしながら一方で、貧困救済の援助をアフリカへ、と叫ぶ。なんのことはない。先発の先進農業大国がアフリカ農村の貧困を固定化しているのである。
だから、セネガルでは日本に農業開発援助を要請してくる。また、ケニアではセネガルほどではないが、40%以上を輸入米に依存している。だから今、コメの3倍増を目指し、日本が20年以上支援してきたジョモケニヤッタ農工大学などが側面支援している。
新しいアフリカの空間
以上が、今回の私のアフリカ実感である。これまで「アジアの経験をアフリカへ」という考え方に同調してきたが、それはアフリカを見ずに発想した単純なアイデアかもしれない。西アフリカのセネガル、東アフリカのケニアを一見しただけであるが、一つのインスピレーションとして、「アフリカにはアフリカの道がある」のではないかと思うようになった。TICAD(アフリカ開発会議)のサブタイトルとして「アジアの経験をアフリカに」という唱えも、たとえアフリカがアジアの経験を学ぶとしても、それは部分的な参考例であって、そのままアフリカに当てはめるには相当な無理を感じる。
それよりも、アフリカの発展への新しい道を、アフリカ人を中心に据えて探求し、それを私たちが側面から助けるという構図が描ければ、望ましい援助の理想型となろう。ケースによっては鉱業であれ、農漁業であれ、天然資源の世界への供給基地になる国も出てこよう。IT革命の導入で、一足飛びに知的産業を開花させる国もあろう。地球環境を考えた野生の動植物の保護とその遺伝子研究、医学的研究で世界をリードする国も現れるかもしれない。そう考えると、私たちはより複眼的にアフリカを見ていく必要があろう。
セネガルの知識人にこう言われた。「新しいアフリカの空間が生まれつつある」。その知識人も、それが何であるかを的確に言い当てることはできなかった。私にはこれまでの国家の発展と違う変化がアフリカに生まれるのではないか、という予感が働いた。
たとえば、アフリカ人の背中を押し始めたのは南アだけでなく、中国、インド、ブラジルなどの新興国の出現かもしれない。ヨーロッパに長い間、支配されてきたアフリカにアジア・アフリカ連帯を唱える中国が実力をつけて乗り込んで、ヨーロッパの既得権益を壊し始めたことに“新しいアフリカの空間”を感じているように思えた。
最後に一言。ホテルのエレベーターでアフリカ人に「中国人か日本人か」とたずねられ、「日本人だ」と言うと、握手を求められた。セネガルでは「ヨーロッパ人は教えるとすぐ帰る。しかし、日本人は教える先生を育てて帰る。日本人はアフリカの自立を大切にしている」と語ってくれた。こうした評価は、わが先人たちの真摯な協力の成果だと思う。先人たちに感謝してやまないアフリカの旅だった。
※国際開発ジャーナル2012年7月号掲載