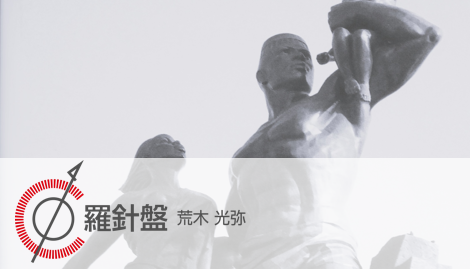戦略的「箱物」援助
セネガルの首都ダカールの中心部で、周辺の環境から浮き上がったような新築の豪華な大劇場が目に飛び込む。ガイドは「中国からセネガルへのプレゼントです」と言う。そして、「2年前ですか、柿落としで京劇が披露されて以来、これといった催しもないですね」と付け加えた。
アフリカでの中国の「箱物」援助攻勢は有名な話になっている。ただし、それは単なる援助(贈与)ではない。その裏にはごく当たり前の話かもしれないが、必ず国家政策が張り付いている。中国はセネガルへの援助攻勢と引き換えに、2年前だったか、セネガルからの「台湾追放」を勝ち取り、中国の基本的な国家政策としての「一つの中国」を実現し、それに乗じてセネガルでの経済的利権取得に狙いを付けているという。
例えば、地下資源では銅鉱山などがある。大西洋に面したセネガルの海岸線は長く、水産資源はアンチョビなど実に豊富だ。中国がこれに目を付けないはずがない。いずれ海洋へも進出してくることだろう。その前に、ひょっとしたら巨大な魚類の缶詰工場を建てるかもしれない。日本は漁民の商いを助けるべくダカール近郊にスケールの大きい中央卸売魚市場を無償援助し、水産日本の面目を保っている。その意味で、日本はセネガルの水産業への最初の貢献者かもしれない。願わくば、日本から水産加工業の企業進出を期待したい。それこそ官民連携事業として有望な事業になると思う。
セネガルの第2の都市ティエスへはダカールから1時間半ぐらいかかる。日本はそこのティエス国立病院で驚くなかれ日本発の生産性向上「改善運動5S」を実施し、好評を博していた。病院内は整理整頓されてゴミ一つ落ちていない。セネガル側に言わせると、「5S」はカネがかからないから、いつでもすぐに実行できると言う。たしかにそうだ。
本当の「5S」は運動と言われるように下から上(ボトムアップ)の参加意識向上であって、それにより企業では製品の品質向上、国家レベルでは国造りの指導原理になる。シンガポールの国家形成期に、リー・クアン・ユー首相は日本から「5S」の労働価値観を学び、政府の中に国家生産性庁を立ち上げたことがあった。セネガル政府もそういう意味で日本の「5S」は参考になろう。
それではもう一度、話を中国の進出に戻してみよう。第2の都市ティエスからの帰路で、再び中国の存在を見た。ダカールに近い道路沿線上からかなりの規模の、ただし、まだ開業していない小児科病院が見える。ガイドの説明によると、中国は建物だけは建てる。ただし、中身の医療機器類については自己調達し、自ら医師を張り付ける、という約束で建築したと言うのである。かなりの時を経た今日でも開業の気配はないようだ。今のセネガルの財力では、医療機器の自己調達など無理な話であろう。しかも、医師の育成となると時間がかかる。
定着型の野菜栽培
とにかく、中国の援助は建屋など「箱物」づくりが目立つ。中国は政治的なデモンストレーションを狙って意図的に「箱物」づくりを推進しているのか、それとも当面、「箱物」づくりが得意だからせっせと「箱物」をアフリカに建てまくっているのか、よくわからない。しかし想い出すと、この話は中国だけの話ではない。その先輩は日本である。日本のODA全盛時代にはマスコミから、日本のODAは「箱物」援助だと、悪いイメージのレッテルを貼られ、いかにも中身の伴わない援助のように非難されたことがあった。それは80年代の倍増するODA予算に援助実施体制が人員不足のためについていけなくなり、手っ取り早い処理方法として物品援助や「箱物」援助が選ばれた。大胆に言ってしまえば、日本は残念ながらただそれだけの理由で、せっせと「箱物」に精を出した。もっとも無償援助は基本的にタイドだから、日本のビジネス界を潤したことは間違いない。日本に比べて、中国の「箱物」にはぴったりと「国家の政策目的」が張り付いている。言うならば「戦略的」なのである。中国は政治目的のために、一つの手段として「箱物」援助を重視しているだけである。だから、援助への考え方が日本とは根本的に違う。そう考えると、中国の「箱物」援助は意図的であり、深謀遠慮だと言える。
話を戻すと、先の空っぽの小児科病院のずっと手前でも、もう一つの中国の影を見た。首都ダカールから北上するほど大地は乾燥していく。それが良くわかるのは、水分を体内に貯め込んで膨らんでいるバオバブの木が目立つようになるからだ。そうした厳しい環境の中で、中国語の企業名の看板が道路沿いに立っている。その先をよく見ると、不毛のように見える大地の中でかなりの規模のチンゲン菜などの「野菜園」が広がっている。おそらく地下水を利用していると思う。スプリンクラーが見える。
いくら中国と言えども腐り易い野菜類を中国へ持ち帰るはずがない。ガイドの説明で納得した。中国野菜を大量に必要とする中華料理屋、次いで韓国料理屋が多いから野菜園が成り立っているのであろう。アフリカに中国人が多ければ中華料理屋も繁盛しているのかもしれない。
周知のように、中国がアフリカで多くの労働者を引き連れての道路や鉄道工事、あるいは建造物を手掛ける場合、彼らは必ず共同生活し、食事は中華料理というのが定番である。プロジェクトが終わると、横すべりに他のプロジェクトに移ることもあるが、中にはカネを貯めて手っ取り早く得意の中華食堂を開店する人も多いようだ。一人が成功すると次々と後継者が出てくる。
しかし、そのうち中華料理屋が地元の料理屋を経営圧迫するようになると、反中国の火の手が上がるかもしれない。
狙われる日本のアセット
今度はケニアの首都ナイロビでの中国の影を追ってみよう。
ナイロビから郊外に30分も走ると、すぐ田舎という感じだ。片側4車線の新しいハイウエーを40~50分も走った所に日本が20年以上かけて援助し、今もかかわりを続けているジョモ・ケニヤッタ農工大学がある。今ではケニアを代表する大学に成長している。20年は血のにじむような努力の毎日だった、と関係者は語る。
中国がこの優良大学に着目しないはずがない。さっそく大学構内にボタニカル・ガーデン(植物園)を開設して薬草を研究し、その一方で構内に孔子学院を開校して中国語の教育を始める。
また、中国はAU(アフリカ連合)が打ち出したAPU(パンアフリカン・ユニバーシティー)構想の下で、アフリカの東ブロックで最有力視されているジョモ・ケニヤッタ農工大学に狙いをつけて新たな講義棟や寄宿舎(ドミトリー)の建設を内秘に打診しているようだ。日本は最近になって同大学で再生可能エネルギーの研究を進めているが、ジョモ・ケニヤッタ農工大学を東アフリカにおける大学・研究協力拠点として継続していく意志が希薄になると、中国にとって代わられる恐れがないとは言えない。
次は中国の道路建設の話である。
この工事はナイロビから北へ向かうハイウエー建設であるが、その資金の出所はアフリカ開銀である。中国は堂々と国際入札で落札している。とにかく中国はアフリカ各地で安値攻勢をかけて多くの道路案件をものにしながら、着々と技術力を高め、蓄財してアフリカに広く深く根を張り始めている。
アフリカ開銀であれ、日本の円借款であれ、国際入札に付されると、日本は中国の安値攻勢で敗北する。しかし、考えてみると、アフリカ開銀の大株主は日米欧である。今の状況はDAC非加盟国の中国のアフリカ進出を日米欧がせっせと応援しているようなものだ。おめでたい話である。
前号で「アフリカの新しい空間を中国が作っている。それはアフリカにおけるヨーロッパの既得権益の破壊を意味しているからだ」と述べた。アフリカの甘い汁を吸ってきた既得権益者には大きな打撃だ。しかし、日本はアフリカとのかかわり合いにおいてヨーロッパと違う。日本は日本らしいアフリカ援助戦略を来年のTICAD(アフリカ開発会議)へ向けて打ち立てる必要がある。
※国際開発ジャーナル2012年8月号掲載