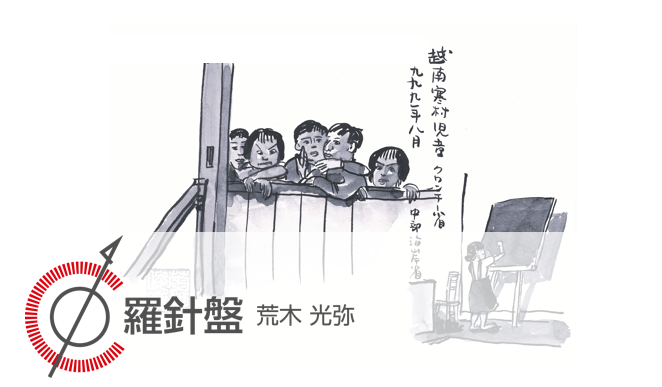現政府のODA問題意識
海外コンサルティング企業協会から初めて事情聴取した参議院のODA特別委員会は7月27日、「政府開発援助の持続的な推進を求める決議」を公表した。そのポイントは3点に絞られているが、これが現政府のODAに関する問題意識であるという点で注視すべきであろう。
(1)第4回アフリカ開発会議(TICAD)で表明した対アフリカ支援(ODA)倍増という国際約束を守ること。
(2)青年海外協力隊の事業成果を更に高めるとともに、隊員のキャリア形成支援や経験・能力の活用を図るために官民による就職支援の拡充、帰国後の起業や現職復帰につながる派遣先・分野の選定などを具体的に実施すること。
(3)わが国の成長戦略でODAを活用するために、まずはODA腐敗防止、つまりコンプライアンスの強化、開発コンサルタントを初めとするODA関連事業者の業務環境の整備・改善に配慮して、次の事柄を速やかに充実させることとしている。①官民連携の推進、②東南アジアの経済社会基盤の整備や技術協力の実情に合った推進、③研修員受入れ、民間連携において地方や中小企業を含む国内各地域の事業基盤や技術の活用を図ること、④ODA案件実施の迅速化(特に円借款のスピード化か)、⑤ODA事業の質の確保に資する事業者選定方法の採用(安かろう悪かろうにならない入札方法の改善を指していよう)、⑥ODA事業の実施に際して相手国の免税措置の確保、⑦ODA関係者の安全確保など。
私は、以上のうち3つの指摘を重視している。
「日本の価値」を広げる
第1点は、青年海外協力隊員の「帰国後の起業や現職復帰につながる派遣先・分野の選定」である。最近、青年の外向き傾向が減っているという。これは私の考えだが、それはイマジネーション(想像力)の欠如によるところが影響しているからではないだろうか。たとえば、どの大学でも海外留学先まで確保し、留学資金(奨学金など)をも用意していても、青年たちの海外留学の意欲は湧かない。青年に聞くと、「留学しても日本での就職先がない」の一言で終わる。就職先についても漠然としている。私に言わせると、「人生設計ができていない」ということになるが、もっと言えば人生設計をするための想像力が不足しているとも言える。
だから、ODAで青年を育てるために青年海外協力隊があると言っても、青年たちに人生への想像力がない限り、キャリア・パスと言っても悪く言えば、ただの途上国の旅になってしまう。このところ協力隊への応募が減少しつつあるのは、単に少子化現象のみならず、青年たちの海外へのイマジネーションが減退しているからではなかろうか。
そういう仮説に立つと、初めから一つの目的をもって、己の知見と技術を磨き、日本の価値を伝授できるような青年に派遣の夢を託したほうが実践的ではないかと思う。その意味で、帰国してから、あるいは現地でBOPビジネスではないが起業したいという、ある意味で野望を抱く青年に的を絞ってもよいのではなかろうか。その点で派遣する前から派遣先や分野を選定することも重要であろう。
すでに、現職復帰できる企業の現職参加制度は存在しているが、出来れば当該企業の市場戦略に沿った派遣国の指定、出来れば当該企業によって受入れ先のフォーメーションなども検討してもらえれば完璧であろう。
私は、青年の育成という漠然としたコンセプトではなく、“日本の価値”を途上国に伝播する派遣コンセプトに改めるべきだと考えている。途上国に対しては“新しい社会づくりへの協力”、つまり社会近代化を助ける青年の協力という位置づけで、協力隊の枠組みをいくつか設けてみてはどうだろうか。
たとえば、産業発展対応、環境問題対応、伝統工芸対応(ものづくり)、音楽・スポーツ・アニメ対応、教育対応(高校の先生の派遣枠はある)、地方自治体対応(自治体派遣枠はある)、保健・医療対応(伝統医療行為も含む)、研究開発対応(大学、企業のR/D、共同研究も含む)などが考えられる。
この場合、従来からの「要請」ベースだけでなく、派遣元(自治体、企業などをも含む)による相手先への「提案」ベースも併用すべきであろう。新しい改革に挑戦しないと、青年海外協力隊制度は予算消化型のマンネリズムに陥ってしまう。
「日本の技術的価値」の伝授
第2点は、研修事業や民間連携に際しての「地方・中小企業を含む国内各地域の事業基盤・技術の活用」である。東日本大震災で福島における自動車部品のサプライチェーン崩壊が話題になったように、日本の地方には隠れた形で優れた技術が存在している。日本の世界的なブランド商品は、ネジ1本といい優れた部品技術によって品質保証されている。日本の中小企業の技術はまさにナショナル・ブランドでもある。工業化を急ぐ途上国には垂涎の的であるから、ひと工夫すれば立派なODA技術協力になれるはずだ。
ところが、ODAの実施機関であるJICAは外のニーズに気を取られて、日本の内側のニーズに目を向けようとして来なかった。援助プロジェクトを仕立てる時、埋もれた地方の技術をくみ上げて、日本の価値を高める努力を欠いてきた、と言ってもよいだろう。
アンタイドの円借款協力は鼻から日本の技術のスペックインはできない。欧米は基本的に、ODAは原則無償であるから、どんどんスペックインしてくる。円借款でもSTEPという本邦技術の活用による援助方式を活用すれば、それなりにスペックインは可能だが、JICA側に実業界をコーディネートする力量がない。昔は総合商社がその任に当たっていたが、今では商社のODA仕掛人は死滅している。残すは開発コンサルタントにその役を担ってもらうしか方法がない、といっても過言ではない。
こういう問題意識で、地方・中小企業技術の活用を進めない限り、絵に描いたモチではないが机上の空論になってしまう。
「官民連携」と入札改革
第3点は、「ODA事業の質の確保に資する事業者選定方法の採用」である。JICAの調達を見ていると、入札が不調になることが多い。再入札を繰り返すごとに行政コスト(これも税金)も膨れ上がる。税金のムダ遣いを排除するための公正な入札絶対主義が、逆に税金をムダ遣いしているという批判も出ている。
こうした弊害を除去するためには、政府の事業主側が“効果的な援助”を目指して、これは価格競争で、これは内容の品質競争で、というように、ある程度差別化した入札制度を設計する必要があるだろう。そうでないと関係者の専門性を高める努力に水を差すことになる。まさに、戦後の日本製品に対する海外の評価「安かろう悪かろう」になってしまう。日本の知恵、知識、技術を劣化させてはならない。今回の参議院による決議は、以前の事業仕分けの行き過ぎを是正してもよい、という政治的シグナルである。これにちゃんと応じなければ、今度はODA事業者側(JICA)の責任が問われることになろう。
これは私見だが、事業者選定などの入札制度改革が責任回避と言われるほど遅れている。ある薬品の一滴で汚れた水を浄化できる特許商品の入札を催しても、競争相手は出てこない。特許は一社に与えられるから当然である。ところが、今の入札制度だと、競争相手が出てこないと入札は不成立になるという。これは、公的な入札で一社入札の特別扱いはできないことを意味している。
これから世界へ向けて、特許をもつ一社の技術なり製品をODAで採用することはできないことになる。これを別の角度からみると、たとえばアフリカで雇用創出の大きい本邦一企業の進出の場合、これも一社支援ということでODAのバックアップは得られないことになるのであろうか。一社支援の場合、公開性、公平性を高める支援方法をその気になって考えれば整合性のある制度設計は可能になると考えたい。
ODAは最近、「官民連携」と言いながらも、それはあくまでも官主導の民間連携であって、民主導の「民官連携」ではないように感じられる。
※国際開発ジャーナル2011年9月号掲載