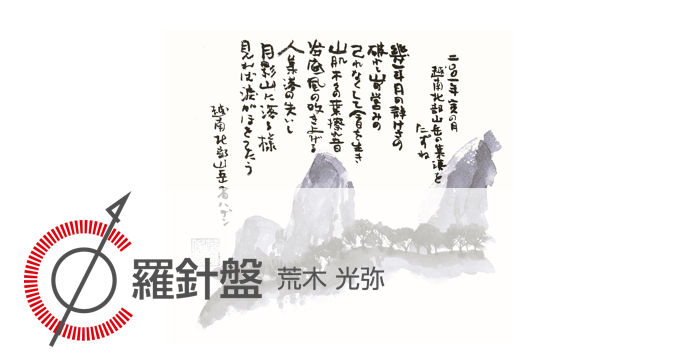多民族適応型人材
経産省とJICA(青年海外協力隊事務局)主催による公開セミナー「企業が求めるグローバル人材」が昨年12月、東商ホールで開催された。基調講演は三菱商事会長の小島順彦氏による「日本の創造に向けて~求められるグローバル人材」であった。
筆者は小島会長の発言からグローバル人材に関する1つのキーワードを選んでみた。それは、事業の国際化あるいは現地化に伴う「国際適応型人材」、もっと正確には「多民族適応型人材」である。
小島会長は若い頃、サウジアラビアの三菱商事系列の会社勤務を命ぜられた。赴任して驚かされたことは、その会社がなんと十数カ国もの国籍をもつ民族混合で成り立っていたことだった。だから、コミュニケーションは当然ながら国際共通語の英語であった。ところが、その英語も文法無視の驚くべきブロークンであったが、お互いにしっかりと仕事上の意思疎通ができることが最大の目標であったという。これが、グローバル人材論に貴重なヒントを与えている。
企業のグローバル化は、まさに企業の多国籍化を意味している。したがって、グローバル・ビジネスは世界各国の民族、宗教、慣習、ものの考え方の異なる人びとと生活を共にし、そして対話し、その意思疎通によって信頼関係を築き上げて、一つの合意を形成できる人材を求めている。そこから企業経営の安定化、現地化、また新しい製品開発が生まれ、新しい市場開発も進展しよう。今、話題のBOPビジネスもグローバル・ビジネスそのものと言ってもよい。
さらに、小島会長の言葉を借りると、「商社は今やモノを動かす貿易だけでなく、世界中でいろいろな事業を展開する企業である」に注目してみたい。よく考えてみると、輸出入の貿易は当該国社会のひと握りの人びととの接点でビジネスが完結する。だが、起業し、それを経営することになれば直接的な利害関係のみならず、その国の社会、そして、そこに住む人びととの信頼関係を築かなければならない。海外での一つの事業はその社会、地域の人びとの理解を得ることなくして永続きできるものではない。
最近、急速に企業の関心を高めているCSR(企業の社会的責任)も、進展する企業のグローバル化の中で必要条件になっている。だから、これもグローバル人材に期待される重要な素養の一つだと言える。
もう一度学習してみると、グローバル人材とは、世界共通語の英語を駆使できるだけでなく、世界中の多様な民族、人種と偏見なく生活を共にしながら相互理解を成し遂げて、一つの事業に関する合意(コンセンサス)を形成できる人材を意味している、と言いたい。そのためにはテクニカルなことだが、他人種との対話の進め方や対話を成功させる方法(ディベート)などを習得しなければならない。
注目される「現職参加制度」
周知のように、企業のグローバル化は総合商社や大手企業のみならず、世界に大きな供給シェアを有する独自技術をもつ多くの企業群も地方の産業空洞化をもたらすほどグローバル化に向かっている。日本の企業にとってはそうしないと、これから生き続けられない厳しい環境が待ち構えている。それは円高による日本企業の海外進出といった一時的な現象だけにとどまらない。
だから、そこに広くグローバル人材を求める時代的な背景がある。すでに三菱商事は事業のグローバル化の中で、全世界で外国人従業員を2万人も雇っているという。昔は現地化企業の幹部やその候補生は、なにがなんでも本社の社員から選抜していたが、今では進出している国の優秀な現地社員を幹部社員として抜擢して大切に育てている。
しかし、企業はこうした選択をあえて行っているのではない。日本人の経営する企業ならば、海外で働く幹部はやはり日本人のほうが最適である。ただそう願っても、最近の日本の青年たちの多くは、日本にどっぷりと安住して海外への関心も好奇心も薄れ、内向き志向を強めている。
彼らは途上国ともなれば、生活環境、子どもの教育、社会的な不安定性などを問題にして海外赴任を敬遠する傾向にある。企業のグローバル展開において新興国を含む途上国地域が将来性の一番高い市場であるにもかかわらず、途上国を苦手とする社員が増えている。
そうした中で、途上国に自ら志願して何か役に立ちたい、そして自らを試したい、未知の世界へ挑戦したい、という青年海外協力隊の存在が、企業の関心を集めている。それは協力隊経験者を雇うこともさることながら、企業が採用した若い社員を2年間、アフリカなど厳しい環境で鍛え直して、企業のグローバル展開の中で活用したい、と考えるようになっている。青年海外協力隊には以前から企業の「現職参加制度」が存在しているが、今では、それが企業の外向き社員の育成制度として衆目を集めているのだ。
期待される青年海外協力隊像とは何であろうか。それはまず、隊員は現地対応の完全なマニュアルを持たなくても、臨機応変に急ごしらえのマニュアルを自ら考案して行動せざるを得ない環境に置かれる。日本では社員が統一された企業の行動様式をとるように一定のマニュアルを用意しているが、それに馴らされると、新しい事態に対応できる臨機応変のマニュアルを自らつくって行動するバイタリティーが失われる。
ところが、企業活動は常に外部要因に左右されるケースが多い。特に、途上国での企業活動では、日本と異なるマニュアルが求められる時が多い。だから、変化に鋭く反応できる社員が必要になる。その条件を満たしてくれるのが生活条件の厳しい途上国に赴き、その中で悪戦苦闘してきた青年海外協力隊だというのである。
第2に、派遣隊員は現地に溶け込むよう努力しなければ、任務を果たせない。溶け込むということは、グローバル人材の必要条件でもある異文化を理解し、現地と対話できる能力を磨くよう努力することである。溶け込んで仕事の了解を取り付ける。これは現地との対話によって一つの約束(合意)を取り付け、事業を軌道に乗せることを意味する。
企業が現地経営で成功する要諦は、コミュニケーション(対話)による現地社会とのコンセンサス(合意)づくりにある。隊員たちは大なり小なり企業の必要とするグローバル人材の要件を満たしていると言える。しかも、現地で言葉が十分でない状況下でもコンセンサスを得るよう努力するという経験は、グローバル人材の要件を満たしていると言える。
幼稚園から“世界教育”を
それにしても、「外向き」青年の減少は困ったものである。それが、日本の国際的な企業活動にも支障をきたし始め、これからの日本に必要なグローバル人材の涵養にも大きな問題を投げかけている。たとえば、政府は新成長戦略の一環として、パッケージ型大型インフラ輸出を掲げている。それを実現するためには、開発プロジェクトをめぐる水面下での交渉能力、時に相手政府とのコンセンサスづくりで、相手を説得できる力量を備えたグローバル人材が商社をはじめとする日本の産業界、コンサルタント業界に不足しているとなれば、政府の戦略も絵に描いたモチのようなものになってしまう。
それでは、どうすればよいか。ここで早急に結論は出せないが、その解決を教育に求めたい。
まずは、急がば回れで、基本的には幼稚園、小学校の時代から“世界教育”を実施してもらいたい。たとえば、英国では幼稚園の教育グッズを開発して、まず英連邦に加盟する国々の名称と国旗を覚えさせている。子どもの頃から、どの国が自分たちの味方であるかを教えている。さすがにかつて世界に覇権を確立した経験は今も生かされている。教育に首を突っ込む気はないが、もし“世界教育”を実施するとなれば、新たに、それを教えられる外向きの専門教師を育てることも一考であろう。内向き青年教師では外向きの子どもを教えることはできない。日本は世界を狭くしては生きられない。
※国際開発ジャーナル2012年2月号掲載