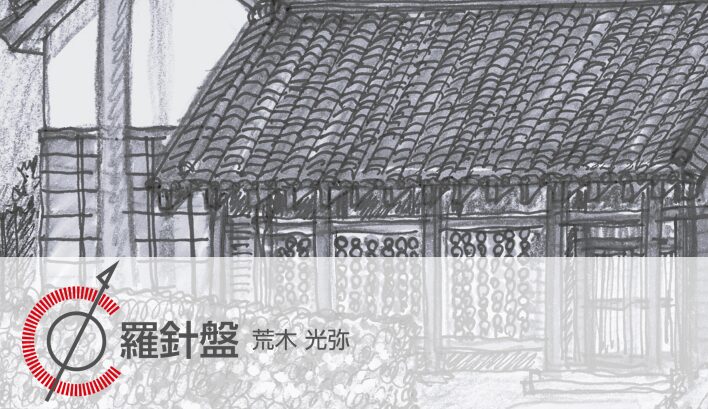“ミスター円借款”の昔話
賀正 新年号で一般の読者にとって難解かもしれない円借款特集を組んだのは初めてのことである。
その訳は、これからのODAにとって円借款がいかに重要であるかを意味しているからである。今や、一般会計(税金)に依存する無償資金協力や技術協力などをこれまで以上に維持することは、極めて難しくなっている。残された道は、まだ余裕のある財投資金、途上国からの返済資金の運用などで円借款をいかに上手に運用していくかにかかっている。
援助現場を担当するJICAは、もっと“売れる円借款”を目指して、大胆な提案を政府にぶつけるべきではなかろうか。
ここで、少し昔話をしてみたい。この話は1980年代の円借款改革物語である。当時の円借款は、1999年に輸銀と政策的に統合されたOECF(海外経済協力基金)が実施していた。そこに、1964年に第一期生として入団した3名のうちの一人、故山本海徳氏がいた。筆者は彼のことを“ミスター円借款”と言い、いろいろ勉強させてもらった。その学習第一号が円借款の援助としての精度を高めるための闘いであった。
それまでの円借款は援助される国の輸入資本財などの外貨分を手当てしていた。だから、商社マンたちは円借款を“円クレ(クレジット)”と称して、いわば一種の輸出増進手段として便利に使っていた。
ところが、実際には援助される国の開発予算(内貨)不足で、円借款は援助としての機能を発揮できなくなった。多くの実施予定プロジェクトが停滞していく。
OECFの若きプロパー、山本海徳たちは円借款をより一層援助効果を高めるために円借款による「内貨融資」を主張し、筆者も一緒に政府へ向けてキャンペーンをはった。政府には自助努力という面から「内貨融資」援助は筋が通らない、と反論された。論争の末に、1985年に「内貨融資」方式が決まった。山本海徳氏はそれをインドネシア首席駐在員の時に実施した。
内貨融資制度のスタートから2年がたっていた。1987年度の対インドネシア円借款は総額880億円。このなかに内貨融資が盛り込まれ、これによって援助案件の遅れを取り戻し、内貨手当てという国内財政支援も可能になった。内貨分は別途のローン・アグリーメント(L/A)を結ぶことになったが、案件全体の30~40%を占めるローカル・コスト分も救済することができた。
当時のインドネシアは石油価格の大幅下落で政府予算が枯渇していた。日本の財政支援は、インドネシア政府のなかに深く記憶されている。今回の東日本大震災でユドヨノ大統領の発言、「恩返し」には、こうした日本の援助の歴史が刻み込まれている。
円借款の改革には、援助としての精度を高めようと努力してきた山本海徳氏のような裏方がいたことを忘れるべきではない。そうした歴史の一考察を心に秘めて、“売れる円借款”、“魅力ある円借款”を目指してもらいたい。
当面の課題はスピードアップ
そこで、筆者は自分なりにいくつかの“売れる円借款改革”の提案を提示してみたい。
(1)迅速な運用
円借款のスピードアップは、経団連も幾度となく提言しているように、最も重要な課題であるにもかかわらず、大きく進展していない。援助案件といえども、優良案件については他の援助国との競合もあり、援助としての“国際競争力”が求められる。
そこで第一の指摘は、F/S(可能性調査)の要請からL/A(借款協定)の締結、そして工事期間までを半減すること。そのためには、少なくとも円借款要請からL/Aまでを9カ月ぐらいで処理するスピードが求められている。9カ月といってもこれも一つの標準期間であって、6カ月への短縮にも挑戦すべきだ。今では標準期間9カ月の4倍近い3年以上の歳月を費やしているから、開発ニーズにタイムリーに対応しているとはいえない。3年の歳月でどれほど世界の情勢が変わるか、ものの考え方も大きく変わる。これだけで“売れない円借款”になってしまう。
第二の指摘は一口で言うと、政府の意思決定の信じられない遅さである。
円借款の決定プロセスには、①財務省主計局、国際局、②外務省、③経済産業省が関与している。各省には、政策的なチェック・ポイントがあるが、それは時にして大局的な見方からのチェックではなく、JICAなど実施機関レベルのチェックにまで及んでしまい、政府の決定をいたずらに遅延させる原因になっているという指摘がある。これは、まさに人災である。もし各省が、本業が忙しいので、と言い訳をするならば、官邸レベルの政治的決定へ移したほうが日本のためになる。
他の援助主要国では、援助省なり援助庁なりの専管省で手際よく案件決定を行っている。日本の3省機能が国際競争力を持ち得ないならば、小さくても援助専管省なり庁なりの設置が必要になるのではなかろうか。政治家も国益としての円借款に目覚める必要がある。円借款に国際競争力があっても、行政面でそのスピードアップを阻害しているならば、ことは重大である。
(2)技術協力の重要性
ODAの一般会計予算の凋落で、技術協力もその影響をもろに受けることになる。これには強く警鐘を鳴らしておきたい。
とにかく円借款をODAの“売りもの”にするならば、魅力あるものにしなければならない。そのためには、単に開発資金を優遇条件で提供するだけでなく、それに援助としての質を高める幅広い技術協力を加えると、そこに大きな付加価値が生まれる。まず、どうしても必要なものは、開発計画の全体像を描くマスター・プラン、そのプライオリティーに従ったF/S(プロジェクト可能性調査)、そして人材育成であるが、その全プロセスにおいてコンサルタントの活躍は言うまでもなく、政府と民間(各産業)との連携は欠かすことのできない必須条件である。
為替リスク軽減
マスター・プランの段階からの民間との連携はリアリティーを伴うものでなければならない。援助される国々にとって、資金と優れた計画と技術が結合したリアリティーの高い総合的で複数事業を内包する包括的円借款アプローチ(たとえば、パッケージ型インフラ建設)ならば、円借款の最大の難関である“為替リスク”をも乗り越えるほどの魅力が出てくる。たとえば、2011年8月にインドネシアとE/N(交換公文)締結した「地熱開発促進プログラム」などは、その良い例である。
このように、最近始まった複数事業を内包した包括的借款契約は、本邦の優れた技術を生かしたタイド型の「STEP制度」の改善にもつながるものである。ところが、計画が大型化するにつれて供与金額も巨額になる可能性が出てくる。すると、そこには円借款の、この国には年にこのくらいという年次供与枠が設けられているので、一種の制約条件になってくる。だから、こうした古い制度の見直しも必要になる。
(3)外貨建て借款の導入現在のような円高になると、実業界にも為替リスクを伴う円借款事業に魅力を感じなくなっているようだ。為替リスクは借り入れ国に最も大きなダメージを与えている。
そこで円貨建て借款でなく、外貨(ドル)建て借款が求められている。すでにアジア開銀、世銀、フランス、ドイツなども外貨建て融資を実施しているが、この傾向はこれから国際的にますます広まることが予想される。
日本ではすでにリーマン・ショック以来、JBIC(国際協力銀行)が外貨貸しを行っているので、もし平等に扱うならば、円借款での外貨貸し適用ができないことではない。とにかく、円借款の泣き所は為替リスクである。かつてこういう議論もあった。
為替リスク解消の最善策は、現地通貨建て返済であって、日本に現地通貨ファンドを設けて、商社などの貿易決済などで活用してもらう、という考え方。これから先、国際的な決済通貨ドルが不安定になれば、こういう話も実現性を帯びてくるものとみられる。
円借款の“売れ行き”は、その為替差損防止が最大のカギを握っているといってもよい。
※国際開発ジャーナル2012年1月号掲載