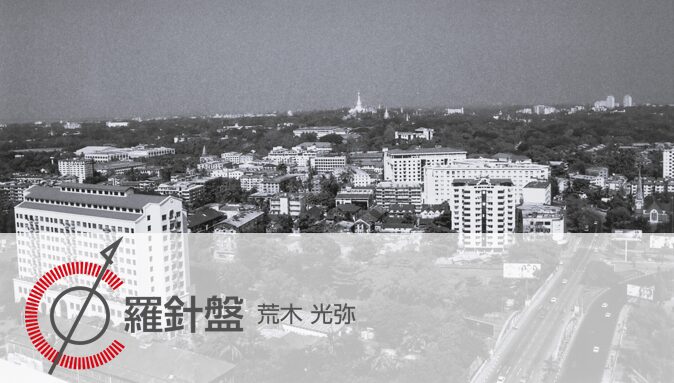試練の“選択と集中”
「わが国ODA事業の戦略的展開に向けて」と題する提言が、日本の開発援助を頭脳、技術の両面から支える開発コンサルティング企業集団の海外コンサルティング企業協会(ECFA)から1月25日公表された。
その中身は、提言の視座から始まって、円借款協力、技術協力、無償資金協力、海外投融資のODA事業全般をカバーしているが、常にODAの現場で仕事をしている開発コンサルタントの経験にもとづいた提言だけに臨場感がある。提言は大所高所から、また現場体験からODAを戦略的にとらえようと努力している。
ところが、開発コンサルタントに援助事業を委託する実施機関のJICA(国際協力機構)には、この提言をめぐって賛否両論の波紋が広がっているようだ。その動きを見ていると、円借款協力に関しては、ほぼ5年前にJBIC(国際協力銀行)から分離統合しただけに、JICAでの歴史が浅く、開発コンサルタントとの馴染みが薄いこともあって、これまでの円借款改善をめぐる提言の延長線上に止まっている感じだ。
一方、可能性調査や総合開発計画(マスタープラン)づくりなどでJICA創設以来、深く関わり合ってきた開発コンサルタントにとって、JICAは勝手知ったる他人の庭のようなものである。技術協力とは古い付き合いだ。だから、その提言には現場感があり、長い歴史を伴う不満感もにじみ出ている。それゆえに、JICA側から見れば、「そのように見られていたのか」とショックを感じる人もいるかもしれないが、提言する方も私利私欲で問題を指摘しているわけではないので、ここは冷静にして謙虚に判断して、客観的に「外から見られているJICA」を知り、その反省を組織改革、機能改革、そして精神改革へと転換させて、減少したODA予算を有効活用する新たな制度設計に立ち向かってもらいたい。
とにかく今のODA実施政策や制度は、必死に援助量をこなしたODAバブル時代から継承されたものが多い。今は、少ない資金を日本の国益にも配慮しながら“選択と集中”させて、戦略的に日本と途上国とのWin-Winの関係をつくっていくことが求められている。その上、途上国援助をめぐる国際環境は大きく変化している。援助された国が援助する国に変身し、昔からの先進国と言われる援助する国々が経済的に地盤沈下している。したがって、これまでの国際的な一種の援助倫理観も失われつつある。
そうした中で、援助のもう一つの側面である“外交の手段”としての援助効果へ期待が高まる。そこには、日本の国益を求める声も反映されてくる。その場合、日本の国益追求も相手の理解を得なければ成立しない。その意味でも相手に役立つことを前提に、日本の国益を追求するという、Win-Winの援助思想が求められている。こうした時代の要請をどう受け止められるのか。それは次世代に課された使命でもある。
ODAのアジア回帰
筆者の感想はここで終わり、次に重要と思われる提言をピックアップしながら、コメント付で紹介してみたい。
(1)提言の視座に注目したい。はじめに「国民負担が増す中で、わが国ODA事業はいかにあるべきか、今一度立ち止まって考えることが求められている」と、提言の大前提を明確にしている。そして、その大前提を受ける形で「世界の経済成長センターのアジア重視を深めるべきだ」と明言し、なぜならば「アジアの今日的な経済成長は投資と貿易を誘引した長年にわたるわが国ODA事業の成果だ」と強調する。地勢学的にも、新興国であろうが途上国であろうが、ODAの“アジア回帰”は戦略的に日本の総意と言える。6月に第5回TICAD(アフリカ開発会議)が横浜で開催されるに当たって、これは皮肉な指摘かもしれないが、一般国民の本音でもある。
次いで「日本はもはや援助大国ではない」という認識の上で、「大幅に削減された税金依存の一般会計ODA予算による技術協力や無償資金協力には“選択と集中”が求められる」としている。この考え方が技術協力などへの厳しい提言に結びついている。
最後に、注目すべき指摘を取り上げてみたい。それは「わが国では世界で活躍できる開発人材が不足している」である。その人材とは、単にODA現場だけの人材ではないと思う。日本では経済再生に向けて海外へのパッケージ型のインフラ輸出などが叫ばれているが、その注文をわが田に引き込むためには魅力ある計画の絵を書ける人材が必要であるのは言うまでもなく、その絵を売り込める専門的な説得力を持ち、政治性はもとより国際性豊かな人材(プログラム仕立人)が必要になる。
(2)円借款事業への提言の執頭は、これまで幾度となく求められた「スピードアップ」だ。コンサルタント選定から本体工事の契約までほぼ7年の歳月を費やしているケースがあるが、これではプロジェクトの必要性のタイミングが大幅にずれるために、その国の発展とテンポに大きな影響を与える恐れがある。また、日本は厳しい国際商戦に勝ち抜けない。貸すお金は政府開発援助であっても、その資金が動き始めると、そこは激しい国際商戦の渦の中だ。だから、円借款を国益に資するためには、援助オペレーションを短縮しなければ商機を失うことになる。問題はJICA側の機動性にも問題はあるが、より根本的なところでは、役所のたらい廻しのような認可業務が大きな要因になっている。
円借款は原則アンタイドというDACの規制がかかっているので、日本のお金でありながら“日本の顔”の見えないプロジェクトになっている。その束縛をこじ開けて生まれたのが本邦技術を活用したSTEP円借款である。しかし、これも相手国の理解が得られないと成立しない。そこには日本の技術力を売り込める人脈が必要であり、先に述べた開発人材の不足がSTEP円借款にも暗い影を落としている。
ダイナミックな事業運用を
(3)技術協力は“日本の顔”を一番良く見せられる分野である。提言は厳しい。第1に、短期、小規模で成果も限定的となる「ばらまき」型の傾向を指摘している。「ばらまき」に見えるのは、一つに、これまでの慣例に従って5年ひと節で相手に引き渡すシステムが自動的に実施されたせいではなかろうか。重要性を考えて、メリハリを付けることができれば、そう見られなかったのではなかろうか。
最悪のケースは相手に継続する実施能力がないにもかかわらず、慣例通りにプロジェクトを引き渡して、期待通りの成果を上げられなかったことである。しかし、筆者が過去の技術協力を調べた中には、たとえば、シンガポールの生産性向上運動(5S)、マレーシアのSIRIM(工業標準研究所)、タイの30年以上の援助史を誇るモンクット王工科大学、さらには20年のケニアのジョモ・ケニヤッタ農工大学のように日本の知見が今も生かされているアセット(財産)が多々ある。これらに共通して言えることは、歳月をかけたからこそ、日本の知見が熟成され、日本の存在感を残していることである。これこそ「日本の顔」の見える技術協力の典型だと言える。そこには、まさに選択と集中が見られる。
第2は、JICA内の管理上の問題であるが、命令系統の不備が現場での混乱を引き起こし、事業のムダを生んでいるという問題提起である。これは現場だけの問題でなく、むしろJICAの組織上の欠陥を露呈しているとも言える。組織的には上意下達の責任体制、指令体制が理事会から始まって下部への指令、命令伝達が不備のままではないか、という機構上の欠陥にもつながる重大問題である。命令系統の完成度は、責任を取る、責任を取らせる厳格な組織上の系統づくりと、仕事に対する倫理観、つまり国民の信託を得て、国民の貴重な税金で組織を運営して、日本の国際貢献に挺身している、という信念と誇りを身に付けるよう一層努力しなければならない。
※国際開発ジャーナル2013年4月号掲載