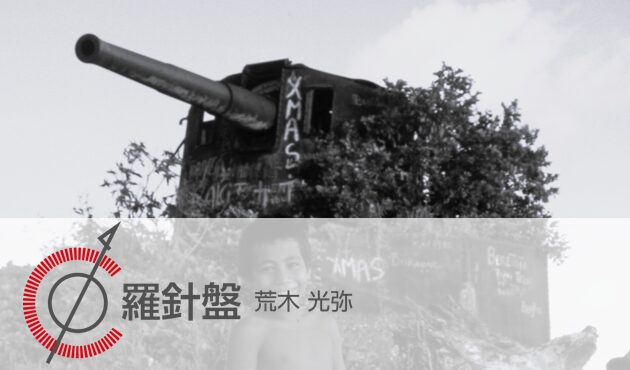ODAの聖域とは
時のたつのを恋しく思う昨今だが、もう12月号の羅針盤を書いている。今年の途上国援助の世界は、民主党政権の事業仕分けに始まって、第3弾の仕分けで終わることになりそうだ。
たしかに援助実施面での反省すべき点、改善すべき点は長年のマンネリズムの中で蓄積されていたと思う。だから、そうした面についてはムダのない税金の遣い方という観点から、事業仕分けはそれなりに理解できる。
他方、途上国援助の新しい基本政策は前・岡田外務大臣の下で「開かれた国益の増進」という報告書に提示されている。“開かれた国益”とは、いかにも苦しい言いわけのように感じるが、それでもタイトルに国益を明示したことは画期的なことである。
しかし、問題はこれだけ大騒動しながら、「こういうODAならば、税金を投入しても国民の信託に応えることができる」という具体的な方針が示されなかったことではないだろうか。たしかに900兆円近い国家の借金は将来に大きな禍根を残すゆゆしき問題である。だから、徹底的に歳出カットしなければならない。その意味でODA予算も聖域ではないという。
特に、財政当局は「聖域」という言葉を好んで使う。ここで言葉遊びをしようとは思わないが、いったい聖域とはどういう意味を指しているのだろうか。常識では、特別扱いされる領域を意味している。これは過去、予算配分で財務省の予算シーリング(概算要求)の枠組みを無視する形で特別扱いされた80年代後半から90年代にかけての時代的な遺産である。
では、いったい何のために特別扱いされていたのだろうか。当時、外からは日本の経済成長にふさわしい応分の国際貢献(ODA)が求められた。外圧に屈したという点では非常に残念ではあるが、それは一つの日本の政策の一環として実行に移され、80年代末から90年代にかけてトップドナーへと登りつめた。こうした実績は財政的に特別扱いされた“漠然たる国際貢献”による結果であった。
言うならば、「特別扱い」とは政策なき援助のことを指しているともいえる。もし、そうであるならば、「ODAでの聖域を認めない」という財務省の考え方は正しい。政策なきものに国民の税金を投入することはできない。
援助を削減しない英国
ここで、最近の英国のケースをとりあげてみたい。英国の新政権も日本と同じように国家財政の建て直しに必死である。財政削減を徹底的に進めている。予算編成では増税方針に頼らず、福祉、教育関係予算、それに援助予算をそれほどカットせずに、他の予算を大幅カットする方針のようだ。日本では真っ先に削減される援助予算が、英国では特別扱いされている。これは、いったいどういうことなのだろうか。
第1に、政策ビジョンの一体化という観点からは、福祉、教育と人間の安全保障としての途上国援助とを思想的に同一視していることが見えてくる。第2に、このほうがより本質的かもしれないが、英国という国が、政治的に、経済的に生存していく上で、途上国援助は必要欠くべからずの基本的条件であることを意味しているのではなかろうか。
具体的には、一つに、旧植民地の多くのアフリカ人、アジア人などが英国国籍を取得して、市民権としての選挙権を持っているので、選挙という政治局面からは彼らの同胞を国家として助ける援助を重視せざるを得なくなっていること、二つに、今も途上国を中心とした多くのコモンウェルズ(英連邦)諸国との政治・経済関係が維持され、既得権益の保持のために特に経済関係の相互依存は無視できない存在であること、などがあげられる。
なかでも植民地時代から築き上げられた政治、経済、文化などの既得権益を維持するコストとして対外援助予算が位置付けられていると思う。建て前上は、普遍性をもつ人間の安全保障としての「貧困削減」を掲げているが、そこはアングロサクソンらしく、本音ベースでは上記のような既得権益を守るという国家安全保障が求められており、それが財政削減の犠牲にならない最大の理由だといえる。
これは、「さすが」としか言いようがない。英国にとって対外援助は経済再建、財政再構築を押し進めていく上で必要欠くべからずの政策なのである。英国のコモンウェルズ諸国との関係が弱体化していけば、英国の財政再建もままならない、という認識の下で戦略的な援助政策を進めているといえる。
ひるがえって日本を見てみると、ODAが激減すると、具体的な形で財政再建にマイナスになるという状況は見えてこない。その程度の援助ならば、この際カットしてもよいという考えに走ってしまう。財務省はそれを見越して、“聖域を認めない援助”といっているのかもしれない。もし、日本のODAが人間の安全保障という建て前だけでなく、政治、経済的上の国家安全保障と深く関わり合っているならば、財政再建にも支障をきたすことになるので、それなりの手当てをしなければならなくなるはずだ。
しかし、非常に残念ながら、過去のトップドナー時代から今日に至るまで、国際貢献の建て前道を歩いてきた日本にとって、一国一国へのODA供与が日本のサバイバルと深く関わっているとは思えない。その意味で、特別扱いされる存在にはなり得ていない。
逆に、特別扱いされるためには、ODAで途上国とのWin-Win関係を維持し、少なくとも半分ぐらいは、日本のサバイバルに必要な政策に基づくODAでなければならない。つまり、“必要経費としてのODA”になるためには、必要経費にふさわしいODA政策が必要になる。それでは、その政策があるかと問われれば、たとえ部分的にあったとしてもオールジャパンという立ち位置でのODA政策は存在しないのではなかろうか。
新成長戦略との共存共栄
今のODA政策は外務省ベースで見る限り、国際約束ベースのものが基調をなしており、日本経済と深く関わる国内的要請ベースのものは極めて少ない。たとえば、ODAのツールを使っての地方活性化、国際化につながるような援助計画、日本特有の環境技術を使って国際的な環境技術市場へ進出する計画、教育援助を通して、途上国に多くの人脈を形成する計画、日本の伝統的ノウハウ、技術力などを生かした総合開発計画づくりなどが政策として立案、実施されるならば、ODAは国策という側面からも重視され、それ相応の予算的待遇を受けられよう。
そのためには、外務省だけでなく、各省の協力の上で、政党、政治家が国家的な上位目標をもって政策的位置付けを行う必要があろう。最近のニュースで、民主党政権のトップ外交攻勢でベトナムの原子力発電所建設を日本勢が行うことになったと伝えているが、想像するにその裏方には過去から現在に至る円借款協力を中心としたODAの実績が重要なサポーターになっているように思う。このことを経済界も深く考えてもらいたい。ODAはその国にどれだけ貢献したか、役立ったかということで、すべて評価される。そういうことを加味すると、何らかの形で、途上国との関係をODAでつなぎとめなければ、いざという時に役立たない。
それは援助の継続性の問題でもある。したがって、日本にとって経済関係、資源関係上、重要な途上国には一定程度の援助や協力を維持し続けないと、鉄道、水ビジネスにしろ、いざという時に日本の影響力は発揮できない。これは、民主党政権の新成長戦略にとって非常に重要な布石だといえる。その意味においても、まず重点援助国へのODA予算配分を工夫しなければならない。しかし、そのためには戦略的なODA予算の増加が必要になる。
役所の描いた新成長戦略のドラフトを見る限り、アジアの広域的な総合的開発計画が主流をなしている。アジアの広域開発計画では道路、港湾といい、マスタープランづくりから始まって、設計、施工へと続くプロジェクトの流れはすべてODAでカバーすることができる。もう一度、ODAを使って新成長戦略を進めてみてはいかがだろうか。
ODAに“国益(国民の利益)”という意義を与えて、戦略的に活用する道を切り開いてみてはどうか。あえて反論を覚悟して問題提起してみた。
※国際開発ジャーナル2010年12月号掲載