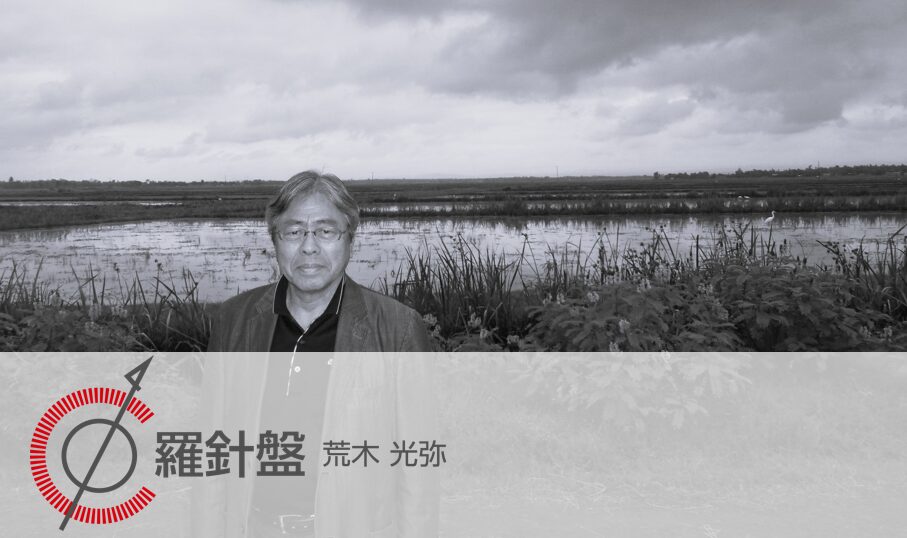国際的な“負のインパクト”
国際社会が協力してアフリカ開発の枠組みをつくっていこう、というのがアフリカ開発会議(TICAD)である。20周年目に当たる今回の第5回会議は、日本のホスト役で来る6月1~3日にかけて横浜で開催される。
しかし、「会議は踊る」と言われるように、国際会議はたしかに踊っている。たとえば、前回の第4回TICADでは「成長をどう加速させることができるか」、「平和をどう築くことができるか」、「地球環境の変化にどう対処できるか」、「2015年までのミレニアム開発目標(MDGs)をどれほど達成できるか」などの目標が提示された。しかし、その内容がどれほどアフリカの実態に迫っているか定かでない。
私たちは国際会議では語られない難解な矛盾がアフリカ大陸にシワ寄せられている現実を黙殺しながら表層的な援助論に終始し、平静を装っているのではないだろうか。そう思うのは筆者だけではないだろう。
今回は専門家の指摘を参考にしながら、アフリカの農業・農村開発に潜んでいる隠された一側面に挑戦してみたい。
1980年代にアフリカの累積債務問題解決のために「構造調整融資」を強行した世銀は、開発の要となるアフリカ農業・農村開発の問題点を的確に摘出している。しかし、努力はそこまでで、その問題点を解決していく具体的な方法論、方策については提示できなかった。そこには、資金力や技術力だけでは解決できない根の深い問題があった。それはアフリカ農業に“負のインパクト”を与えている穀物市場の国際環境である。
筆者が昨年5月に訪ねたアフリカ西海岸のセネガルは、周知のようにフランスの植民地だった。だから、どのレストランでもパリと同じようにパンがおいしい。その訳は原料の小麦をフランスから全量輸入しているからである。また、魚料理を好むセネガル人にはコメも欠かせない主食だ。しかし、これも需要の40~50%を常時輸入している。同じ西海岸沿いのガーナでも需要の40~50%の割合で海外からのコメ輸入に依存している。こうした傾向は大なり小なりアフリカ各国に存在している。こうしてコメなど穀物輸入のために貴重な外貨が流出している。
農業開発への壁
ところが、問題は食料の高い輸入依存度だけではない。海外からの大量の安い穀物輸入によってアフリカの農業が成り立たなくなっていることである。日本はアフリカ農業開発の一つの柱として、日本が研究支援したネリカ米の普及を目指しているが、いかんせん安い輸入米には太刀打ちできない。
アフリカ各国の政府にしてみれば、長期にわたって大きな財政投入を余儀なくされる農業開発よりも、外貨を手っ取り早く稼げる地下資源開発および工業化に力を入れたくなる。アフリカ各国のリーダーたちは、農業開発とその構造改革にかなり長い時間をかけて、継続的な財政投入を図らないと、海外から輸入される価格競争力のあるコメなどの穀物には対抗できない、と思っているに違いない。
だから、どうしたら輸入食料と互角に闘えるコメなどの食料作物を生産できるかが、アフリカ農業の最大の課題になる。そのためには、厖大な農業投資を長期にわたって実施する必要がある。しかし、言うのは簡単だが、そんな長期投資の資金力は、石油など有効な資源を有する国を除いた他の多くのアフリカ諸国には期待できない。だから、いきおい先進国の援助に依存せざるを得なくなる。しかし、今の先進諸国にはヨーロッパを見るがごとく、継続的に援助できる資金力はない。その意味で、アフリカ人によるアフリカ農業の前途は暗い。
すでに知られているように、欧米、中東産油国、中国などがアフリカの大地を買収して囲い込んでいる。おそらく大規模なプランテーション農業を興すことになろう。聞くところによると、コンゴなどはすでに国土の半分ほどを外国資本に売却しているという。ある意味で、植民地主義の再来と言えないことはない。
そのうえ、アフリカはWTO貿易自由化の傘の下で、先進農業大国、それにアジアのタイ、ベトナムなどのコメ輸出国の食料輸出の草刈り場の猛威にさらされている。こうした国々の安値攻勢から自国農業を守るには、好むと好まざるにかかわらず、アフリカ諸国が食料の一定の自給率を達成するまで、食料の輸入関税障壁を一定期間認めることしかない。
ところが、こうした話を日本政府に提案しても、ただ一言、「農業大国の米国が横になったら、すべては終わりですからね」と答えるに決まっている。世界の援助大国がアフリカ開発を熱っぽく語っていても、ひとたび自国の国益に抵触すると、開発援助の正義は葬り去られる。
農村の凋落は国の凋落
かつて冷戦時代は、アジアにおいて国家の安定のために経済開発が優先され、外国の経済攻勢から自立化を守るために高い関税障壁が設けられた。工業分野では輸入品に高関税をかけたので、日本など輸出国は、その国に進出して、輸入代替産業を興した。“緑の革命”に支えられた農業分野も高関税に守られて、自給率を高めた。
ひと口に農業と言っても、その主役は農民であり、そもそも国家は農村社会の健全な発展に支えられている。どの国も農業社会は国を支える要である。それはその国の活力の源泉でもある。民族国家の形成からみても、農村社会の凋落は、その国の凋落にも通じる。私たちは、最も大切なことを議論せずにアフリカ開発を語っているのではなかろうか。実に不可解である。
とにかく、アフリカの食料問題は人口増大とともに重大な社会問題になっていく。アフリカでは、今も25歳以下が人口の3分の2を占めている。増大する若者人口を工業化だけでは吸収できない。魅力ある農村づくりで若者たちに雇用機会を提供する必要がある。さらに、食料事情の改善を図らないと、食料価格が上昇し、食費に占める食料コストが高まれば高まるほど賃金を押し上げていく。
今でもアジアに比べてアフリカの賃金は高いと言われている。このままだと労働集約的な産業の発展は見込めない。そうすると、増大する若者労働力を吸収する道が閉ざされることになる。
だから、今の状況下では、アフリカにはアジア的な発展モデルは望めないかもしれない。しかし、ひと口に「アフリカにはアフリカの道がある」と言っても、一国の発展のためには、一度は通ってもらいたい道でもある。そうしないと、近代国家として次へのステップを踏み出すことが難しくなる。
人びとは、簡単にアフリカの食料問題を語るが、とくにアフリカにとって農業の持つ意味は大きく、それは国の在り様にも及んでいる。
※国際開発ジャーナル2013年2月号掲載