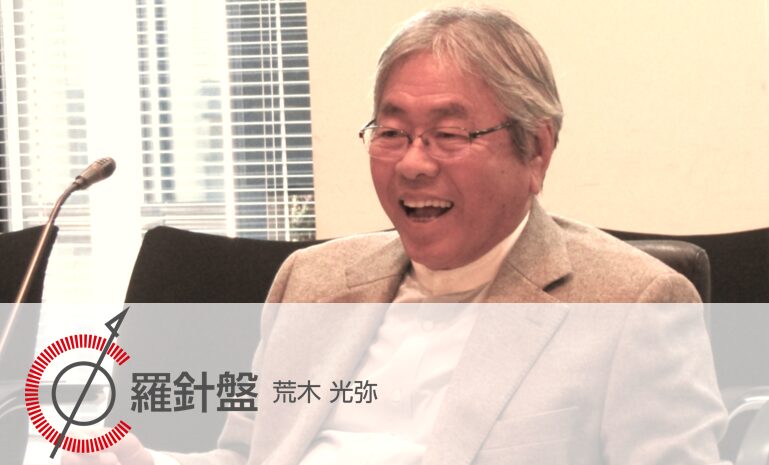地盤沈下のヨーロッパ
2013年元旦。新年おめでとうございます。
国際社会は大きく変動している。それを国際開発、開発援助の分野において展望してみると、「援助大競争時代」の出現が予想される。それは端的に言うと、台頭する新興国が外交の手段として政府開発援助(ODA)を巧みに使い始めたからである。その代表格が中国、韓国、ブラジル諸国である。ここでは、この3カ国を中心軸にして「援助大競争時代」を描いてみたい。
周知のように、かつて多くの植民地を支配してきたヨーロッパが途上国援助の中核を形成してきた。それは、過去の贖罪意識、関係の継承という観点からみて当然の成り行きと言える。
しかし、そのヨーロッパ(EU)はギリシャの財政危機にとどまらず、潜在的にはスペイン、ポルトガル、イタリアも危険視されている。海外放送を聞いていると、スペインのテレビ放送TVEは、トップニュースで毎回のように失業者の増大に警鐘を乱打しているし、隣りのポルトガルについては皮肉にも、かつての植民地ブラジルの資本が、経営に行き詰ったホテル、大農園、あげくの果てには国営航空会社まで買収しようとしている、とヨーロッパの衰退を嘆く。さらに、新興国・中国の陶器などの安値輸出攻勢で、ヨーロッパの伝統的な陶器産業は大きな打撃を受けて悲鳴をあげている。元気なのはドイツだけである。
だから、第二次大戦後、ヨーロッパ復興のためにパリに設立されたOECD(経済協力開発機構)の下部組織DAC「開発援助委員会」も、ヨーロッパの地盤沈下の中でかつてのような勢いはない。EUは欧州復興開発銀行の途上国融資を少しソフト化してODA勘定に組み込めないか思案している、という話が伝わってくるくらい、ヨーロッパの財政事情は苦しい。だから、ODAのお目付け役のDACもその神通力を失いつつあり、これまでの途上国援助の考え方を変えようとしている。
先年12月に来日したDAC議長のブライアン・アトウッド氏(元米国国際開発庁=USAID長官)は、「これまでの贈与援助や借款協力といった従来からの援助メニューにとどまるだけでは援助の役割を果たせなくなった。新しいODA手法を開拓する必要がある」と、援助の多様な発展を示唆した。そこに登場したのが新興国の中国である。
われわれは中国の援助行為を途上国援助と呼んでいるが、中国はDACの援助思想を宗主国の植民地支配への贖罪を含んでいると言い、その中国もかつて植民地にされたので、最初からDACの援助思想に反発してきた。
その意味でも、ヨーロッパに何百年も植民地支配されてきたアフリカは、中国のWin-Win(互恵)型援助に好意を抱く傾向にある。また、中国はそれを売り物にしている。
新興国・中国の対外援助
2011年に公表した中国の「対外援助白書」によると、その総額は2,562.9億元(約3兆1,000億円)。日本と比較してみると、2011年の日本の円借款協力を含めた総額が約1兆5,800億円であるから、ざっと日本の2倍に値する。
その内訳は、1元=12円で換算すると無償援助が約1兆3,000億円、無利子借款が約9,200億円、優遇借款が約8,800億円である。さらに、債務免除(救済)は約3,100億円に達する、としている。援助対象国は161カ国で、うち約50%がアフリカで、アジアは30%。さらに、76カ国では援助をテコに325の事業を興しているが、うち約60%が経済インフラであるとしている。
ただ、実際は対外援助の範囲は広く、優遇バイヤーズクレジットや中国アフリカ開発基金なども包含しているので、実態は見えてこない。日本では「官民連携」を叫んでいても、DAC規範に忠順である以上、そこまで範囲を広げることはできない。しかし、よく考えてみると、あそこまで官民(民と言っても国営企業だが)が一体化し、資金ソースを一体化しなければ、何もないアフリカで事業を興すことはできない。
しかし、もう一度よく考えてみると、日本も資源開発の大型プロジェクトを“ナショナル・プロジェクト”と称して、あらゆる資金を動員していた。ブラジルのウジミナス鉄鋼開発ではないが、今になって見ると日本経済へのボディブロー効果は大きい。中国はこうした日本の大規模な開発輸入事業を参考にして国家事業(ナショナル・プロジェクト)に仕立て、それにあらゆる援助資金を総動員している。
その結果、現地には税金を落とし、多くの雇用効果を生み、技術移転にも寄与し、貿易も興している。これが、本物の援助かもしれない。
筆者が昨年12月4日の経団連サブサハラ地域委員会で講演した内容も、かつてアジアで経験し、成功を収めた「三位一体型開発モデル」のアフリカ版計画であったが、それは貿易、投資、ODAの一体的、総合的活用で、現在の中国の対外援助モデルと相通じるものがある。もっとも、日本がその元祖なのである。
8%増の韓国援助
さて、アジアでは韓国も黙っていない。資源、市場に乏しい韓国の生命線は海外展開にある。この宿命は、政権交代に関係なく維持されなければならない。
少し数字は古いが、2008年のODA実績は約8億ドルで、日本の10分の1に及ばないが、昨年12月に来社した韓国調査団の話によると、2013年の韓国ODAは8%増を見込んでいるという。この数字は政策的な数字であって、そこにはちゃんと国益が織り込まれているのである。日本とは意気込みがまったく違う。
大野泉氏(政策研究大学院大学教授)は「韓国の援助は“ナショナル・ブランド”を売りにしている」と述べているが、それは中国とは一味違う政策志向と言えよう。中国もナショナル・ブランドの国営企業の売り込みに熱心だが、その必死さから言うと、韓国のほうがより厳しい。それは大なり小なり日本と類似している。
だから、韓国は体制を強化すべく、日本の援助動向、援助体制に注目し、たとえば、韓国外交通商省が監督責任をもつ韓国国際協力団(略称KOICAは日本のJICAと似ているが、実はその実施体制もJICAを参考にしている)なども日本に学んでいる。
昨年、弊社を訪ねた韓国調査団はウォン借款と技術協力との一体化を目指している様子だった。その意味で、円借款を統合したJICAの運営にかなりの関心を示していた。ここでは韓国の援助実態を詳しく述べられないが、一つだけ紹介すると、知的ODAと言われる「知識共有プログラム」がある。
この背景には、新興援助国として途上国と伝統的援助の「架け橋」となり、韓国の経験を“ブランド・パワー”として国際社会にアピールしていく、という戦略的発想がたたみ込まれている。
日本と連携するブラジル
最後に、ブラジルの対外協力にも歴史がある。筆者が1986年に新首都ブラジリアを訪ねた時は、外務省に国際協力局があったが、今では国際協力庁の下で、まずはアフリカではアンゴラ、モザンビークなどポルトガル語を共有する国々への協力を重点的に進めている。
予算のスケール感を見れば、2005~2009年の5年間で約16.1億ドル(約1,288億円)で、同期間の債務救済は約4.7億ドル(約376億円)、食糧支援が約3.5億ドル(約280億円)、優遇融資が約17.4億ドル(約1,392億円)。したがって全体のスケールは5年間で約41.7億ドル(約3,336億円)である。
アンゴラでは医療保健制度の強化、また職業訓練も行っている。中南米地域では地域の警察活動を支援している。さらに、モザンビークでは、日本の協力したセラード農業開発の経験を生かす形で日本と連携してモザンビーク熱帯サバンナ農業開発事業を開始している。なかでも2011年にスタートした技術協力プロジェクト「ナカラ回廊研究・技術移転能力強化プロジェクト」は、農業の適正技術の研究や人材育成という面で注目されている。
ブラジルは日本の大切な友好国である。大統領も「日本と連携してアフリカ大陸での農業分野で貢献すべきだ」と述べている。
ブラジルの国際協力の範ちゅうには、①人道支援、②留学生への奨学金支給、③技術協力、科学協力、④国際機関への拠出、⑤平和維持活動、などが含まれる。ただ、国際協力の理念などは明記されていない。どちらかというと非常に実践的で、かつ国策に沿った外交の一環として国際協力を展開していると言える。
今後、ブラジルも中国や韓国と同様に工業製品、農産物、その加工品などの市場拡大を狙って、経済・技術援助をテコにして途上国市場に進出してくるだろう。日本はこうした動きをどう受け止めるのか。とくに、安く、量を求めるローテク市場は人口が20億人とも30億人とも見られる巨大市場だ。
その意味においても、ビジネスへの触媒効果を果たす開発援助は、大競争時代に突入することになろう。
※国際開発ジャーナル2013年1月号掲載