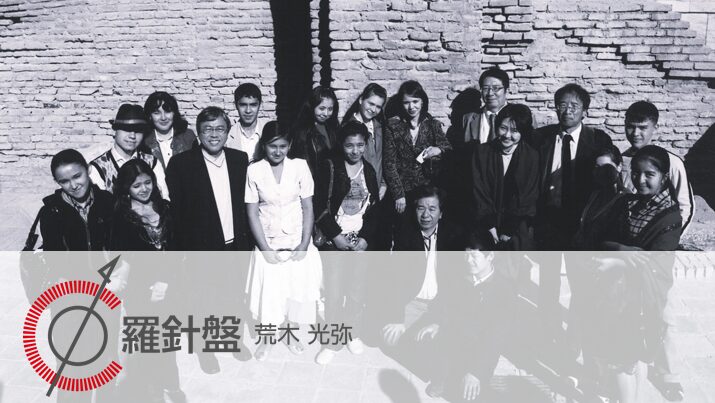激変する「援助される国」
新年おめでとうございます。
冒頭に申し上げたいことは、世界の勢力図、なかでも従来からの「援助する国、される国」の勢力図も激変しているということである。この変化を楽観視したり、軽視したりしていると、わが日本丸は世界航路やアジア航路で座礁、難破することも考えられる。なかでもアジア航路を侮ってはならない。
つい最近まで、私たちが「援助される国」(被援助国)としてみてきた開発途上国が国家としての力量を備え、今では中国のように独自の外交路線に沿って戦略的に対アフリカ援助を展開したり、地球環境問題で「CO2削減の最大の責任は先進国にある」と主張して、先進工業国との対立構図を鮮明化している。こうした国は中国だけではない。インド、ブラジル、メキシコ、南ア、サウジアラビア等々で、ASEAN諸国ではシンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ、インドネシアなども含まれる。周知のように、先進首脳国会議(G7、G8)が世界を差配する時代ではなくなった。最近の首脳国会議はG8からG20に移行している。あと10年もするとG30以上になるのではないかとみられている。
冷戦時代に「南北問題」が登場し、南(途上国)と北(先進工業国)との経済格差是正が唱えられた頃、「世界人口の80%を占めている南側の所得は世界の20%を占めるにすぎない」といわれていたが、今では「その所得が世界の20%から40%以上のシェアを占めている」とみられている。その反面では先進工業国の所得がかつての80%から50%近くにまで下降し、世界的な所得の再配分が着実に進んでいることを物語っている。
現在、その主役を務めているのは地域でみれば、東アジア地域だ。かつて、米国が風邪を引き、日本がクシャミをすると、アジア諸国は肺炎に罹るといわれていたが、それはいかにアジア諸国の対米輸出依存が高かったかを比喩した言葉である。ところが、1990年代以降、アジアの域内貿易が急上昇し、米国への東アジアからの輸出に占めるシェアは、1980年の31%から2008年には16%にまで半減している。日本も17%から8%へ低下した。ところが、中国の台頭で日本を含む東アジアの対米輸出比率は50%近くにまで上昇している。
しかし、アジアは今や世界の工業製品輸入でトップに躍り出ている。そのシェアは2006年のデータで米国15%、日本3%、他のアジア諸国が20%へと成長し、まさに世界にとって「マーケットとしてのアジア」へと大きく育っている。
「東アジア」の核はASEAN
そうしたなかで、鳩山首相は11月13日、シンガポールで開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)で「東アジア共同体構想」を打ち出した。構想自体はこれまでの路線から大きく飛躍するものではなかったが、少なくともアジア諸国に日本の考え方をメッセージとして表現したという意味ではそれなりの意義があったとみるべきであろう。
その際、共同体の芯の部分をASEAN10カ国に置くとは明言していない。これに対し、ASEANからは「ASEAN」を共同体の核にしてほしいと念押しされている。ただ、ASEAN中心は既成の事実として、日本はASEANのネックであるインドシナ半島メコン流域諸国(カンボジア、ラオス、ミャンマーなど)の開発の遅れを取り戻すために、インドシナ半島の物流などを改善するインフラ整備に協力する旨を公表した。その援助資金規模は5,000億円というから、今の日本の財政事情からみると決して少ない数字ではない。そこには日本の政治的意図が手にとるように浮き彫りされている。
アジア太平洋の地域協力ではASEAN+3(13カ国)、東アジアサミット(16カ国)、APEC(21カ国・地域)などの構想が次々と打ち出されているが、それらの核の部分は基本的にASEAN10カ国であると言っても過言ではない。その意味で、日本が今回明言したインドシナ半島の貧困削減に向けたインフラ整備協力は、ASEAN内の貧富の格差を是正しながら、ASEANの経済統合を側面からサポートする政治的意志を明らかにしたものとみられる。
私は、日本のASEAN重視は守るべき本道だと思っている。日本は60年代から70年代における東南アジアの平和と安定を維持するために、ASEANの育成に尽力してきた。60年代の佐藤内閣時代には初めての「東南アジア開発閣僚会議」を東京で開催した。それが日米同盟の証明書といわれようとも、東南アジアは日本経済の生命線でもあったので、日本は日本なりに「東南アジア開発閣僚会議」の意義を見出していた。
その頃、「共産主義の東南アジアへのドミノ倒し的現象」を恐れて米国流「ドミノ理論」が喧伝されていたが、米国は苦戦を強いられていたベトナム戦争を有利に展開するためにも、背後の東南アジアの経済的安定が政治的安定につながり、米国のアジア戦略を利するものと考えていた。
当時の福田首相は、国会議員として初めて国会でASEANの重要性を強調した人である。それゆえに福田首相の、いわゆるASEANに対する「福田ドクトリン」は、シンガポールのリー・クアン・ユー首相、マレーシアのマハティール首相たちに“日本再発見”を促した。特に2つのキーワードは尊重された。「軍事大国にはならない」、「ハート・ツー・ハート」(心と心のつながり)。
その後、その時の「信頼感」はマハティールの「LookEastPolicy(日本に学ぼう=東方政策)」に結びついた。
日本へのアジア的信頼感
私は昨年11月から12月にかけて、日本が40年以上もの長い間、協力し続けたタイのキング・モンクット工科大学(モンクット王工科大学)、これと匹敵するぐらいの長期の協力を続けてきたマレーシアの「工業標準研究所」(SIRIM)、さらに、かつてのシンガポールを支えた「生産性向上プログラム」などを通じて、「日本の知見」がどれほど社会に残留し、それが日本のイメージとしてどれほど定着しているかなどを個別インタビュー方式で探った。
彼らは私たちを快く歓迎してくれた。ここで詳しくは述べられないが、私は彼らの日本に対する一種の「恩義」をハダで感じ取った。そこには「信頼感」があった。日本人のやり方はスマートでないところもあるが、自分たちに知恵と技術を与えてくれた現場的な職人ハダの専門家は、差別感なく、仲間意識で多くのことを教えてくれた、と繰り返し述懐していた。英国には新しい知識があるから学びに行くが、あの上から見下す態度には嫌悪感を今ももっていると語る。
しかし、日本の職人たちは最後の研修旅行先で自分たちと同じフトンで眠り、差別感などほとんど感じなかったと述べ、それが青春の良き思い出になっているようでもあった。
私たちの先輩たちは、東南アジアの現場で日本の技術や制度だけでなく、一番大切な「信頼感」という赤い糸を日本とつないでくれた。
そこで今、最も大切なことは、ODAに例えれば、単純発想でDACの援助基準の国民所得水準からみると、ASEANの中進国といわれるマレーシア、シンガポール、タイ、そのうちインドネシアも入ると思うが、これら諸国を「援助卒業国」とみなして、援助を打ち切る方向にある。私はこの考え方は、より貧しい国へ援助を回すという点では一面正しいが、果たしてODAはそれだけの理由で存在しているのかどうか、貧しい国を助けることも、日本との「信頼関係」をシステムとして維持し続けることも長いスパンで考えると、同じく「国益」に属するものと考えたい。
したがって、アジアの中進国とみられる国々に対しては、従来の「援助する国、される国」という概念と異なる「イコール・パートナー」としての政策的ODAを目指して、過去からの「信頼関係」を未来にもつないでいく新しい協力を、あるいは「ASEANの中の中進国」協力をASEANという地域連携協力形態として、従来のODA予算でカバーすべきである。その根幹を成すものは、モノ、カネから脱皮したヒトの「人間関係」、もっと言えばASEANとの重層的な「人脈形成」に必要な高度教育、高度な知識・技術交流、学問および高度な科学技術研究のための共同研究、協力・交流のネットワークづくりなどを重点に置いた予算配分を行うべきだろう。
民主党政権が「コンクリートから人」へ政策目標を置くならば、「東アジア共同体構想」のより根っことなるASEANとの連携を長きにわたって維持すべきであり、その絆はなんといってもASEANとの重層的な「人脈形成」である。
※国際開発ジャーナル2010年1月号掲載