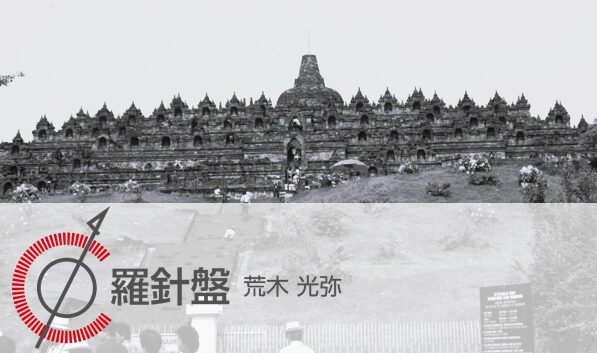新成長戦略と開発協力
ECFA(海外コンサルティング企業協会)の新会長に就任した草野干夫氏(システム科学コンサルタンツ社長)は、新しいビジョンとして開発コンサルタントの“プロフェッショナリズム”の高揚を強調し、「われわれはプロフェッショナル集団であることを自負し、自分たちの専門性にもっと誇りをもたなければならない」と語気強く語る。
日本の開発コンサルタントは、戦前の南満州開発以来の長い歴史の中で育ってきた。たとえば、総合開発計画(マスタープラン)づくりなどは満鉄以来の伝統を継承している。その伝統は、戦後賠償援助をはじめ、東南アジア諸国の戦後の新しい国造りに生かされてきた。ところが、最近ではプロジェクトの「選択と集中」が叫ばれながらも開発プロジェクトの小型化が進んで、本来の開発コンサルタントとしての能力が発揮できず、その能力は年々退化しているとみられている。開発コンサルタント業界からは、①発注量の増大と1案件の小型化、②案件の多様化により従来からのコンサルタントの領域でない業務の増加、③開発調査案件の減少で開発コンサルタントとしての鍛錬の場が少なくなったこと―などの不満が噴出している。
1~2兆円規模の大型インフラ整備、水ビジネス、環境関連ビジネスなどの将来の巨大需要を考えると、「新しい産業を興し」、「経済の活性化を図り」、「新しい雇用を創出する」という開発コンサルタント本来の“プロフェッショナリズム”の復活が待たれる。
8月26日、ASEAN+日本、中国、インドなど16カ国の非公式の経済閣僚会議が開かれ、2020年までにインフラ整備で総額約2,900億ドル(約25兆円)を投資する「アジア総合開発計画」を了承した。この計画をリードしているのは日本で、政府の新成長戦略に一つの道筋をつくっている。
この計画の対象地域は3つで、1つは「メコン総合開発」(タイ、カンボジア、ラオスなど)、2つは「ビンプ(BIMP)広域開発」(ブルネイ、インドネシア、マレーシア領のボルネオ島、インドネシア領のスラウェシ、フィリピンなどを含む)、3つはインドネシア(ジャワ、スマトラ)、西マレーシア、タイなどのいわゆるIMT成長三角地帯などである。
他に、「デリームンバイ産業大動脈」計画がある。これはデリーとムンバイ間を貨物専用鉄道で結ぶ、ハードとソフトを総合的に整備する計画。総額900億ドルのうち、700億ドル程度を民間投資でカバーする。これは4年前の日印首脳会議で合意されているが、昨年12月にはプロジェクト開発ファンドへのJBIC融資契約(7,500万ドル)とスマート・コミュニティーの推進でジェトロとデリームンバイ開発会社で運営協定が結ばれている。なお、貨物専用鉄道整備では4,500億円の円借款供与が見込まれる。
事業立ち上げ能力を磨け
こうした広域開発のグランド・デザインやマスタープランを誰がつくることができるのか。本来ならば、ODAベースの開発コンサルタントの経験とノウハウが生かされなければならないが、果たして今の開発コンサルタントがその需要にどこまで応じられるかどうか、そのプロフェッショナリズムが問われている。なかでも、デリーとムンバイ間に4カ所のスマート・コミュニティーをつくる計画には東芝、三菱重工業、日揮、日立製作所などをヘッドに多くの日本企業が参入している。少なくとも、こうしたコミュニティーづくりにODAソフト系コンサルタントが参入できないのか。ODAがまだまだオールジャパン体制に組み込まれていないようだ。
さきの草野会長の「プロフェッショナリズムの高揚」論は、今の開発コンサルタント業界の苦悩を表している。夢と現実との乖離は大きい。ODA調査事業に携わるコンサルタントの中には、プロフェッショナリズムよりも安易な形での金儲け主義に走るコンサルタントも散見できる。なかにはプロとしての職人気質を守っている者もいるが、全体としては玉石混交の状況にあるといってもよいであろう。これは極端な言い方かもしれないが、ODAの諸悪の根源ともいうべき在外公館ベースの小さな「要望調査」を押しつけられたJICAの委託事業で生計を立てているコンサルタントの中には、徐々に本来のプロフェッショナリズムが希薄になり、ライフワークともいうべき自分の特技が生かされないで苦悩する企業もいる。
では、なぜJICAの仕事をしているとコンサルタントとしてのプロ意識が弱まるのだろうか。関係者の意見を総括すると、次のように指摘している。
「JICA自身に開発事業に対する技術的なプロ意識あるいは大局観に立ったプロ意識が不足している。ノンプロ集団ともいわれるJICAに対応する開発コンサルタントのプロ意識にも“甘えの構造”が生まれ、徐々にプロの厳しさが失われていく」という。さらに論点を煮詰めると、JICAのみならずコンサルタントにも、調査事業が目的化しているところがあるという。つまり、調査という手段が目的化してしまい、調査だけで終わると、一つの計画あるいは事業立ち上げを成功させるという援助本来の目的が失われることになる。開発コンサルタントの仕事はマンマンスの報酬をいただく“一丁上がり”の仕事になってしまい、開発事業を立ち上げるというプロフェッショナリズムの厳しさが萎えていく。
JICAの「ああ勘違い」
これは委託する側が悪いのか、それとも受託する側が悪いのか、厳密にいうと、委託する側に問題があるようだ。つまり、JICA側にプロ意識の低下が顕在化しているからである。その意味でJICA側にプロ意識向上の余地が多く残されているといえる。だから、自分の将来を懸念するコンサルタントの中には「JICAの仕事ばかりに夢中になっていると、開発のプロフェッショナリズムが失われそうな不安を感じる」といって他産業界へ転身する者も現われる。
では、なぜJICAのプロフェッショナリズムが希薄になっていったのだろうか。その原因をちゅうちょなく答える人がいた。それはJICAが7年前に独立行政法人になった時に「ああ勘違い」を起こしてしまったのだという。振り返ると、独立行政法人化の最初の段階において、JICAは「これで中央官庁の干渉から開放される」と小躍りした。ODA、なかでも技術協力は、1960年代のOTCA(海外技術協力事業団)の時代から1970年代以降のJICA(国際協力事業団)を通して、専門家派遣、研修生受入れにしても、関係省庁の専門的指導下に置かれていた。
農林水産、運輸交通、建設の各省には専門研究機関を擁しており、日本の技術に誇りをもつ多くの技官、研究者が存在している。だから、JICAプロジェクトをコンサルタントが受注すると、関係省庁は専門的なお目付け役として作業監理委員を送り込み、JICA事業への注文のみならず、受注したコンサルタントの仕事に注文をつけたり、助言したりした。そこには、常にプロフェッショナルな緊張感が漂い、それが結果的にはJICAマン、コンサルタント双方を刺激して専門意識を少しずつ高め、双方のプロフェッショナリズムを鍛えることにもなった。
他方、“官民連携”が叫ばれるなかで、“オールジャパン体制”をどうしたら形成できるか、その具体化が求められている。その場合、たとえば広域的なアジア・インフラ整備計画づくりでは、JICAと企業との連携だけでなく、産業政策、運輸、建設行政での経験と研究蓄積を有する関係省庁とも合流した形の3者連携というオールジャパンの組み方も必要になってくる。
官民連携では以上のように国家的立場の行政経験者も入ったオールジャパン体制が求められる。しかし、それを実効ならしめるには、JICAの事業立ち上げの時の構想力と実行力、虚業的ではなく実業的感覚、そして広い視野に立ったプロフェッショナルな調整能力が必要であろう。
※国際開発ジャーナル2010年11月号掲載