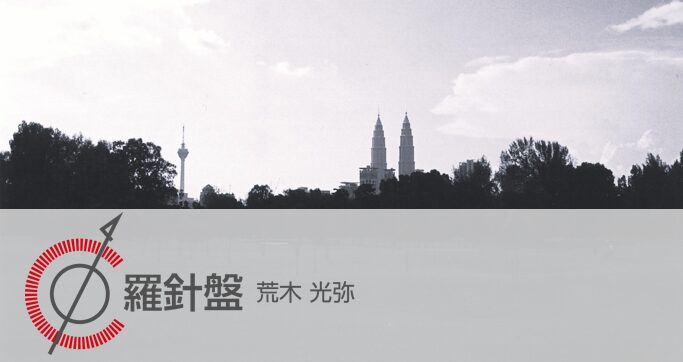対外援助の“原点”
昨年11月から、今年8月で創立50周年を迎えるタイのモンクット王工科大学、30年以上に及ぶマレーシアの工業標準研究所(SIRIM)、シンガポールの生産性向上プロジェクトなど、東南アジアの援助史に残るような技術協力プロジェクトを調べてきた。
その目的は、今日でも当時の「日本の知」、「日本の情(文化)」が、それらのプロジェクトやその周辺社会にどれほど残存しているかを調べるかたわら、現地の人たちを主役にした「援助物語」を書くための素材収集の旅でもあった。
実に面白かった。皆さんご存知の“温故知新”とは、昔の事を訪ねて、新しい見解や知識を得ることを意味しているが、昔の援助プロジェクトを調べているうちに、今はなき日本の対外援助の“原点”を発見することができた。今回はそれを紹介してみたい。
その発見とはこうである。それは、どのプロジェクトにも国家政策、アジア政策がバックボーンとして貫かれていたことである。1960年代は戦後復興から経済成長を目指した池田内閣の「所得倍増政策」を実現すべく、外貨獲得のための輸出振興政策が至上命令になって、経済協力(政府開発援助)もこの政策の中に組み込まれていた。組み込まれるというより、初めから輸出振興になるように計画された対外援助プロジェクトであった。
その市場は賠償から培ってきた東南アジアであったが、すでに1950年代末の岸内閣の時に布石を打っていた積極的なアジア外交が輸出振興政策をバックアップしていた。その先兵となった商社はじめ多くの日系企業の第一線では、東南アジア市場のシェア拡大のために先進的な欧米企業と闘った。援助も円借款を中心に戦略的に使われた。
こうした日本の政策と手段としての援助が一丸となって実施されたこともあって、短期間のうちに東南アジア市場で大宗を占めていた旧宗主国のヨーロッパ勢は敗退した。日本の経済協力に市場的な脅威を感じたヨーロッパ勢は、裏からDAC(OECD援助委員会)に手を回して、「円借款協力は商業的援助だ」とのキャンペーンをはって、遂に輸出振興の戦略的手段となっていたタイド援助(ヒモ付き)をアンタイド(ヒモ付き撤廃)へと追い込んだ。こうした事情からわかるように、円借款協力を中心とする日本の経済協力は、輸出振興という国家政策の手段として有効に働いたのである。
ASEAN政策の不在
このように、対外援助は国家政策、外交政策が背後にあって、国民国家のために働いてきた。それゆえに、援助予算は政策的な意味と意義をもたされ、国家政策がスポンサーになって拡大されてきた。現在の中国は援助のスポンサーになってアフリカで大規模な地下資源開発を行っている。まさに、かつて資源確保で世界中を狂奔した日本を想い出す。もっとも中国のスピード感は一党独裁の強みを生かしたものであり、その規模、そして軍隊まで動員する傍若無人ぶりはかつての日本とは桁違いである。
だからといって、筆者は昔に戻れと言っているのではない。「知新」、新しきを知れと言っているのである。つまり、日本の対外援助は1980年代末から90年代にかけて、日本経済のバブル化と共にバブル化して、トップドナーに踊り出た。間もなく冷戦崩壊が到来する。冷戦時代は西側の一員として、また対米外交の面で対外援助を支える国家政策らしきものは存在していた。しかし、ポスト冷戦では国民国家のためになる国家政策に裏打ちされた対外援助政策は姿を消して、国の発展に基盤を置かない対外援助がまかり通り、JICA等の援助実施機関は極端にいって、援助量の消化作業を行っているように映った。
こうした流れが今も続いている。政府はアジアをどう思い、その中でASEANをどう思っているのか。国家としてのアジア政策をアジアの中で生きていく日本として考えているのか。貿易立国の日本は世界の無差別貿易体制を守ることを国是にするうちに、政策的目線は欧米にはりつき、足元のアジアへの配慮を欠いてきた。今やアジアは「世界の生産工場」となり、中国、インドなどの市場が世界経済を左右するほどに成長した。しかし、日本はその成長のスピードを見誤った観がある。したがって、政策の展開にもスピード感がなく、国内の政権不安定もあって、政治的推進力も落ちた。かつての日本では政権交代があると、新首相は必ずASEAN主要国を歴訪した後に米国を訪ね、アジアの架橋となってアジアの考え方を伝えたものである。
その時、必ず政治的な政策意図を盛り込んだ対外援助政策を発表し、帰国すると霞が関の行政府に対しても政策の行動計画立案を指示したものである。
しかし、今はASEAN中進国に対しても斜陽のDACの言い分に気を遣って、「援助卒業国論」を持ち出して、援助消極論を展開する輩がいる。筆者は、今回の調査で中進国といわれるASEANの国々では、かつてのお師匠(日本)と連携してASEAN後発国はもとより、インド、中東、アフリカに対しても「連携型国際協力」を企画したいという声を多く聞いた。
連携型国際協力
すでに日本が40年以上も支援してきたタイのモンクット王工科大学は、日本と連携して隣国ラオス国立大学工学部で人材育成を始めている。また、同大学は日本が広域的な高等教育の人材育成ネットワーク化を目指した「SEEDNet」(東南アジア工学系大学ネットワーク)の要になっている。SEEDNetのネットワークはASEAN19大学、日本11大学が連携して工学博士、修士の育成を1997年のアジア経済危機以来続けているが、これには2人の日本の首相が貢献している。まさに、日本の政策的意図が働いた「連携型国際協力」である。
シンガポールではすでに日系企業とは日本の技術力とシンガポールのグローバルな資金、経営人材ネットワークを組み合わせて、インド進出を図っている。これは企業連携であるが、かつて日本が伝授した生産性ノウハウを今度は日本と連携してインドから中東、アフリカへ拡大してはどうかという連携型国際協力の提案もあった。
マレーシアでも工業標準を日本と連携してグローバル展開する夢を語っていた。ASEANの経済的アキレス腱であるインドシナ経済・社会開発でも、日本はASEAN先発国と連携して取り組む「連携型国際協力」という新しい道を開拓してほしい。
連携はネットワークにつながり、日本とASEANとの人的絆を強くし、そのポジションはアジアの中で政治的にも重要な意味をもつことになる。
現在は、そうした政策がまったく不透明であり、そうした状況の中で対外援助を続けても対外援助の政策的効用はまったく期待できないし、現場の企業人や専門家たちにも気合いが入らない。中途半端な状態に置かれた対外援助の世界は目的意識を失い、いつしか人も組織も怠惰になり、世間から軽視されるようになる。今はもうそうなっているといっても過言ではない。
こういう状態は、納税者を一番の被害者にしてしまう。納税者のためにも為政者は、日本という国家は何のために援助するのか、その政策的意図を明示し、説明責任を果たしてほしい。
最後に一言。筆者がここで強調した対外援助のスポンサーになる国家政策とは、国際協調のための美辞麗句ではなく、将来の日本を支える“生存”のための政策を指している。それがないと、日本の対外援助に明日はない。
※国際開発ジャーナル2010年3月号掲載