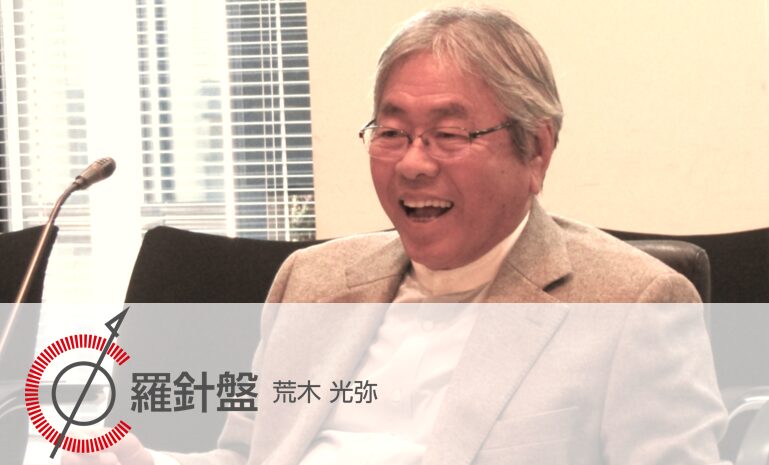各地に解け込む国内研修を
行政刷新会議の“事業仕分け”は国際協力の分野にも大きな波紋を残した。まず、賛成派の意見はこれまで政権政党(自民党)の下で財務省主計局と霞が関他官庁との予算折衝で始まり、国会ではほぼ概算要求通りに国家予算が決められてきた。予算決定のプロセスは国民にはほぼ霧の中であったが、今回の事業仕分けで初めて予算の実態が明らかにされた。その点、納税者にとっては有意義であった。
次いで、クレーム派は事業仕分けの公開の原則には異論はないが、事業仕分けはどうかといえば、天下りに伴う予算のムダ遣いに異常反応を示し、事業の意義を長期的な展望、または国家戦略的な視点でとらえながら是々非々で判断する余裕は見られなかったという。
私は11月24日のJICA事業仕分けを気にしながらバンコク、シンガポールに旅立った。旅先で『週刊文春』のセンセーショナルな記事を読んで、これはいけない、40年にわたってODAをライフワークにしてきた者として自分なりの見解を述べておきたいと思った。
まず、仕分けは間違いなく国際協力の意義、事業の意義を認めている。そのうえで大きくいって、仕事を進めるうえでのムダ、仕事を進める職員のコスト(人件費)を問題視した。仕事を進めるうえでのムダとは、(1)途上国からの国内研修のあり方、(2)聖域に踏み込んだとみられるJOCV(青年海外協力隊)のあり方、(3)調査・研究のあり方、(4)業務を民間に委託する時のあり方などである。仕事を進める職員の人件費とは、ずばり人件費さらに旅費のあり方である。
(1)途上国からの国内研修事業のあり方。
端的にいうと、第1は研修施設「箱物」の整理統合である。国内研修施設は北海道2つ(札幌、帯広)、関東では横浜/東京、名古屋、関西では大阪、神戸、広島、北九州にある。なお、沖縄センターはASEANセンターの一環に位置づけされている。仕分けは、それらを札幌/帯広、横浜/東京、大阪/神戸を整理統合するよう指示した。さらに、これまでJOCVの根拠地でもあった東京・広尾の施設の売却を指示した。この地は東京のなかでも一等地であり、高値売却が見込まれるが、売却代金は言うまでもなく国庫に納入される。
なぜ国内研修施設が必要だったのか。その歴史をたどってみると、戦後、日本は賠償留学生、続いてコロンボプラン(英国主催の東南アジア技術協力機構)加入によって技術研修生などを受け入れたが、当時の社会環境の未整備とあいまって、日本人の閉鎖性からの一種の偏見によって留学生ホームステイのみならずホテル宿泊も不可能に近かった。そこで、集団施設をつくり、そこをベースに研修することになった。これが当初の事情である。
しかし、時代は進み、日本の地方でもアジア人、アフリカ人などへの偏見も消え、今ではむしろ彼らを地方の国際化のためにも歓迎するようになった。ところが、一方では地方自治体が政治家を介して研修施設を誘致するようになり、いわゆるマル政案件として地方施設が次々と誕生した。しかも、各施設の大きさも、たとえば予定の150室に対して財政当局の後押しもあって200~250室というように拡張されるケースもあった。特に、バブル期にはふんだんに建設資金が投入された。言っておきたいが、それはJICAプロパーの意志というより政治的、外部的要因によるところが大きかった。
しかし、歴史の流れからいって、今では研修生は地方のホテル、旅館、あるいはホームステイによる宿泊、地方の施設(民間、自治体あるいは廃校利用)での研修計画を考える時代に入っている。研修生たちは日本の地方に残されている日本本来の伝統にも接触できる一方で、地方の優れた伝統工芸を知ることができる。そのうえで、宿泊費など研修費が地方にも落ちて、税金の循環作用が起きる。国際協力の意義が名実ともに日本各地に広がることになる。その意味で、研修施設の統廃合にはそれなりの意味があると思う。
規律ある人材・組織づくり
(2)JOCVのあり方。
日本のJOCVは米国ピースコー(平和部隊)のコピーでありながら、その内容は日本独自の発想にもとづいていた。最初は農村の三男坊を動員する形で途上国の農業開発に貢献させようとした。しかし、工業化の進展とともに農村から都市へ労働人口の移動が起こり、次は都市型ともいえる自動車修理工などの現場型技術者がJOCVの花形になった。しかし、こうした職種もいつしか消え去り、伝統的な柔道などのスポーツ分野のみならず、音楽、絵画など文化的な分野まで範囲が広がり、農村に入る青年たちはこれといった技能を特に持たない者たちが大宗を占めるようになった。
悪口を言う人たちは「あれは官費による観光旅行だ」と言う。しかし、それは言いすぎである。村のために、またエイズ患者のために村で闘っている青年たちもいる。村長から称号を授与される青年もいる。問題は予算通りに人数合わせをして派遣するのではなく、現場のニーズを調査したうえで、そのニーズに合った青年を派遣するという厳格な仕組みをつくることである。実際には学校の先生を計画的に派遣するといった目的別編成による派遣計画を実施しているが、こうした計画性が求められている。つまり、先に予算ありきでなく、役に立つ人間ありきでJOCVのあり方を抜本的に改革しなければならない。
(3)調査・研究のあり方。
調査・研究費は30%削減が指示されたようだが、事前調査などは50億円程度に縮減されそうだ。50億円が妥当かどうか、これから精査する必要があると思うが、優良事業の準備などで支障をきたさないか心配である。
しかし、その反面で反省すべきところもある。多くの場合、調査とは事業を立ち上げるための準備作業であるはずだが、コンサルタントに調査報告書を提出させ、それをもって事業が完了したと錯覚する人たちがいないとは言えない。資金の有効利用が叫ばれている時に、調査費用は事業を立ち上げるという目的に直結しなければならない。また、数撃てば当たる方式の調査のムダもはぶかなければならない。JICAには意識のうえで、またシステムとしてトップドナー時代のODAバブル的後遺症が残っているケースも見受けられる。もう少し、民間事業のようにコスト意識を高め、節約する所は節約するための点検能力を高めてもらいたい。
(4)民間への業務委託のあり方。今のJICA調達制度を見ていても、形式至上主義に陥って、経費の点検を厳しくする余り、逆に費用対効果を失っているケースもある。形式至上主義で自己責任を完全ならしめるあり方から、組織、職員のディスプリン(規律)を高める教育を強化し、それにもとづく制度設計を行い、税金の費用対効果を高めてもらいたい。
相次ぐ統合の果てに
最後は人件費の問題である。JICAのラスパイレス指数は130とも言われた。つまり国家公務員指数を100とするならば、JICAは30も高いという。しかし、実際は少々オーバーな指数で、それほど高くないという。とにかく人件費は将来に向けてラスパイレス指数を100に近づけるような努力をしなければならなくなった。本来、JICA職員の給与水準はそれほど高くなかった。それが高くなった背景はこうである。
周知のように、JBICの円借款部門との統合で、高い給与水準の円借款部門との調整が行われ、旧来のJICA給与水準も少し引き上げ、円借款部門からの職員給与を少し引き下げて調整した結果、現在の給与水準となったのである。それでも他から見ると高い給与水準に見られている。問題はJBIC円借款部門の給与水準が、民間銀行並みの水準である旧輸銀に準拠して決められたからである。そもそも2000年時のOECF(海外経済協力基金=円借款)と日本輸出入銀行との強行合併(私は白紙撤回を求めた)でJBIC(国際協力銀行)が創設された時から因果関係を引きずっている。当時、OECFの給与もJICAと似たり寄ったりであったが、輸銀レベルが民間銀行レベルであったために、それに右へならえとなり、自動的に旧OECF職員の給与も高めに引き上げられた。そうした状況を引きずったまま、JICAと統合した。
いずれにしろ、統合は時の政権、時の役所の責任であって、働く人たちはその流れに抗しきれずに現状に順応している。そこには働く人、一市民としての生活設計がある。そこに家庭の営みもある。それを一方的に、ある日突然変更せよと言われても、あまりにも無慈悲な話である。私は、給与に関してはもう少し時間をかけて解決すべきだと思う。まさに基本的人権に関わる問題だからだ。
これを契機に、地球環境問題にも対応できるよう機能の点検、制度設計を行うとともに、天下りなき組織として自らの機能を発揮できる組織改革に取り組んで欲しい。そのために外部の知恵を借りることを怠ってはならない。真に「開かれたJICA」を目指してもらいたい。
※国際開発ジャーナル2010年2月号掲載