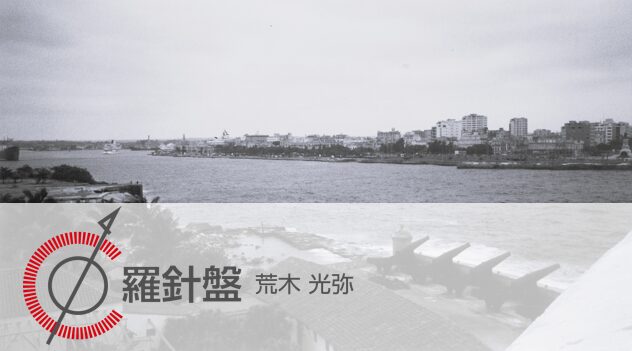タイ政府の行政放棄か
成長戦略に貢献すべき第1号の「パッケージ型インフラ輸出」が挫折を味わうことになった。それは、ソフトとハードを融合させたタイの治水対策事業入札である。
6月25日付けの日本経済新聞は、4段見出しで「タイ9,500億円洪水対策事業、中韓勢が大半を受注、要件厳しく日本は辞退」と大きく報道した。日刊建設工業新聞も「タイ治水対策国際コンペ、日本JV、最終選定を辞退、契約条件に過大リスク」と、日本側は4月17日付けでタイ政府に辞退を通知したと述べている。
日本側の辞退に関する第一の理由は、事業を請け負う業者が土地収用から住民説明、住民移転まで引き受けるだけでなく、環境アセスメントをも実施しなければならないという条件。タイ側はこれも民活の一環だと言っているが、これらは本来、政府の仕事である。その意味で、この治水事業を一手に引き受けることによって副首相に上り詰めたプロートプラソップ前科学技術大臣ら治水事業責任者の行政放棄に等しい。
タイでは、同国建設業界第4位の「ユニーク建設」が地下鉄プロジェクトで住民移転を一括して請け負って成功させたケースがあった。タイ政府はこうした一例をとって「タイでは住民移転も民活でできる」と思っているフシがある。
道路建設では社会主義体制のベトナムでも住民移転交渉にかなりの日数を要している。政府の強権発動も通じないほど住民パワーが強い。これを入札条件に入れたら、正当なビジネスであるならば絶対に受け入れられないだろう。特に、工事と一緒に住民移転交渉を始めた場合、必ずと言ってよいほど工事の延期を余儀なくされる。そうなると工事遅延のペナルティーが課せられかねない。そして工事の予定額も増大して大きな赤字工事になってしまう。
筆者は過去、円借款によるフィリピンのバタンガス港開発に伴う住民移転騒動を見てきた。あの時は、日本のNGOグループも不法な住民移転だと言って住民の条件闘争を支援していた。筆者も取材して、よせばいいのに「もぐりの住民も多い」と、ミンダナオなど他から保証金欲しさに移転してくるニセ住民のことを書き、日本のNGOから大変なお叱りを受けたことがある。
もし、日本企業グループがタイで住民移転にまで関わり、現地住民とのトラブルが大きくなろうものなら、日本のNGO、NPOとタイの住民派のNGOグループに非難攻撃され、企業のコンプライアンス(企業倫理)まで問われかねない。たぶん、日本企業グループはそうした危険性を予知しているにちがいない。
プーミポン国王の勅令予算
第二の辞退の理由は、5年間で最大28のダムを建設するという無謀さを危惧しての判断。専門家筋では、いまだダムの建設地さえ決まっていない場所もあるのに、28のダム建設などもってのほかだと語る。
さらに、もう一つの重大なことを指摘しなければならない。この治水対策事業に要する1兆円近い国家予算は、緊急を要するということで、正式な国会承認を得ずに“プーミポン国王の勅令”で決めてもらったものである。国王の勅令の条件は「予算の枠内で5年で完成すること」ということが付されているとのことである。だから、工期は厳重に守らなければならない。工期延長の場合には、1日当たり契約金額の0.05%、つまり7,700億円の契約金額だとすれば、1日当たり3.8億円を支払わなければならないという規定が盛り込まれている。
日本の関係筋では、5年間での完成は絶対にムリだと言っているのに、タイ、中国、韓国の連携グループはどう対処するのだろうかと詮索する。それによると、タイ側受注グループが政界工作を行って5年という期限の延期を決めるのではないかと推測する。これは不敬な言い方になるが、プーミポン国王の病状がまだ回復せず健康状態が危ぶまれているなかで、「5年」の制約が解かれる可能性を見込む一派もいるかもしれない。
以上、二つの理由で巨大計画の前途が危惧されている。だが、筆者は危険な憶測かもしれないが、日本側は今、日本で厳しく問われている企業のコンプライアンス重視から、この計画にダーティーな悪臭を嗅ぎ取ったのではないかと推測する。
とにかく、日本側はタイ側の顔ぶれと、その背後関係から、以上のキャンセルの二つの理由のほかに、隠された形で計画の裏側にひそむダーティーな危険性を察知しているように感じる。日本チームは、すべてのTOR(業務指示書)メニューに対して異常なほどの高い入札価格を提示したと言われるので、日本側のキャンセルの意志の強さが明確に打ち出されている。
恐らく日本チーム側は「ここまで仕組まれては勝ち目なし」と判断したのであろう。日本人の中には「インラック首相は日本に味方している」と言う人もいるが、治水事業を自分流に押し進めようとするプロートプラソップ現副首相・前科学技術大臣(日本の天敵と見られる)を表向き批判しても失脚させることはできない。最近の内閣改造でも一時は失脚かと見られていたが、インラック首相はなぜか国民に人気のない彼を排除できなかった。
この人事を深読みすると、海外亡命中のインラック首相の兄であるタクシン元首相がその背後でなんらかの指示を与えているのではないかという憶測もあるようだ。もう10年も前のことだが、タイの国際空港スワンナプームに円借款を供与した時、ターミナル建設のPMC(プロジェクト・マネジメント・コンサルタント)選びの入札で、時のタクシン首相が日本を排除したことで、在タイの赤尾信敏大使の激しい抗議を受けるという紛糾があった。もちろん、タクシン側には良くないウワサがつきまとっていた。
甘い護送船団方式
それでは、プロートプラソップが失脚すれば、日本は再びPMCに挑戦するのかと関係者に問うと、そこまでやれる交渉能力はないのではないか、という答えが返ってくる。交渉力とは、一度決まった規定でも工事のプロセスで変えていく根強い駆け引きを指しているようだが、リスクを極端に避けたがる今の日本の会社風土では、決まったことをひっくり返すなどとんでもない、と一蹴される可能性が大いにある。
現地情報によると、タイ建設業界ナンバーワンのイタルタイ社のプレムチャイ社長は「日本のコンソーシアムにはリーダーシップが見られない。それに意思決定が遅い」と不満を述べている。ある人は、「企業のトップにベンチャー精神がない。サラリーマン社長が多すぎる」と嘆く。今回のケースでもチャレンジ精神のなさが目立っていた。「最近の日本企業は、リスクを異常なほど恐れている。だから、カントリーリスクの見方も短期的な判断に偏って、ネガティブな決定へ走ってしまう傾向にある。だから、商いのビッグ・チャンスを見失うケースが多い」という指摘もある。これに対して、「それは株主のシバリが強く、短期決戦を余儀なくされるからだ」と嘆く声も聞ける。
今回は国土交通省が民間を護送する船団(コンソーシアム)の指揮をとったようだが、そのやり方に甘さがあったと指摘されている。カウンターパートになるタイ側ゼネコン会社トップは、「日本側はもっと精鋭化しなければならない」と言う。「皆で渡れば恐くない」という集団によるリスク回避策から、「リスクのあるところにビジネス・チャンスあり」という精鋭集団を政府はバックアップすべきではないか、と言いたい。そうでないと、激化する国際商戦に勝てないのではないだろうか。
一方、政府はODAベース(JICA実施)で洪水被害の直後からきっちりとフォローアップし、治水工事を支援するサポート調査や技術協力も実施してきた。日本は治水対策の能力を世界に誇示できた。開発プログラムは上流(計画づくり)を仕切れば、下流(工事全般)もコントロールできる、という仮説を信じた役人や民間人も多かったのではなかろうか。しかし、結果は肩すかしをくった。担当省である国土交通省と現地事情に詳しいJICAやタイ政府との連携についても、その在り様が問われている。
※国際開発ジャーナル2013年8月号掲載