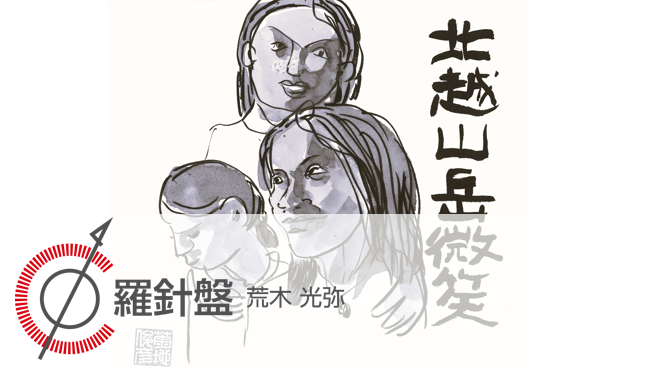世界134カ国からの支援
3月11日金曜日。マグニチュード9.0という巨大地震と共に巨大津波が岩手、宮城、福島、茨城など東北関東沿岸を襲い、3万人に近い尊い人命を奪った。自然は人間を育て、時にしてその命を奪う。実に無慈悲でもある。亡くなられた方々に心から哀悼の意を表したい。合掌
私もそうだったが、私の友人、知人たちも最近、体調不良を訴える人が多い。それは病理学的には説明できない「心の痛み」に属するものである。改めて、私たち日本人が世界に冠たる単一民族であることを、今、立証しているようでもある。それが健全に働いて、日本再建への団結力となることを願ってやまない。
日頃、私たちは途上国の「国造り」を支援することをライフワークにしてきた。一昨年のマグニチュード9.0のスマトラ沖大地震と大津波の時にはその復旧を支援し、被災地域の再建で多くの経験を積んできた。さっそくインドネシアからは救助隊15人、義援金200万ドル(約1億6,200万円)、タイからは日本救援予算2億バーツ(約5億3,400万円)を決定し、その他毛布2万枚、義援金500万バーツ(約1,340万円)を表明している。その他、主だった国では中国、台湾、韓国、ベトナム、シンガポール、ラオス、ミャンマー、インド、パキスタン、ブータン、トルコ、南アフリカ、メキシコ、ブラジル、ペルーなど途上国、新興国など世界134カ国が支援の手を差しのべている。
国際協力をライフワークにしている私たちにとって、自己満足的な感激かもしれないが、途上国の人びとのウォーム・ハート(温かい心)を“恩義”として感じてならない。あの小さな国ブータンがワンチュク国王義援金100万ドル(約8,100万円)を寄附してきたことを知った時、一人の日本人専門家(ダショー西岡)が命を賭してブータン水稲の普及に努めたことを想い出した。また、モンゴルは救助隊12人、義援金100万ドル(約8,100万円)を決めたが、あわせて政府は公務員を対象に給料の1日分の募金を呼びかけ、その輪が一般国民や企業に広がって、すでに1億2,500万円以上が集まっているという。1990年代にモンゴルが社会主義国から市場経済国へ移行する時から、日本は最大の援助国としてモンゴルの国造りに協力してきた。日本が援助を始めた頃の冬、首都ウランバートルの火力発電所が故障して、冬期の都市機能が失われる危機に見舞われた。発電機能が失われると、電力のみならず首都のスチームによる地域暖房機能も落ちて、ウランバートル100万人が過酷な冬を送らざるを得ない、という時に、日本は間髪入れず円借款資金協力で機材の手当て、それに専門家チームを派遣して、火力発電所の復旧を成し遂げた。以来、この話はモンゴルの人たちの伝説になっている。
私はモンゴル国立大学の敷地内に設置している「モンゴル・日本センター」(JICA)の支援委員会委員長として10年ほど助けてきたが、ここの経営講座を卒業したモンゴル青年実業家たちが先頭を切って義援金を申し出ている姿が目に浮かぶ。中央アジアのキルギスから飲料水約2.5トンが贈られてきたが、これも「キルギス・日本センター」で経営講座を卒業した飲料水メーカー経営者が一役買っている。
EPA看護師や介護福祉士たちも
次に紹介したいケースは、EPA(経済連携協定)にもとづいて来日しているインドネシア、フィリピンの看護師・介護福祉士たちの動きである。両国からはこれまでに日本の看護師・介護福祉士の国家試験合格を目指して1,000人ほどが派遣されているが、日本滞在の看護師国家試験合格者の3人を含め約50人が災害ボランティアグループを結成して東北の被災地に向かう準備に入っている。
看護師たちは口々に「お世話になった日本、大好きな日本のために出来ることは何でもしたい」と語っている。たしかに、彼女たちを受け入れた看護施設では、看護、介護される日本の高齢者たちも含めて彼女たちを親切に扱ってきた。彼女たちは一般の日本人たちの機微にふれている。その彼女たちから、こういう時に「大好きな日本!」と言われると、本来の自信を取り戻せるような気分になる。自信は「元気の源泉」である。
しかし、国家は彼女たちに厳しい。彼女たちの日本での看護師国家試験はすでに100回目を迎えているが、その受験者は4,998人に達する。今年は約400人が受験したが合格者は16人で、合格率は4%である。ちなみに日本人の合格率は92%というから、その差に愕然とする。日本政府は3月11日、2008~09年に来日したインドネシア人とフィリピン人の看護師、介護福祉士候補者の滞在期間3年を1年延長する特例措置を決めているが、これが合格率を引き上げる決め手でないことは明らかだ。問題は依然として解決されていない。それは、外国人にとって難解という点では世界一と言ってもよいほどの日本語習得であるが、なかでも看護、介護等の国家試験は一般の日本人にも難解な用語が続々登場する。
たとえば、「振戦、仮面様顔貌」、「僧帽弁狭窄」、「羞明」、「産褥、臍下、血性悪露、冷罨法」等々、かなりの知識人でも読めない難解用語がずらりと並んでいる。日本人の受験者は読解力もあり、また日本語の暗記力もあるから、高い合格率を誇っているが、考えようによっては排他的な国家試験と言われても抗弁できないのではないだろうか。
インドネシアの若い彼女たちの「日本大好き」を超法規的に解釈して国家政策に反映してもらいたい、と願っているのは、彼女たちの看護のサービスを受ける一般日本人の高齢者たちであることを忘れるべきでない。
「日本がお手本だったのに…」
それから、先日、文部科学省系の会議で防災分野の権威ある研究者が狼狽気味というか、困惑気味にこう語った。インドネシアやフィリピンの防災関係の教え子たちから「今回の未曾有の大災害は非常にショックだ。私たちは日本をお手本にしてきたから、どうしたらよいか途方に暮れている。日本は防災のすべてを知り、万全の対策を打ってきたのではないのか」、教え子たちにこう詰め寄られたのである。当の研究者は「いや、日本はすべてを知っているわけではない。だから、お手本でもない。これから一緒に研究していこう」としか言えなかった、と涙ながら残念そうに語っていた。
地震多発の途上国の多くは、このように日本の科学技術力、その応用能力、研究能力を信奉している。それが、日本のソフトパワーとなって日本の信頼度を高めてきた。その信用を失っては世界から期待され続ける日本ではなくなる。なんとしても総力をあげて東北の新しい都市づくりを早期に実現してほしい。とくに私たちがお手本となって新しい国づくりを長年支援してきた多くの途上国の信頼に応えなければならない。
これは私の独白だが、大災害の結果を見ていると、私たちは防災インフラへの過信がなかったのか、それが防災教育という防災ソフト開発・普及に災いしなかったのか、それが街づくりに影響を与えなかったのか、等々を考えながらより根源的な矛盾を感じてしまった。人間の安心、安全を確保しようと思えば、すでに世界で起こっているマグニチュード9.0以上に備えなければならない。すべてがマグニチュード7.8ぐらいを低目に想定して防災プログラムを組んできたのではないか。もし、そうだとしたらそれは科学力というより経済合理至上主義とのぎりぎりのバランスでコスト計算された防災結果ではなかったのか。災害の範囲、深刻さからいって、最も慎重に建造しなければならなかった原子力発電所がマグニチュード9.0を想定していたとは思われないほどのダメージを受けている。ここに、人間の安心、安全を守る防災科学力の落とし穴があったといえないことはない。コスト至上主義からみると、電気料金にもはね返る建設コストを、マグニチュード9.0を想定していては経営的に成り立たない。コストとの折り合いのなかで、残念ながら科学力が敗北した、という結果が福島原発の災害に見ることができる。
国民の安心と安全を民間の経営能力だけにまかすのではなく、国家保障とのバランスのうえで考えざるを得ないことを示唆しているのではなかろうか。こうした観点からも途上国のお手本になることをこれからの日本に求めたい。
※国際開発ジャーナル2011年5月号掲載