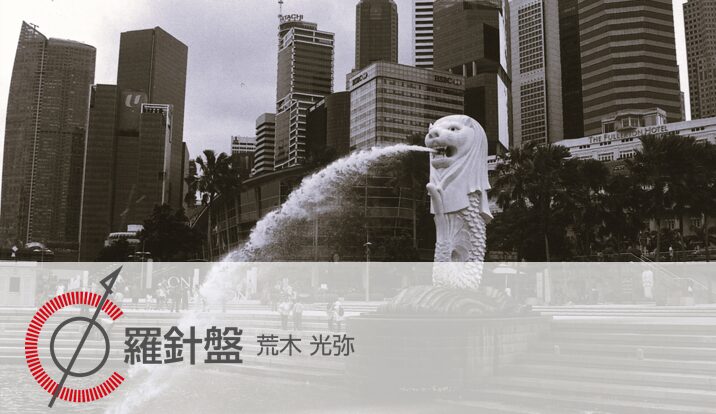ハコモノ援助への誤解
3月1日の夜8時から10時近くまでのBSフジの番組・プライムニュースは、「日本のODAの実態は-大島元国連大使に問う国際貢献の課題と展望」と題して正面からODAの実態に迫ろうとしていた。
ゲストとして大島賢三・JICA副理事長と私が出演したが、いざ本番となると事前に用意した台本構成などはふっ飛んでしまい、司会者の反町さんのふってくる質問に即興で答えなければならなかった。
ここでは、番組の舞台裏でプロデューサーたちがODAに対して何を問題にしようとしていたのかを追跡したいと思う。本来の番組題名は「新時代の国際協力とは」であった。実にタイムリーな考え方である。舞台裏では次のようなシナリオを組み立てていた。
第1ステージは「ODAとは」である。気になる主な設問をあげると、第1は「援助することによって、日本は自らのライバルを作ることになるのでは」である。これは、飛ぶ鳥を落とす勢いの中国を想定している。これにどう答えるべきか考えた結果、次のような答えを用意した。「日本は戦後、東南アジアに対して戦後賠償による国造り、続く経済協力、貿易、投資という三位一体の協力で東南アジアの経済発展に寄与しながら、多くの経済権益を獲得し確保してきた」。しかし、これからは「良きパートナー、信頼されるパートナーとして、ある時は競争し、ある時は協調しながら“共生”、そして“相互補完”の道を選ぶしかない」、「アジアが発展することで、日本の技術力、経営能力もそれ以上に伸びざるを得ない。アジアの発展は日本の発展の更なる促進剤、刺激剤にならなければならない。それが出来ないと日本のサバイバルはない」。
第2の設問は「ハコモノ援助を批判される日本の国際協力だが、どういう点でハコモノ援助が誤解されているのか」。私の回答は次の通り。「基本的には、たとえば発電所だけ、学校だけという単体の援助が多いものだから、モノ的援助のイメージを深め、商業的援助のイメージを強めた。つまり、建設する側のビジネス・チャンスだけが浮き彫りにされた感じだ。発電所建設を援助するならば、合わせてオペレーターや故障修理のできる技術者の養成も行って、初めて援助の形になる。学校を建てるならば教育者の養成、病院ならば医師や看護士の育成という人づくりが伴って、初めて援助といわれるものになる」。
この問題をより専門的に掘り下げると、発電所の場合、有償資金協力(円借款)と技術協力が制度的に連携していないことになる。また、学校の場合、無償資金協力と技術協力との連携がない。これまで無償は外務省が先行してプロジェクトまで決めていたので、JICAの技術協力とスレ違いを生んでいた。実際の姿は技術協力と無関係に、ただご都合主義的にあれこれ利用され、日本の対外援助としての計画性の高い援助にはなっていなかったといっても過言ではない。
時代遅れの「要望調査」
第2ステージは「日本の国際協力の現状と課題」。問いは「予算が逼迫しているなかで、国際協力はどういう工夫が必要だと思うか」、「事業仕分けでもODAに関する予算は縮小しているが、これについてどう思うか」。これらに対し、こういう回答を用意した。
工夫という面では、小さな予算で大きな効果を得るには、途上国からの多くの要請を“選択と集中”で徹底的に整理して、出来れば途上国のためになると同時に、日本のためになるようなWin-Win、互恵的なプロジェクト、プログラムに仕上げる工夫が必要ではないのか。
問題点は、これまで反省材料にもなってきた「要請主義」である。要請ではなく提案型援助だといいながらも、実際は毎年、JICAも大変なエネルギーを使う「要望調査」が途上国の各大使館ベースで行われている。要望を出せといえば際限なく要望が出てくるのが途上国である。それをいちいち聞いていては、援助がコマ切れになって、まとまった効果も出ない。それは日本の援助として光を放つ存在ではなくなり、援助効果のみならず外務効果も失われ、あげくの果ては日本国民の大切な税金が有効に使われないことにもつながる問題だ。
基本的には、相手の要望を聞くならば、相手の大きな国益にもなる長期的展望をもった要望を政策対話で聞き出して、それに日本側の国益を合体させながら援助計画を立案するのが援助の本筋ではないのか。現在の「要望調査」はまさに裏口からの御用聞きのようなものである。
大きなエネルギーをかけた「要望調査」は、援助の本道から見て脇道というか、時代遅れだといえる。したがって、予算の節約という意味でも一刻も早く撤廃すべき制度だと思う。
現地大使館には、すでに官民連携による「ODAタスクフォース」が設けられているので、この機能を生かして、これまでの「要望調査」をもカバーするのも一考である。「要望調査」を一つ撤廃するだけでも、世界的なスケールで考えると、大きな“行政コスト削減”になる。
次いで「事業仕分けによるODA予算縮小」については、まず援助実施する側が自己反省する必要がある。現在の援助体制は、基本的に1980年代末から2000年までトップドナーにのし上がったままの流れに沿っているだけで、ODA縮小に合わせた変革が見られない。小さな予算でも大きな効果を産み出せるような制度変革「システム・リボリューション」が必要だ。それは行政コストの削減につながり、一銭でも多く途上国の貧困削減、生命の危機からの脱出に使われるように工夫してほしいものである。恐らくこの願いは一般国民の望みと同じではないかと思う。
さらに、制度変革にはそれに伴う精神的変革が必要になる。ODA行政も実施するJICA側も、湯水のように使えた余裕のあるODA時代から一刻も早く脱却して、資金を納税者のためにも無駄なく、いかに有効に活用するかに心血を注ぐ姿を見せてほしい。資金が少ないから小さく使うのではなく、小さな予算を集めて大きく使う有効な援助プロジェクトの発掘と準備にエネルギーを集中させてもらいたい。
見えづらい国益
次の問題提起は「日本の国際協力は国益という点が見えづらい」である。この問いが、恐らく現在の日本人の考える最大公約数ではないかと思う。これまでの援助実施者たちは援助する意義、援助される側のメリットを「貧困削減」の旗印の下で叫んできた。そのなかで、「援助する側のメリット」を叫ぶ声は小さく、せいぜい相互依存の世界という範ちゅうで私たちの食べ物など生活物資がいかに海外依存しているかを訴えるなかで、途上国にも助けられていることを示唆する程度であった。
タイの学生たちは、日本の援助について「日本は援助していると強調するが、われわれから見ると“互恵”だ」という。日本は援助といい、日系企業進出による技術移転や雇用拡大といい、タイの経済・社会の発展に大いに寄与した。それは認める。しかし、その反面で日本は貿易や投資で厖大な富をタイでつくり、日本へ持ち帰っている。その点で、互恵関係が成立している。時に、日本の政治家は一部であるが、「援助してやっているから感謝すべきだ」という時がある。これこそ大いに反省すべきだ。
いずれにしても、互恵といえば丸く収まる。BSフジの番組でもウガンダ駐日大使とのインタビューが放映されたが、大使は援助という言葉は使わず、これからはパートナーシップが大切であることを強調していた。つまり、援助の代わりにアフリカは資源を提供するのだから、イコール・パートナーだということを主張したかったのであろう。
したがって、日本のなかでも途上国援助は“互恵”であることをはっきりと主張して、国民の納税は決して無駄にならないことを説明する必要がある。互恵には短期的な互恵も長期的な互恵もある。今日、援助して明日に恩恵が返ってくるものでもないが、広い意味での恩恵を納税者に説明する責任が政府にあるのではなかろうか。
私たちは現実に約973兆円もの国の借金を国民に押し付けている現状にあって、援助を減らすなと自己主張しているだけでは「井の中の蛙」になってしまう。国民と共に歩む援助事業であるならば、人びととの一体感、全体感をもって、時代に合った政策変更、実施体制の変革を成し遂げて、人びとの信頼を得ていくべきであろう。
※国際開発ジャーナル2010年4月号掲載