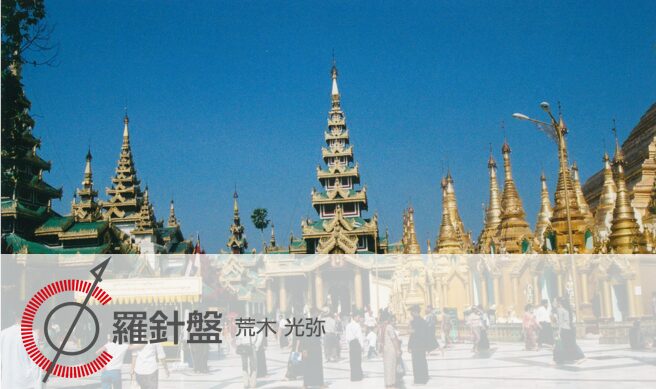失われた既得権益
臥薪嘗胆すること70年あまりと言えば、少々大げさな言い方かもしれないが、去る5月、国際協力機構(JICA)に待望のプロパー(職員)出身の副理事長・山田順一氏が、理事昇格という形で誕生した。
とにかく、今回の人事はJICAという組織にとって歴史的な快挙である。同時に多くの職員にとっても、切磋琢磨すべき将来への目標が目前に現れたことになる。いずれにせよ今回の人事はJICAの健全な発展にとって理想的な第一歩だと言えよう。
JICAナンバー2の副理事長ポストは、2003年の独立行政法人発足以来、基本的には一般公募(今回は8人が立候補した)で決められることになっている。しかし、今までは外交的観点から、またJICA所管官庁という関係から暗黙の了解のように外務省の局長級経験者が副理事長ポストを踏襲し、それなりの役割を果たしてきたと言える。前任者の越川和彦氏は外務省国際協力局長時代から構想していた政府開発援助(ODA)による全国レベルの中小企業海外展開支援に一つの道筋をつくるなど、大きな功績を残した。
しかし、JICAの副理事長というポストは、個人的な志や能力は別にして、外務省にとって2003年のJICAの独立行政法人化以来の、一つの既得権益になっていた。それが今回失われた。これをどう評価すべきかを考えるにあたって、そこに政治的要因といった特殊事情があったとしても、筆者は歴史的な必然性とも言える一つの大きな出来事だと考えている。
3者3様の綱引き
周知のように、日本経済は一時に比べれば衰退に向かっており、ODAも外交の手段としての役割が後退し、どちらかと言うと、極端な形で国益追求型のODAを強く求める時代になりつつあることを感じてならない。中でも、官邸主導による国益追求型の経済協力によるインフラ輸出戦略がJICAの円借款協力に大きなインパクトを与えている。こうした傾向はポスト・コロナ時代の経済再建時代においてもますます強まるものと考えられる。
そうした背景から、今回のJICAプロパー昇格人事には官邸の政治力が働いているという見方が有力である。つまり、プロパー昇格人事は、端的に言って、インフラ輸出戦略において重要な役割を果たす円借款協力に精通した現場型のプロパー人材の登用ではないのか、という見方である。
もしそうだとしたら、今回のJICAプロパー昇格人事はそれなりに的を射ていると言えそうだ。副理事長に理事から昇格した山田順一氏はもともと海外経済協力基金(OECF)に入り、OECFと日本輸出入銀行(当時)との統合という厳しい経験を積み重ねながら、ひたすら円借款協力の現場を歩いてきた。それだけに、円借款協力の実践、論理ともに精通している人物である。これからの日本経済にとって主力となる産業輸出産品が少ない中で、各種の産業技術的なノウハウを売り物にするインフラ輸出は、国策として重視される分野であり、その重要な手段としての円借款協力への期待は高い。
したがって、今回のプロパー副理事長の誕生には、そうした日本のインフラ輸出をリードする官邸側の政策的な意図が投影されているように見られている。他方、副理事長の任命権を有するJICA理事長としては、官邸とある程度の歩調を合わせたとしても、JICA本来の正常な組織のあり方に立って、プロパーの副理事長昇格に踏み切ったという見方もある。いずれにせよ、プロパー副理事長の誕生には官邸、外務省、JICAという三角関係の中で、いろいろな駆け引きがあったのではないかと推察される。
次期理事長への思惑
続いて、次期JICA理事長ポストの問題を考えてみたい。現理事長の残任期間はほぼ1年だと言う。2003年の独立行政法人化以来、初代の緒方貞子理事長に続いて、2代目の田中明彦氏、3代目の現・北岡伸一氏と続いているが、この人事の流れは緒方人事と言われるもので、学者グループで占められている。こうした人事の流れは、人材不足から、おそらく次の4代目に引き継がれる可能性は低いとみられる。
それでは、次はどうなるのか。今から関心の集まる問題である。しかし、まもなく安倍晋三政権の次への移行が現実のものとなることから、今の官邸の神通力がどこまで発揮されるのか、不透明さが漂っている。そもそもJICA理事長の任命権者は外務省である。これは憶測にすぎないが、次の理事長人事の時は、外務省筋による理事長人事が行われる可能性が考えられる。歴史を振り返ってみると、1974年の特殊法人国際協力事業団の発足から2003年の独立行政法人化まで5代にわたって外務省人事であった。初代の法眼晋作氏、有田圭輔氏、柳谷謙介氏まで外務省次官というトップクラスの人事であった。4代目から局長経験者の藤田公郎氏、5代目は川上隆朗氏であった。(もともと5代目は外務次官経験者の斎藤邦彦氏であったが、2000年ごろの外務省スキャンダルに巻き込まれて実現できなかった)
その後、外務省は緒方理事長時代から、副理事長ポストを4代にわたって維持して来た。中には世が世であれば、理事長に匹敵する人物もいた。そこで、次の“ポスト北岡”では外務省筋による理事長人選が行われるのではないかという見方も考えられる。
したがって、今回のJICA副理事長人事の背景には、ひょっとしたら理事長任命権を持つ外務省による次期理事長への布石が含まれているのではないかという憶測も成り立つ、という見方もある。いずれにせよ、先のことはよくわからない。来年になると、政界の力関係も大きく変化しそうな雲行きであるから、上記のような仮説が成り立たないとは言い切れない。
以上、JICA副理事長がらみで独断と偏見を述べてみたが、JICA職員側に立つと、これから“上に開けた時代”になりつつあることを信じて、互いに強い共同体意識を持って、上昇志向を高めてもらいたい。すでに日本輸出入銀行とOECFの合併によって発足した国際協力銀行(JBIC)の前田匡史・代表取締役総裁は、プロパー昇格人事である。これまでは、財務省OB人事の牙城であったので、時代の大きな変化を感じてならない。JICAにも将来、そういう時代が到来するかもしれない。
※国際開発ジャーナル2020年8月号掲載