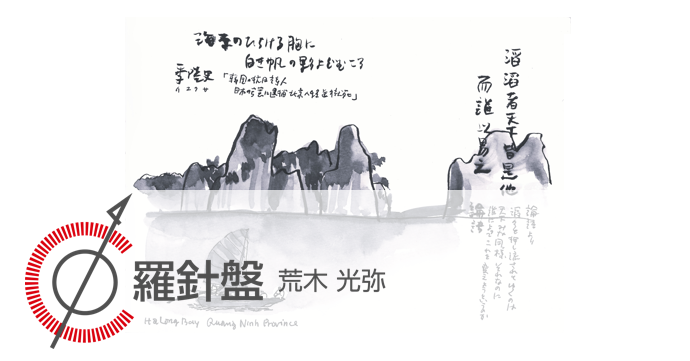ODAは手段、目的でない
参議院ODA特別委員会が2月24日、「ODAに対する国民の理解、参加等」というテーマで開かれた。筆者も、国際的なNPOオックスファム・ジャパンの山田太雲氏と一緒に参考人として出席し、国会議員の質疑を受けた。
質疑の前に、参考人は20分ほどで自己主張することになっている。数年前の出席の時には、「ODAの目的を国会でしっかり討議しないと、霞が関が勝手にODAを配分する」と警鐘を鳴らして物議をかもしたことがあった。今回は3つの論点にしぼって問題提起した。
第1点は、あえて「ODAはわが国の国家政策を遂行する“手段”である」を強調した。日本では、国会でもマスコミでもそうだが、国家政策の手段としてのODAをいかにも目的のように論ずる傾向がある。国連等国際機関への国際協調的な資金拠出は別として、日本の外交を強化する二国間援助は、日本がODAを駆使してどういう国家政策を展開しようとしているのかを常に国民に提示する必要がある。
それが政策の情報開示であろう。政府はODAの具体的な目的を明解にし、その政策目的が日本の健全な発展、生存にいかに必要であるかを説明する責任がある。
率直に言って、最近のODA議論はその使い方だけが厳しく問われるだけで、ODAが日本にとってどういう意味と意義をもっているのかを国家政策の観点から説明しきれていない。一方的に「相手のために」と言われても、生活に追われている庶民には、良いことだと漠然とわかっていても生活実感からは納得できないものがあるに違いない。この傾向は日本経済の低迷とともに日増しに深まっている。
政府は新成長戦略の一環として、大型インフラの輸出振興を強化して、日本経済の活性化を図ろうとする政策を打ち出してはいるものの、これまでのタイド援助(日本の技術、ノウハウを生かした援助)への国際世論を気にしてか、その政策とODAとの積極的なリンケージを強化しようとしない。JICA(国際協力機構)のPPP(官民連携)などの海外投融資事業もまだパイロット(試験的)の段階から踏み出すことを許されていない。ODAで中小企業の新しい活路を海外に切り開こうと言っても、政府が率先してそうした政策を打ち出しているようにも見えない。
第2点は、最初の論点を深掘りするために、「ODAは国家事業であって、チャリティー事業ではない」ということを強調。
主要援助国の本音
主要援助国では、最初から国家政策を遂行すべく、政策立案とそれを実施する実施機関を設けている。
たとえば、米国は国務省と一体となっている米国国際開発庁(USAID)、英国は国際開発省(DFID)、ないし英連邦開発公社、ドイツは経済協力省(BMZ)、その傘下のドイツ国際協力公社(GIZ)、フランスはフランス開発庁(AFD)、そして日本は周知のように外務省国際協力局の所管の下で独立行政法人国際協力機構(JICA)を設けている。
米国は冷戦時代から議会制民主主義の旗を掲げて、戦略的な対外援助を押し進めている。米国の援助思想は「米国への脅威を排除すること」に徹している。冷戦時代は資本主義を脅かす共産主義を世界から排除することに専念し、現在は「核拡散の脅威」に加えて、「テロの脅威」に厳しく立ち向かっている。経済的な意味では、保護貿易も自由貿易の脅威として捉え、モノ、カネ、ヒトのグローバリゼーションが米国の国家政策を支え、一つの思想を形づくる。
英国は旧植民地時代からの英連邦体制を維持するために、英連邦傘下の途上国を中心に援助している。実際は英連邦開発公社が国益的な援助に専念し、国際開発省は開発政策を国際的にリードする国際活動にエネルギーをさいている。つまり、自国の利益を守る戦略的な開発構想を世界的規模で展開しようとするのがアングロサクソン流なのである。
フランスは英国とは対照的で、世界中にちらばっている旧フランス植民地国(途上国)との精神的、文化的「絆」を維持するために、対外援助の大半をこれらに当てている。
ドイツは経済的、技術的な戦略構想の下で、エンジニア(職能技術者)の育成などを通して、途上国にドイツ流の技術的基盤を築こうとしている。最近では、環境に優しいドイツ技術の普及に力を入れ始めている。
主要援助国を見る限り、国民の多くはODAが国家政策の一環として、その役割を果たしていることを当たり前のように認めている。その意味で、ODAは国家維持装置の重要な一部分を担っているとも言える。英国ではアジア、アフリカなど旧植民地国の人びとが市民権を得て、投票権も行使できる。だから政治家は彼らの母国を助ける貧困救済を演説の一節に組み込む必要に迫られている。「なぜ援助するのか」はメディアの議論にもならない。
フランスはもっと徹底している。いつも旅するフランス語圏の途上国に楽しくドライブできるハイウェーを建設する援助になんら抵抗感もない。
ドイツは対外援助に極めて冷静に経済合理主義を貫こうとしている。何がドイツの得意分野か、それがどれほど国際競争力をもっているかを確認しながら機械産業分野、環境技術分野などの得意分野、将来の可能性が残されている分野にシフトしている。まさに、援助の具体的な“選択と集中”である。これも国家ビジョンがなければ、そう簡単にできるものではない。
欧米の日本を見る目
したがって、欧米は「ODAを支持する、支持しない」という世論調査に明け暮れて、一喜一憂している日本に対して驚きの目を向けている。筆者はオーストラリア対外援助関係者のインタビューを受けて、ODA大綱、ODA白書を説明したところ、「日本の本当の政策的狙いを教えてほしい」と迫られた。筆者は、自分流にODAの国益論を述べることができても、それが広く国民とともに共有されてないことを淋しく思った。言うなれば、国家の発展を担うべき政府、あるいはリーダー層の主体性の欠如が問われているのである。
第3点は「新しい援助の潮流」。主要援助国では、国家政策、国家戦略の下で、かつての政府主導の援助体制から民間をバックアップする新しい体制へ移行している。民間企業は効率的な経済開発、市場開発、技術開発などで、NGO、NPOは貧しい国々の市民の自立化を助けることなどで、大学はNPOとして、また民間企業と協力して知的協力することなどで、自治体は民間企業、政府援助と組んで公共的なサービスの提供などで新しい援助領域をつくろうとしている。
まさに、今までのODAを越えての「BeyondODA」である。その典型がPPP(PublicPrivatePartnerships=官民連携)であろう。そうしたなかで、ODAがどういう役割を果たすべきか、今ではその政策をより明確に打ち出す必要に迫られている。
筆者の意見に国会議員が鋭く反応した一つは、タイド、アンタイド問題とDAC存在の必要論議、不要論議であった。ここで、その回答を長々と述べる紙数がないので、端的に言うと、今では中国など新興国が台頭している。しかし、彼らはDACに加盟しようともしない。新興国を納得させることのできないDACは、今や新しい時代を担う国際機関とは言えない。
日本もいつまでもその傘下でアンタイドのしめつけに苦しむ必要はない。そもそもアンタイド化は、日本の国力を削ぎ落とすための策略であったとも言われている。
もう一つの忘れられない質問は、「民間企業との連携で民間の利益を優先するのか」であった。これに対して、「ODAはまさに公的資金である。民間企業の開発能力が優れているからといって、自分だけの利益追求のために公的資金を投入することはできない。その企業の事業目的が公益性、あるいは国益(国の利益)を充足することができるものに限って、ODAという公的資金を投入すべきだと考えている」と答えた。
とにかく、今回はかなり本音で語ったつもりである。美辞麗句の説明では、今や国民の理解を得ることができないところまで、市民感覚は窮乏化しているからだ。
※国際開発ジャーナル2012年4月号掲載