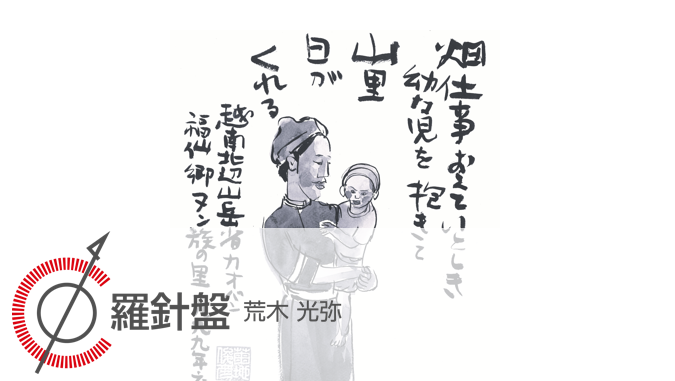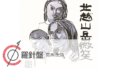拡散効果
中東・北アフリカのイスラム諸国に地殻変動が起こっている。
事の発端はチュニジアからである。長い専制・独裁・強権政治に怒りを爆発させた民衆はベンアリ大統領を国外逃亡させた。欧米筋ではチュニジアは、カントリー・リスクの少ない国だという評価だったので意表を突かれた感じだった。次の火の手は30年間も君臨してきたエジプトのムバラク大統領に飛び火して、一族ともども首都カイロから追放された。
貧困、不自由、不正義を強いられてきた民衆の不満は、燎原の火のごとく北アフリカから中東一帯へと拡散した。なかでも深刻な事態に陥っているのはリビアで、武力による民衆弾圧に対して国連安保理は2月末、リビア制裁を決議した。人びとの怒りは中東のバーレーンのハマド国王、オマーンのカブス国王などイスラム王制国家を直撃し始めている。専制という意味ではサウジアラビア、ヨルダン、アラブ首長国連邦などへの波及も懸念されている。
今回の民衆革命の決め手は、なんといってもインターネットである。同じ情報が瞬時にしてネズミ算式に広がる拡散効果は大きい。ところが、その脅威にさらされているのが中国で、あらゆる手段を駆使してネット情報の消去に懸命だ。生のネット情報は加工されていない情報だけに人びとの感性を強力に刺激する。そこでは理性が遠のく。ある意味において恐ろしい存在だ。かつてホメイニ師によるイラン革命は「ビデオ革命」ともいわれた。ホメイニ師による革命説法がビデオに吹き込まれて、密かに支持者に配布された。街頭演説はただちに弾圧されたので、ビデオ演説は地下に潜って効果を発揮した。
中国政府はおそらく将来にわたってインターネットによる民主化運動に悩まされることになるであろう。その動きが沿海部から辺境部へ移ることにでもなれば、事態はもっと深刻になるものとみられている。中国は歴史的にエジプト、ギリシャ、ローマ文明などの良き影響を受けてきたが、今度は中国にとって残念ながら西からインターネット革命という悪しき影響を受けることになった。
ネポチズム
さて、問題は民衆蜂起の原因だが、専門家は次のような要因を挙げている。(1)独裁政権による長期にわたる弾圧的政治―自由の抑圧、(2)権力者一族郎党による汚職の蔓延、(3)若年層失業の増大、(4)食糧価格の高騰への不満などで、共通して言えることは一定の経済成長を遂げている中所得国や中進国での民衆の不満が爆発していることである。
独裁政治が長期化すると、間違いなく政権一族による国家財産の不正貯蓄(汚職)が始まる。それは中東の部族主義が原因ではなく、人類共通ともいうべき人間の性が災いしているといえる。東南アジアではイスラム国家インドネシアで痛いほど経験している。それは30年以上も大統領に君臨してきたスハルトのケースである。スハルト政権は1965年、共産党勢力を壊滅させてから30年以上にわたって独裁を続けたが、教育の普及とともに台頭してきた学生たちの改革闘争で退陣を余儀なくされた。退陣の引き金になった1998年初めからの全国学生による改革闘争運動は、今回のチュニジアやエジプトの学生たち(卒業生を含む)の反政府運動と同じく、非常に単純なスローガン「物価を下げよ」から始まった。エジプトのスローガンは「食糧価格を下げよ」だった。事の始まりは生活苦からの民衆の叫びからで、それが次第に体制改革へ発展していく。体制を変革しなければ貧困から脱出できない、といって政権打倒へ走り出す。
インドネシアの学生たちはシンボリックな形で「KKN」排除を叫んだ。KとはKorupsi(汚職、国費の着服)、もう一つのKはKolusi(癒着、特に企業癒着)、NはNepotisme(ネポチズム=縁故主義)である。今回のエジプトのムバラク一族にせよリビアのカダフィ一族にせよ、長年の汚職、癒着による蓄財は日本円にして兆を超えるスケールである。スイスはじめ欧米諸国は資産凍結を決めているが、もし、これらの資金が国の発展のために有効に活用されているならばと思うと、チュニジア、エジプトなどの貧しさに耐えた人びとの無念さが伝わってくる。
ところで、インドネシアでのKKNは、東南アジアではミャンマーの軍事政権一族、ある意味でカンボジアのフンセン長期政権も疑惑の対象となりつつある。北朝鮮の金一族はKKNを世襲化しているのでKKNの塊のようなものだ。隣の中国も一党独裁を支える中国共産党幹部たちも部分的かもしれないが、集団的なKKNを享受しているようにも見える。中央政府が常時、「汚職摘発」を叫んでいることがその証左といえる。さらに、中央アジアに目を転じると、去る2月に来日したウズベキスタンのカリモフ大統領の強権政治、カザフスタンの「家産制」(支配者が国家を私物化する)を強化するナザルバエフ大統領などは典型的なKKNグループであろう。
エピソードを一つ紹介すると、ウズベキはドライフルーツなどで知られるように農業国家でもある。この国の企業規模をみると、99%が中小企業で、大半は家族経営に属する。政府は経営近代化を掲げて、経営者育成に協力する「日本センター」に大きな期待を寄せる。しかし、よくよく実態を調べてみると、多くの経営者たちは企業を大きく育てることに躊躇がちだ。その理由をたずねると、一流企業に育てると大統領ファミリーが強引に株式取得する形で関与してきて、あげくの果てには企業自身が乗っ取られる恐れがあるという。要するに、カネの臭いをかぎつけて、分け前にあずかる方式が常套手段のようである。
一抹の不安
最後に、汚職問題とは異なる論点から中東の民衆革命を分析してみたい。それは教育と雇用の関係という論点である。ここにJICA中東・欧州部が作成した一枚の表がある。これを参考にすると、最初に民衆革命を始めたチュニジア、次のエジプト、そしてアルジェリアの高等教育人口比率(%)と若年層失業率(%)を比べてみると、興味深い事実が浮き彫りになってくる。たとえば、チュニジアでは高等教育人口比率が34%に対し、若年層失業率は30.7%、エジプトは28%に対し23.3%、アルジェリアは24%に対し24.3%というように、端的に言って、いくら高等教育を受けても、同じぐらいの比率で卒業生への就職の機会が用意されていないことを物語っている。10万人ともいわれるカイロ大学の学生たちは高等教育の資格をとっても職にありつけない。それが物価高騰に伴う生活苦とあいまって、絶望的な気分で反政府への気運を高めていったと見られないことはない。
それにしても、今回の民衆革命でチュニジア、エジプト、リビアなどの民主化が一応進展するものと考えたいが、たとえばイスラム国で例をあげると、トルコのような議会制民主主義になるにはまだまだかなりの試行錯誤を繰り返すことが考えられる。次の政権担当者の選択を誤れば、場合によっては振り子が元に戻る恐れもあるが、なにしろ何十年間も独裁を続けると対抗馬を育てないので、多くの場合人材不足に陥る。そうすると政治が混乱し、それが経済を悪化させ、人びとの革命の夢を砕くことになる。場合によっては秩序が乱れ、革命前よりも事態が悪くなることも考えられる。
インドネシアではスハルト失脚後、一時政治は混乱したものの、少しずつ議会制民主主義が定着し、現在のユドヨノ大統領という優れた指導者の出現で中進国への道を着々と歩んでいる。国の栄枯盛衰は指導者の資質にかかっているといっても過言でない。民主主義は忍耐が必要だといっても国の安定は時間とのシーソーゲームでもある。忍耐している間に、民主主義の芽を摘み取る恐れもある。その意味で、中東の次の新しい秩序づくりには一抹の不安を感じてならない。
※国際開発ジャーナル2011年4月号掲載