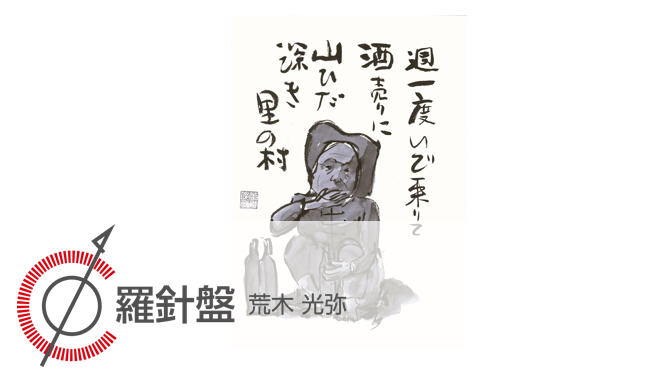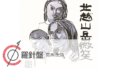国際公約を守った日本
久しぶりにわが国政府開発援助(ODA)の外交を見た。
去る5月1日にアフリカのダカール(セネガル首都)で開催されたTICAD(第4回東京アフリカ開発会議)の合意達成状況を確認する閣僚級フォローアップ会合で松本外相は、「日本は大震災を乗り越え、これまで同様に国際社会の平和と安定のために積極的に役割を果たす」と述べ、「日本は国際公約したアフリカ支援倍増を実行する」と明言し、アフリカ各国代表の信頼感を高めた。
アフリカへのODA倍増とは、TICADまでの5年間(2003~07年)の実績平均値約9億ドルを基準にして、徐々に増加させて2012年の供与額を約18億ドルに倍増することを指している。なお、5年間の実績平均値の9億ドルのうち無償資金協力、技術協力、国際機関を通じた贈与額は7億ドル。さらに18億ドルのうちの無償資金協力、技術協力、国際機関を通じた贈与は14億ドルである。
とにかく2012年はアフリカ支援倍増の最終年度に当たる年で、最後の成果が問われる年でもある。外務省は日本への信頼を高めるためにも倍増の国際公約を守らなければならない。実際はJICA交付金の削減に伴って、残念ながら一部の新規の技術協力事業は削ったものの、アフリカ向け無償資金協力は減らしていない。
さて、日本が最悪の国難に直面していることは、世界中が知っている。また、最悪の財政難に陥っていることも知っている。世界は大震災に際しての規律正しい日本人を賞讃したが、今度はアフリカ支援倍増という国際約束を守る日本人魂を高く評価している。
実は、ここに至るまでには自民党を巻き込んでの政権内大バトルが繰り広げられた。初めは第一次補正予算(4兆円)の財源の一部として、ODA予算(2011年度5,727億円)の20%(約1,000億円)を差し出せという案が民主党幹事長筋から出されたという。一般会計予算5,727億円は前年度比7.4%減(460億円に当たる)である。こうした削減は2000年以降12年間も続き、1997年度のピーク時の1兆1,687億円の半分以下になっている。
民主党政権も財政当局も「ODAは評判が悪く、国民の支持率も低い」と踏んでいたので、20%カットでも反発されることはないだろうと高を括っていた。だが大震災の翌日から様子が変わった。世界135カ国から激励のメッセージや貴重な義援金が続々と届けられた。
被援助国からの恩返し義援金
前号でも紹介したように、最貧国に入るブータンもワンチュク国王義援金100万ドル(8,100万円)、モンゴルも100万ドルというように、まさに貧者の一灯が届けられた。なかでも驚かされたのは、東チモールの義援金である。それは日本の東チモールへのODAを超える金額となったようだ。紛争渦中のアフガン人もカブールを中心に多額の募金を集めた。多くの途上国は口を揃えて「お世話になったから」、「再び元気になって欲しい」というメッセージを送っている。インドネシアのユドヨノ大統領は、「国造りで助けられた。国造りはインフラ整備からという日本の援助哲学は間違っていなかった」と、これまでのわが国政府開発援助を支持した。
これには、日本の政治家が覚醒した。
政治家たちはこれまでマスコミの影響もあって「ODAは役に立っていないのではないか」という疑念に取り付かれていた。ところが、多くの途上国が“恩返し”を口にして多額の義援金を届けてくれた。今や日本は援助受取国としてはアフガンを抜いて世界一になった。
ODAの専門分野では、DAC(OECD開発援助委員会)の5段階評価手法を使って、長年ODA政策評価、国別評価、プログラム・プロジェクト評価などを計量的に行ってきた。だが、人びとはそれを自己満足の評価ではないのかと疑いの目を向けてきた。筆者も評価報告書だけでは、どのくらい役立っているのか確信を持てないでいた。
しかし、今回は不幸中の幸いと言えばひんしゅくをかうかもしれないが、135カ国の多額の義援金に裏打ちされた“日本への思い”、“恩返し”などを含む激励のメッセージを受け取って、改めて「本当に役立っていたのだ!」と叫びたい気持ちになった。
恐らく政治家もマスコミも半信半疑でODAの役割を観察していたに違いない。だから、多くの政治家は135カ国のメッセージと義援金に開眼し、「本当に役立っていたのだ」という見方に変わろうとしている。
ODAを包んでいた霧は少し晴れてきた。見識高い国会議員は与野党協力してODA20%カットに反対し、ODA20%カットを10%カットへと後退させた。今では「もう少し正当にODAを評価してみよう」という“追い風”が吹き始めている。また、今回のODA削減にはNGOグループも岡田幹事長に抗議するなど、反対運動を展開した。NGOグループは国際約束通りにMDGs(ミレニアム開発目標)実現への協力を実行するよう訴えていた。彼らは困窮という点では今回の東日本大震災の被害者も途上国の困窮者も同じ環境に翻弄されている、という視点に立っている。
これからの焦点は実施管理部門
結論から言って、10%削減(約500億円)はODA以外の、たとえば感染症対策などの世界基金、国連分担金、国際交流基金などの拠出をうまく調整して、従来のODA事業費を大きく削減せずに終わらせている。たとえば、世界基金については、昨年10月の世界基金第3次増資会合で日本は当面最大8億ドルをプレッジした。そこで、平成22年度補正予算では約107億円を計上した。ところが、その後、アフリカの一部の国がその支援資金の一部を不正使用したことが判明し、一部の援助国は資金拠出を中止している。こうしたことから日本も新たな拠出を見送ることになった。
また、一部の国際機関への分担金・義務的拠出金については、日本の分担率が予算編成時の見込みより少なくなったために、予算額が支払わなければならない金額を上回っており、その差額分が削減対象になっている。削減した分担金・義務的拠出金75億円の主なものは国連分担金37億円(23年度額272億円)、化学兵器禁止機関分担金8億円(23年度予算11億円)、ユネスコ分担金7億円(23年度予算16億円)。
JICA予算に限ってみると、運営交付金を24億円、出資金を275億円削減するだけで、一次補正予算財源の穴埋めにされずに済んだ。もっとも、ODAの財源といっても、その規模は大河の一滴のようなものであって、大局に影響を与えるものではない。それよりも、日本の次の飛躍へ向けて、小規模でも世界貢献への足場となるODAを続行すべきだという声が与野党の政治家から聞こえるようになった。
たしかにODAには“追い風”が吹いている。だからといって、政治家はODAの実施にマル優を付けているわけではない。事業仕分けでもわかるように、民主党政権は事業費削減の前に外務省やJICAの管理部門などのムダをなくすよう求めた。だから、運営交付金の削減に手をつけた。
しかし、管理部門の効率化が硬直した形で進展すると、逆に事業の効率的、効果的な運用に支障を来たす恐れも出てくる。最近、効率が優先して、効果のための効率化を見失うケースが多発している。援助機関が絶対に見失ってはならないことは、“援助効果”である。効率化を公正に行うことだけにこだわると、たとえば、入札に見るように、細分化された入札になればなるほど再入札も含めて行政コストがハネ上がり、管理部門の効率化が逆に高コストになる可能性がある。
したがって、ODA予算削減の大きなバロメーターは、ODA実施管理部門の理にかなったスマート化があげられる。これからODAの“追い風”に乗って、一つの流れが出来そうだが、それに乗れるには援助の総合機関JICAの命令系統を整えた組織改革や制度改革、それから民間との連携を意識した思考の改革という3大改革を断行しなければならない。実施機関の責任は大きい。
※国際開発ジャーナル2011年6月号掲載