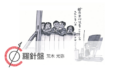注目される中国の輸入力
南沙諸島、西沙諸島をめぐる中国とベトナム、フィリピンとの争いも、ASEANを介在させながら一時的かもしれないが、小康状態に入った。その決め手は、貿易をはじめとする経済協力のようである。なにしろ中国の2010年の輸入総額は前年比38.7%増の1兆3,948億ドルという巨額に達している。たぶんフィリピンは領海紛争を一時棚上げにしても、経済利益を優先させたかったのであろう。
巨大な輸入マーケットは強力な外交手段になる。米国がソ連崩壊後、世界のリーダー国家としてパックス・アメリカーナ時代を築けたのも、軍事力だけでなく自由貿易を掲げ、懐の広い輸入マーケットを世界に提供してきたからである。中国も米国と同じ道を歩いているといっても言い過ぎではないだろう。
また対外投資も中国の対外援助外交の重要な手段である。2010年の中国の対外直接投資は金融業を除いて前年比36.3%増の590億ドル(約4兆9,000億円)に達し、過去最高を記録している。その主力は資源分野で、海外企業買収などによる資源権益の拡大を目指す。その戦略は、欧米が敵視しているような資源国をターゲットにしている。
たとえば、核問題で制裁を受けているイランでは、日本はアザデガン油田権益を75%から10%に自主規制して縮小したが、中国はそのスキを突いてアザデガン油田の70%の権益を獲得した。ただ、カダフィのリビアも狙い目の一つで、油田開発とその他の経済開発で厖大な投資を行ったものの、今回の反カダフィの市民革命で一つの挫折を味わってしまった。
しかし、そのくらいのことで退却する中国ではないだろう。
前座が長くなったが、初めに中国流の対外援助を取り上げようと思う。まず、中国の対外援助の2つのキーワードをあげてみたい。1つは輸入マーケット、2つは海外投資である。たとえば、アフリカに対しては巨額の開発資金を投入して資源開発を行い、その全量を中国に輸入する。アフリカ諸国にしてみれば、一銭も金を遣わずに眠っていた地下資源なり農業資源が換金されて国庫に入るから、笑いが止まらない。しかも、開発地周辺の町づくり、道路、水などのインフラも整備してくれる。こうしたことがパッケージ化されて中国の対外援助政策に組み込まれている。
「開発輸入」の元祖は日本
ところで、こうした開発援助方式は日本が元祖で、「開発輸入」と呼んでいた。1950~70年代の日本の海外資源開発のモデルが「開発輸入」方式だったのである。日本は道路のみならず、港湾などの整備もタイド(ヒモ付き)の円借款協力で行っていた。
1950~70年代にわたって、ナショナル・プロジェクトと称してブラジルのウジミナス鉄鉱開発、アラビア石油、北スマトラ石油、アサハンアルミ、アマゾンアルミ、日伯パルプ、シンガポール石化などが国家のギャランティーの下で展開された。
最近、温故知新という意味で、JICAに「コンゴ・マタディ橋研究会」が設けられているが、これも1960年代のコンゴ銅鉱山開発輸入の一環として実施された鉄道併用の吊橋(全長722m)建設事業であった。約343億円の円借款(タイド)が供与された。
銅鉱石を開発輸入するために鉄道、橋梁建設、港湾整備までを包括した開発輸入計画だった。しかし、コンゴ側の財政悪化や一次産品価格の低落で開発輸入の目的は挫折した。
ところが、最近では中国のアフリカ資源確保戦略の攻勢を受けて、鉱山開発、鉄道建設までをパッケージで援助してもよいというアプローチを行っているという。
こうした開発輸入方式の経済協力は日本のお家芸で、貿易拡大、海外投資(企業進出)と三位一体で実施されて、今日の東南アジア経済発展のベースづくりに貢献した。ところがその後、OECD(経済協力開発機構)の援助国クラブとも言えるDAC(開発援助委員会)は、日本のタイド援助の円借款に「日本の援助は商業的援助だ」とクレームをつけた。日本は抵抗してLDCアンタイド(先進国抜きの途上国と日本の競争)やE/S(エンジニアリング・サービス)を残して、日本の技術のスペックインを可能にする方法などを試みたが、外貨準備高が増大するにつれてガードできなくなり、最後には完全アンタイドにされてしまった。日本側もDACのアンタイド化を受け入れないと、ODAとしてDACに公式計上できないという圧力には抗することも出来ずに、DAC(欧米)の軍門に下った。
中国は、そうした日本の苦い経験を意に介せず、“開発輸入”こそ援助の本流のように突き進んでいる。他の新興国も過去の経験から援助の第一義が「経済成長」、「経済発展」にあると確信しているので、中国流の「開発輸入」方式の対外援助に同調する。
これでは、DACの主張するミレニアム開発目標の教育、健康などに力点を置く援助方針と衝突することになる。しかし、国造りに成功した中国など新興国は「経済発展」を援助の第一義にしているので、経済活動を開発の重点に置いている。経済活動が活発になり、所得の向上が図られれば、自らの力で教育や健康にも力を入れるようになる、と主張する。だから、経済を活性化させるのが最大の援助の目的であるとしている。
かつて、日本の援助(円借款)を商業的援助だと批判したDACに対し、半世紀たった今日、中国が反旗をひるがえしているのである。歴史は実に面白い。援助された経験を持つ国が、DACによる援助理論は順序が違うと言っているから、反論の余地もない。そこで、筆者は何を言いたいかというと、日本もDACの下僕にならずに、日本の得意とする経済開発とインフラ整備をドッキングさせた経済開発援助を主張し、得意とする技術分野ではタイド方式を採用してDACに挑戦して欲しいと言いたいのである。そうした流れの中で、わが国の立国の条件である科学技術に光を当てるべきだろう。
人材は一日にして成らず
しかし、現実にはそこに大きな壁もある。仮に援助をタイド化しても、プロジェクトを発掘し、それを実施に移せるように仕立てる専門家がビジネス界に存在しないのではないかという不安がつきまとうからだ。かつて、タイドの円借款が許されていた時代は、総合商社を中心にプロジェクト仕立人が多くいた。彼らが発掘してくるプロジェクトは実業が伴うだけあって、相手のニーズを十分満たしていた。商社の途上国での力量は大きく、政権トップグループは言うまでもなく、政府官僚のトップクラスと対話ができた。次々と発掘するプロジェクトで当時のOECF(海外経済協力基金)のプロジェクト・パイプライン(有望援助案件がつまったパイプという意味)がいつも満杯だった。OECFは嬉しい悲鳴を上げたものだ。
ところが、1980年代からアンタイド化が強化されると、商社の援助プロジェクト仕立人たちも出番がなくなり、次々と定年を迎えながら消失していった。途上国の商社人脈も彼らの引退と共に引き継がれることなく消えたり、細くなっていった。
今、政府は成長戦略としてパッケージ型大型インフラ輸出を唱えているが、実際には、それを推進する仕事人がどれほど存在しているのか定かではない。要するに、海外プロジェクトの仕掛人と仕立人など推進者が企業に存在しないと、パッケージ型のインフラ輸出案件をコーディネートすることもできない。だから、それを補うべく内外にわたって企業連合を組んでいる。つまり、そういう意味でのグローバル人材が不足しているので、外国企業と組まざるを得なくなっているとも言える。
筆者が一人、円借款のタイド化を叫んでも、1980年代から30年以上続いているアンタイド(ヒモ付きなし)の時代を通じて、国際的大型プロジェクトを組成できる人材も死滅したのではなかろうか、という不安に陥る。まさに「河清くして魚住まず」の観はまぬがれない。
一口に、大型インフラ輸出と言っても前途多難といわざるを得ない。「人材は一日にして成らず」という言葉をしみじみと噛み締める今日この頃である。
※国際開発ジャーナル2011年10月号掲載