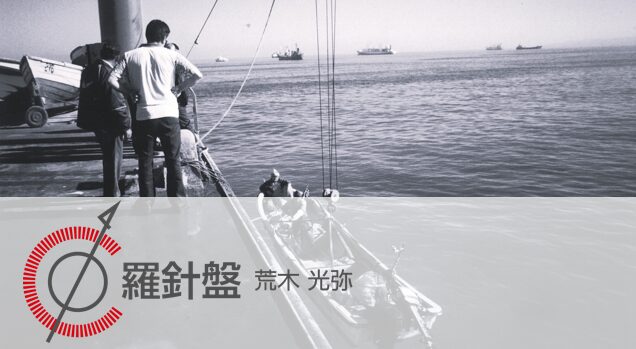市民感覚的連携か
民主党政権の誕生で政府の開発協力政策でもNGOの現場経験に基づく意見が尊重されるようになった。それは、6月末に公表されたODA改革300日プランにも反映されている。こうした傾向は自民党政権下では見られなかった。岡田外相はODA政策に市民感覚を取り入れて、ODAに対する国民の理解度を深めたい、という考え方が強く、NGOグループとの直接的な懇談会にも力を入れている。そこには市民派政権というイメージを鮮明にしたいという意向も働いている。
改革プランのタイトルは「開かれた国益の増進」。その中の「多様な関係者との連携」という課題ではNGOとの連携がかなり重視されている。重要なポイントをあげると、第1が外務省・JICAとNGOとの人的往来の促進。NGOで経験を積んだ人材を外務省・JICAにおいて採用し、その知見をODA政策の企画立案や実施に活かすよう努力するとしている。この方針は画期的なものといえる。
米国では私の知っているハーバードを18歳で卒業した才女が、NPOのネイチャー・コンサバンシーから米国国際開発庁(USAID)の南西アジア担当局長に採用された後に、今度はアジア開銀の理事となり、次には米国を代表する財団のシンガポール代表を務めるなど、実に多彩な転身を遂げている。労働人口の移動が自由な米国ならではの話かもしれないが、それに近いことをNGOとの連携で行おうというのであるから、日本のお堅い公務員制度をよくぞ乗り越えたものである。
ただ、私は途上国の現場での経験という点では開発コンサルタントグループとの連携も採用すべきだと言いたい。開発コンサルタントは開発のプロとしての現場体験を積んでいる。政府の開発協力政策の企画立案にその能力は十分役立つと思う。見方によっては、NGOが社会的勢力として市民権を得ているのに対し、開発コンサルタントは未だ市民権を得ていないからだと言えないこともない。しかし、なんとなくNGOを特別扱いしているようにも見える。
もう一つの重要なポイントは、NGOの独自財政基盤強化への支援。第1点は、寄附文化の定着を図るためのNPO税制改正案の実現に向けて、国際NGOの意見が適切に反映されるよう関係省庁と連携するとしている。第2点は、NGO提案による官民合同資金をベースにした途上国市民社会支援基金の創設の検討。第3点は、NGO財政基盤の強化にもつながるNGO連携無償資金協力予算の拡大(29億円を50億円へ)、しかもNGOの自己負担要件の撤廃、一般管理費の導入などを提示している。さらに、JICA草の根技術協力の支援期間、上限額を見直すこと(3年間・5,000万円を5年間・1億円へ)。NGOによるアフガニスタン支援と連携強化のためにジャパン・プラットフォーム加盟NGO支援に向けて初年度15億円規模の資金協力を行うとしている。
政府依存のヨーロッパ
日本のNGO、とくに国際NGOの脆弱な財政基盤は、日本の寄附文化の低迷にも起因するもので、結果として国際的に活躍するNGO人材の育成を難しくしている。ワールド・ビジョンにいわせると、個人ベースの寄附を日米比較すると、日本は米国の10分の1だという。しかも、同NPOのアジアでの寄附金額を各国比較すると、日本は香港、シンガポールよりも少ないと指摘する。
ただ、日本では国連機関のユニセフはじめ欧米発の国際NPOへの寄附は、なぜか日本発の国際NGOよりも多いというから不思議だ。日本人は未だ舶来主義なのか、それとも日本の国際NGOはその名も知られず、市民権を得ていないのか。不可解な現象がそこにある。日本の国際NGOの弱さの一つが“宣伝べた”なことであるが、根本的なところでは経営べたというか、経営合理性を追求することを不得意とするところが目立っている。日本に比べ欧米のNPOは主義主張もさることながら、経営合理性を厳しく追求している。巧みに宣伝して広く市民のお金を集めている。企業が商品の優位性を宣伝するように、自分たちの信条の優位性を宣伝して市民社会を呼び込んでいる。日本のNGOは信条に固執しすぎて、資金集めの障害になっているケースが目立つ。たとえば、非政府組織というコンセプトにこだわって自ら財政の政府依存度を制限しようとする。
古いデータだが、ジョンズ・ホプキンス大学教授、レスター・M・サラモン氏の1995年、NPOの収支構造の国際比較調査によると、22カ国のNPOセクターの収入の平均42%が政府からの公的補助で、平均47%が会費や料金収入で占められ、意外なことにフィランソロピーは11%にすぎない。
さらに、全体の収支構造を「会費中心型」と「公的補助中心型」に分類している。
「会費中心型」のベスト5をあげると、(1)メキシコ(会費85%、公的補助9%)、(2)ペルー(68%、19%)、(3)オーストラリア(62%、31%)、(4)日本(62%、34%)、(5)フィンランド(58%、36%)。米国は6位で会費57%に対し公的補助30%で、他の国に比べてみると、財政的にバランスがとれている。
次に、「公的補助中心型」のベスト5をあげてみると、(1)アイルランド(公的補助78%、会費15%)、(2)ベルギー(77%、18%)、(3)ドイツ(64%、32%)、(4)イスラエル(64%、26%)、(5)オランダ(60%、38%)で、フランスは第6位で58%、35%、英国は第8位で47%、45%。
フランス、英国は22カ国中全体から見て、公的補助と独自の会費等収入とのバランスが一番良くとれている国だといえる。米国とヨーロッパ主要国を比べてみると、米国には今も政府とNPOとの対立の攻めぎ合いが続いているが、ヨーロッパ主要国では政府の社会福祉分野を第三セクターが分担し、公的補助は当たり前という市民感覚が育っている。
貧困対応モデル
概してヨーロッパ諸国は公的補助依存度が高く、それゆえにNPO個別の信条というよりキリスト教社会を母体とした広い理解に立脚しているように見える。たとえば、ドイツの常勤65万人、ボランティア150万人という巨大な自由福祉協会は6つのカトリックとプロテスタントの社会福祉機関で構成されている。こうしたNPO組織はオランダ、スウェーデンにも存在している。
ところが、米国でも第1の第三セクター支配モデル(政府の行動を制限し、資金繰りと基本的サービスの調達では第三セクターに依存)、第2の政府支配モデル(政府活動を拡張して第三セクター活動を制限)という対立だけでは進歩がないということで、ヨーロッパ諸国による第3の「協調モデル」(政府は財政面を担い、NPOは政府の財政の支援するサービスを提供し、その機能を果たす手助けをすること)に傾斜しつつあるという。
「協調モデル」は、とくに財政負担の多い貧困軽減を長期にわたって支援する途上国援助の時に有効だとされている。一方、NPOの収支構造の国際比較によると、国際関係は公的補助33%、NPO独自会費25%、フィランソロピー41%となっており、フィランソロピー依存度は特別として、公的補助が重要な役割を果たしていることがわかる。
いずれにしても、日本はまだまだ社会的に欧米のような状態に達していない。
ただ、私の個人的見解では、日本と欧米の社会的発展の歴史的な違いが双方の市民意識の発展に大きな影響を与えていると言いたい。それは、また司馬遼太郎の「日本人は、いつも思想は外から来るものだと思っている」という「この国のかたち」にも深く関わっているかもしれない。その議論は後日に回すことにしたい。貧困対応モデル(参考文献「NPOと政府」、2007年、ミネルヴァ書房)
※国際開発ジャーナル2010年8月号掲載