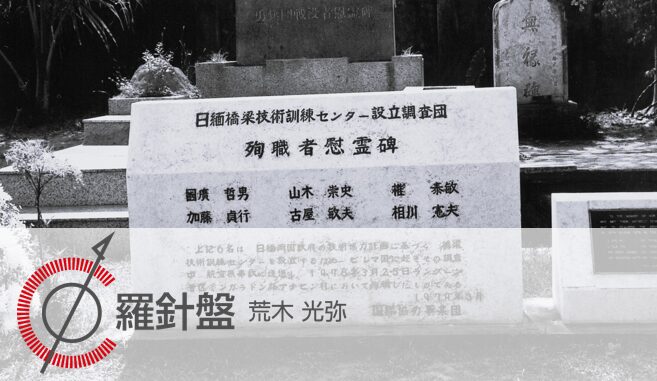膠着状態
アフガニスタンの米軍は、一部を残して撤退することになった。こうした光景はこの国の長い歴史の中で幾度ともなく繰り返されてきた。
2001年の9・11のテロ事件以来、米国はテロ撲滅を誓い、テロ潜伏地とみられるアフガンのタリバン政府を攻撃した。しかし、「テロとの戦い」は決着点を見出せずに、米国は軍隊を撤退させることになった。歴史は繰り返されている。それは軍事力による制圧・支配を意図した歴史で、アフガンは今回もそうした大国の軍事力による一方的な国造りを否定したことになる。そこで注目されるのが、平和構築を目指す開発協力である。
日本政府は5年間に50億ドル(約5,000億円)という巨額の援助資金をアフガニスタンの平和構築に集中投入しようとしている。しかし、現実はテロの脅威に阻まれて、現場から見る限り日本の開発協力による平和構築は一種の膠着状態に陥っている。
カブール首都圏70キロまでは防弾自動車で辛うじて身の安全を守ることはできるが、それは一本の道路という線上での安全であって、開発協力者の求める“面的な展開”はほぼ不可能な状態に近い。開発の設計図は書けても、それを施行に移すようになれば、広い地域での展開が必要になる。とくに、アフガンの生命線ともいわれる農業開発ともなれば、水資源開発とともに広大な耕作地の確保が絶対的条件になる。
現在、首都カブールにはJICAをはじめ20社近いコンサルタント会社が事務所を設けて、開発の可能性をうかがっている感じだが、自爆テロなどの脅威の前で、開発協力者たちの勇気も萎縮しがちだ。実は、JICA、コンサルタントを含めて、第一線に立つ若者たちの中には、平和の構築に燃えて、なんとか「武力中心でない平和的な開発」に挑戦すべく“覚悟”を決めている者たちもいる。しかし、後方(日本社会全体、そして政府)では“覚悟”することを恐れてお茶を濁しているといっても過言でない。
日本政府は、もし1人でも犠牲者が政府開発援助で出たら政府の責任が問われるということを異常に意識して、アフガンの開発前戦に対して一種の足枷をはめているように見える。それは、株式上場している大企業にもいえることで、もし1人でも犠牲者が出たら責任者の首が飛ぶことを恐れて臆病神にとりつかれている。
それでいて政府は900兆円近い国家的借金を抱えていながら、アフガンの平和構築のために「50億ドル」という巨額の資金を国際約束している。しかし、その巨額の資金は現実にはテロの脅威に負けて、遣うに遣えない資金になっている。他方、巨額の予算を預かり、それを有効に遣わなければならない外務省では、有効に遣われない矛盾に陥って、どうしたらこの予算を消化することができるかを考えれば考えるほど、本来の予算の目的を見失うような精神状況に追い込まれているという。
その一方で、政府は開発協力(ODA)のムダを指摘して、予算を減らそうとする。事業仕分けでは重箱の隅をつつくような注文をつけた。ところが、アフガン対策のための50億ドルという巨額な予算については、その遣い道に無頓着のように見受けられる。どう見てもアフガニスタンの平和構築、経済開発のために50億ドルを有効に遣うという、国家としての“覚悟”が政府にどこまであるのか。その決意はわれわれだけでなく、広く世界にも示されていない。
憲法と自衛隊
論を一歩進めると、極論かもしれないが50億ドルは一種のジェスチャーというか、“外交的見せガネ”にすぎないのではないのかと疑われても抗弁できないのではなかろうか。つまり、50億ドルは国連の枠組みというよりも、日米同盟の枠組みにおける日本の応分の政治的協力経費として分担したシンボリックな資金であって、本気で体をはってアフガンの平和構築を成し遂げるという“覚悟のない資金”としか見えない。
それは、1990年の湾岸戦争(イラクのクウェート進攻)の際、国際的に評価されなかった130億ドルの国際貢献に似ていると言われかねない。あの時はカネだけ出せば何とかなるという日本の姿勢が評価を下げたのである。
もし、アフガンの平和と発展を軍事力だけに依存せずに、開発協力という平和的な手段に軸足を置いた国家としての“覚悟”があるならば、アフガンで見せたドイツのような軍隊に守られながらの開発協力を採用したかもしれない。
しかし、それが今の日本には出来ない。日本の自衛隊は国連平和維持軍として派遣することさえもできないという憲法の制約を受けている。しかし、イラクでは「非戦闘地域で後方支援を行う」ことが憲法違反にならないということで、自衛隊は非戦闘地域とまでいかないまでも、戦闘の極めて少ない地域に派遣され、日米同盟の形式的行為と批判されながらも一応民生的な貢献を行った。だが、アフガンではいつどこで自爆テロが発生するか予測がつかない。アフガン全域が戦闘地域である。そうなると、イラクのような大義名分でアフガンに自衛隊を大々的に派遣することも難しくなる。
そうしたなかで、日本(自民党政権)は苦肉の策として、インド洋における洋上での自衛隊の給油活動を展開した。ところが、民主党政権は現状認識不足というか、アフガンの平和構築に50億ドルを投入することを国際社会、とくに米国に約束した。しかし、それは自分の身さえ自分で守れないような制約を受けている開発協力をJICAの現場に押し付けているようなものだ。これは、無責任ともいえる押し付けになる。
憲法の制約を受けて、自衛隊を軍隊とも呼べず、武器使用さえも制限されている現状の中で、アフガンへの自衛隊の派遣が、たとえ平和的な開発協力のためでも不可能であることは民主党議員の誰でも熟知しているはずだ。それにもかかわらず、50億ドルを先に積んだということは、現場での安全は保障できないが、覚悟して開発協力を行えと言っているようなものだ。“覚悟”の意味が違う。
「普通の国」
こうしたリアリティーに直面すると、私たちは開発協力の重要テーマである平和構築について深く考えざるを得なくなる。平和構築とは、人間の安全保障に根ざした思想である。それは安全を保障されていない人びとを救済すると同時に保護し、保護された人びとも含めて自立できる政治的、経済的な社会基盤を構築していくための協力である。
しかし、そうした協力を必要とする国は往々にして政治が乱れ治安が悪い。治安の悪さから見れば、一種の戦闘状態の国もある。アフガンはその最たる国である。こうした国の平和構築は、武力による治安回復と同時に人びとの生活の安定を図るための開発協力が同時並行的に行われないと効果的でなくなる。その場合、協力する側に犠牲者も出る。それは軍隊のみならず、開発協力に携わる民間人にも出る可能性が高い。
もし治安が悪く、開発協力に支障をきたす場合は、治安回復を先行させて平和が確立されてから開発協力者が本格的な国の開発に取りかかるという考え方もある。こうしたケースこそ今の日本の出番ではないだろうか。
開発協力者の安全を軍隊に守ってもらいながら民生安定のために協力することは、現行の日本国憲法下では不可能である。
また、仮に欧米軍の庇護の下で開発協力を行うにしても、政府だけでなく民間企業も含めて犠牲者の出るのを恐れて消極的になる。それは日本の社会的なタブーにもなっている。
つまり、日本において平和の問題は“一国主義的”で、世界の平和への貢献という理念の域に達しておらず、それは非国際的な「島国的エゴイズム」と言われても反論できない。また、自分の国は自分で守るという“民族的”な覚悟なき国家は、世界平和をいくら唱えても、「普通の国」としての資格さえ有していない、ということを銘記すべきであろう。アフガンの平和構築は私たちに多くの教訓と宿題を残したことになる。
※国際開発ジャーナル2011年2月号掲載