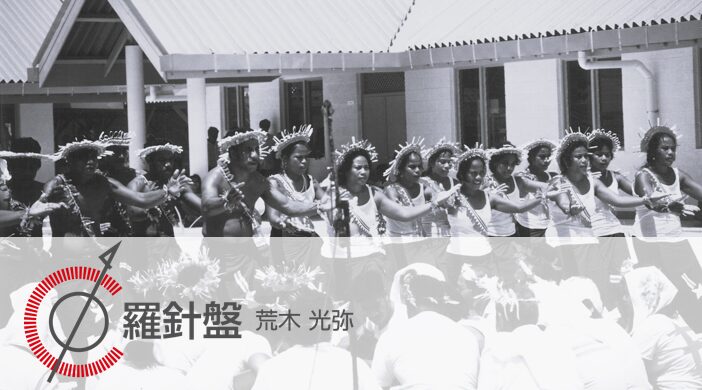青年海外協力隊への応募も下火
日本人の今の“内向き志向”は過去にみられない現象だという。文部科学省の上級会合では日本への「30万人留学計画」は大学の独立行政法人化に伴うサバイバル作戦の下で、それなりに実行されるであろうが、その逆の日本から外国(とくにアジアなど途上国)への留学は減少している、とわが国青年たちの“内向き現象”を懸念する声が強かったという。かつての「海外雄飛」といった言葉は死語に近い。
そこで、上記の上級会合では“内向き志向”を“外向き志向”に変えていくには中・高生の段階から“外向き教育”を充実しなければならない、という意見が支配的だったという。
“内向き現象”は最近の青年海外協力隊への応募状況にも現われている。不景気対策で期間2年の公募にも青年たちが殺到するかと予測していたが、意外と応募は冷え込んでいる状況。以前だったら2~3年間、途上国で汗しているうちに社会状況も好転して、次のキャリア・パスを目指すことができた。ところが今は違う。これは推測だが、この世界的な金融恐慌による不況は2年や3年で終わりそうもないと考えているのだろうか。それとも、あくまでも“内向き”で日本でのライフワークを決めて、日本での安定と安寧を求めているのだろうか。どこに原因があるのかよくわからない。
ただ、こういう事情に直面したことがある。これも日本の少子化現象の一つかもしれないが、親が一人っ子の息子や娘の海外一人旅を歓迎しない傾向にあることだ。だから、青年海外協力隊の公募にパスしても、親が事務局へ乗り込んできて、子どもの合格取り消しを強要する。こうした傾向は昔からあったことはあったが、このところ、表に現われない形でその度合いが強くなっているようだ。
この問題にもう少し言及すると、そもそも戦後、日本で青年海外協力隊が発足したのは、アメリカの“ピース・コー”(平和部隊)に習ったとはいうものの、農村の次男、三男坊を食い扶持減らしのためにも海外へ送り出して、途上国の農業開発に協力させ、次世代を担う人材として見聞を広めて帰国させるという狙いがあった、と聞いている。アメリカの“ピース・コー”は平和のために汗して働いてくることを建前としながらも、狙いは英語の普及とパッケージでアメリカの民主主義を広めることであった。日本とは考え方あるいは戦略性が異なる。
日本の青年海外協力隊も日本経済の復興に次ぐ高度成長のなかで、農村青年が工場労働者として都市周辺へ出稼ぎに行くにつれて、青年海外協力隊への応募も激減し、いつの間にか都市型の修理工をはじめスポーツ、教師、さらには芸術分野にも応募が拡大し、いわゆる“農村型”から“都市型”へと応募状況が変化していった。企業も有給休暇制を導入して社員の協力隊応募をサポートした。
今では年間1,200~1,300人ぐらいの派遣隊員のうち、一定の枠組みをつくって、たとえば教師派遣を行うなどの制度を設けている。それでも応募状況は減少傾向にあるから、現在の青年たちの“内向き現象”は決して一時的なものではないように思えてならない。
国内での海外疑似体験
その原因はどこにあるのだろうか。企業の海外活動をみていると、人材の登用に関して昔と異なりつつある。かつては海外進出先の幹部のほとんどは本国日本で採用され、訓練を受けた正社員で占められていた。そのため時々、現地従業員からは不満が噴き出して、ストライキに発展するケースもあった。ところが、企業のグローバル化が進むにつれて、企業の現地化が進み、優秀な現地人の現地採用が増えた。国によっては日本の青年より優秀で勤勉な幹部候補が採用され、企業のグローバル化を支えている。その面でも日本青年の働き口が減ったことになる。それは数の上ではたいしたことではないかもしれないが、労働市場の一つの変化とみることもできる。
もう一つの傾向に注目してみたい。それは“国内満足度”である。昔は“舶来崇拝”という言葉が使われたように、日本人は流行病を患ったようにパリ・コレクションのような舶来熱に浮かれていたが、今では銀座でも新宿でも世界中の一流舶来ブランド品が店頭で買えるようになった。ディズニーランドもフロリダまで出かける必要もない。インターネットの普及で海外事情がリアルタイムで入手できるし、テレビ番組でも海外での疑似体験ができるようになった。人びとは東京など大都市にいなくても地方でも十分甘受できる。
つまり、青年たちの好奇心は海外にまで出かけなくても、国内で十分満たされ、一種の疑似体験が可能になった。青年たちの“内向き現象”は少子化現象だけの問題ではなく、“国内満足”の享受を可能にした社会的変化がもたらした現象ではないだろうか。
しかし、私は表面的な疑似体験的な社会現象に不安を感じてならない。疑似体験では生身の人間が飢えや病気で苦しんでいることをどこまで体で受け止めることができるだろうか。疑似体験では戦争の犠牲になった子どもたちや母親たちの悲しみと憤りを、実感としてどこまで受け止められるだろうか。擬似的な青年たちが将来増えていくと、途上国の貧困削減、平和構築を目指すODAへの支持者が減っていくことも考えられる。“内向き現象”はODAの大敵なのである。
一番良い例が“戦争ゲーム”である。痛みと恐怖心を感じない戦闘疑似体験が、人間の奥底に潜む人間の暴力という魔性をどれほど刺激するかは議論するまでもない。いずれにしても戦闘疑似体験は正常な人間の理性の発育を拒むことになりかねない。その反面で、太平洋戦争を体験し、目の前で死んでいく戦友、あるいは空襲で焼け死んだ家族、友人、知人と悲しい別れを余儀なくされた人たちが理屈抜きに戦争に反対するのは、それが擬似でなく現実であるからだろう。
「開発教育」のすすめ
ところで、文部科学省は今になって海外への留学組が減っていく現象に危機感を抱いて、この流れを逆転させる手立てを講じようとしている。その一つが夏休みを利用したスタディー・ツアーである。擬似でない現実の途上国を体験させて、好奇心を起こさせ、海外になじむ心を育てたいと考えているようだが、果たしてうまくいくのか、疑問の声も聞こえてくる。
一時、文部科学省の政策主流ともいわれた「国際理解教育」に加えて、平和、環境、人権、民主化、貧困救済などを包含する「開発教育」の重要性が唱えられ、NGOを中心に全国展開しているものの、いまだ中・高生たちへの広がりはそれほど進展していない。こうした「開発教育」は単なる補助教育のレベルでなく、社会科の教科書で教えられるようにならなければ、子どもたちの心を開けないのではなかろうか。
私は学校の本科で世界への好奇心を育てるような仕組みをつくらない限り、青年たちの“内向き”を“外向き”に変えられないと考える。しかも、それらが入試で出題されるように企画される必要がある。私は「開発教育」を「国際理解教育」の最終章だと思っている。「開発教育」は理解するにとどまらず、貧しい人びと、困窮する人びとを助けるというアクション(行動)につながる教育だと考える。
日本人には物事を客観的に受け止めよく理解するものの、それから先のアクションでちゅう躇する傾向がある。最近、高校で学校ぐるみで途上国の貧しい子どもたちへの援助運動を積極的に進めているが、これこそまさに学校ぐるみの「開発教育」だと思う。
拓殖大学では高校生作文コンクールの一環として、高校生たちの“国際協力へのアクション・プラン”を応募の対象にしているが、その実績をみると、年々応募数が増えているので、教育の現場での努力がひしひしと伝わってくる。文部科学省がこうした運動を政策的にバックアップすると、間違いなく大きなハズミになると思う。
ODAの分野からみても、こうした「開発教育」はODA支持者にもなる可能性が強いだけに、もっと親身になって、こうした運動をバックアップする必要があろう。長期的にはその一部が“外向き”になり、国際協力事業にもプレイヤーとして参加することも考えられる。
※国際開発ジャーナル2009年4月号掲載