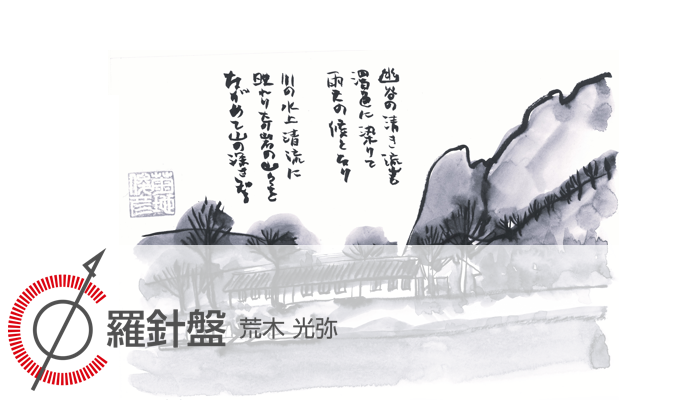日本の援助への「安心感」
3・11の東日本大震災からもう3カ月が過ぎた。その間、世界から多くの激励のメッセージや多額の義援金が届いた。日本の途上国援助を40年以上も追っかけてきた筆者にとって、この3カ月間は改めて日本の半世紀以上にわたる途上国援助が、援助される側から見てどういうものであるかを知る絶好の機会になった。
東日本大震災に対する135カ国以上の支援国のうち、少なくとも100カ国は日本が政府開発援助(ODA)で支援してきた開発途上国であると言ってもよい。ただ、ここではあえてODAに焦点を当てているが、いわゆる日本への「恩返し」の範囲は広く、鉱物資源、熱帯農水産品などの大量輸入、日系企業進出による雇用の拡大、技術の移転、そして多くの留学生の受け入れなどに及んでいると言える。したがって、ODAだけが「恩義」の対象だとは決して言うつもりはない。
そういう前提で“政策的意図”を内包させた先進主要国の途上国援助と対比させながら、日本の援助の特徴を改めて考えて、「恩義」の根源を探ってみようと思う。
第1の視点は日本の援助への「安心感」。日本の援助の第一歩は「国際社会への復帰」を念願して、東南アジア諸国への戦後「賠償」を開始し、さらに、南西アジア、東南アジアの戦後経済発展を援助する国際的な組織「コロンボ・プラン」に参加して技術協力を開始し、日本への世界の「信頼回復」を目指した。その頃の日本には、「国際社会への復帰」という純粋な動機しか存在していなかった。
ところが、次のステージでは好むと好まざるにかかわらず、米ソ超大国の冷戦構造に組み込まれる形で東南アジアへの経済協力の強化を要請される。米国は東南アジアに対して、東南アジア諸国を共産主義諸国よりもいち早く経済発展させる援助を求めた。その大役をおおせつかったのが日本である。日本には平和憲法があったので、非軍事的な貢献、経済協力が要請されたのである。
日本は東南アジアへの賠償援助に加え、1978年からODA3倍増を公約し、1990年代末から2000年までの10年間、援助大国にのし上がりトップドナー(世界一の援助国)になった。その間、東南アジアには政治的枠組みを強化した東南アジア諸国連合(ASEAN)が誕生し、大きく成長していった。当然ながら日本の東南アジアでの経済権益は欧米を凌ぐものとなった。
これに対して、米国の軍事援助も経済援助も共産主義との抗争において基本原則である「議会制民主主義」、「自由主義」を旗印にしていたので、冷戦崩壊後はその要請が一層強まり、多くの途上国に対し急速な民主化を求める内政干渉を強めていく。時には露骨な政治的圧力、軍事的介入を辞さなかった。これにはヨーロッパも同調し、途上国援助に関する日本と欧米との温度差は大きく開いていった。
つまり、日本には欧米に比べて「ノンポリシーがポリシーか」と言われるほど、途上国に対して内政干渉にもつながる政治的体制への政治的圧力は存在しなかった。その結果、日本の途上国援助は途上国側から「安心感」を持たれるようになった。時に、多くの人びとから「日本は軽んじられている」と言われるほどであった。
別な言い方をすると、「警戒されなかった」と言える。また、欧米の外交には、時々ダブル・スタンダード(二重規準)が見られる。日本は国民性なのか、国際外交的に未熟なのかもしれないが、スタンダードはいつも一つで、いかにも単純。それが途上国の人びとの「安心感」と「信頼感」を得ているように感じる。その意味で、早期の経済回復と本来の援助の再開を願う被援助国の気持ちを多くのメッセージから読み取ることができる。
「要請型援助」への信頼感
第2の視点は「要請型援助」。ここで言う要請型援助とは、融通のきかない公式主義を指していない。基本的なスタンスは「押し付けない援助」のことである。つまり、日本は相手の要望をよく聞いたうえで、提案する援助方式を原則にしてきた。そのことは相手国の主権を尊重することに通じるので、日本への「信頼感」を高め、日本への「安心感」を深めることになった。
一方、欧米型援助には政治、行政、経済政策などにおいて「トップダウン」(上からの押し付け)方式を押し通すケースが多く見られる。そこには、国造りにおいて自分たちが絶対だという自信に満ちた発想が横溢している。それを現場レベルで見ると、たとえば、農業指導において彼らは現地人の現場監督を育てて、現場指導させる。欧米人は手を汚さない。植民地経営手法と言えないことはない。
ところが、日本の場合は現地のリーダーを決めていても、彼と一緒に畑に入り、泥まみれになって現場指導することが多い。これは、ものづくりの工場指導でも同じである。こうした土壌が現場での品質管理を向上させるQCというボトムアップの経営方式を育んできたとも言える。新しい国を造る時、トップダウンは必要だ。しかし、人びとに自信を持ってもらうためには、ボトムアップも必要だ。途上国の人びとは現場型の日本の協力方式に親しみを感じている。それは同じ目線に立っているからであろう。
ただ、援助する側から見ると、欧米のように戦略性をもってトップダウンで臨むべきではないのか、という指摘も聞かれる。それも一理ある。しかし、日本人は国民性と言ってしまえばそれまでだが、現場が好きだ。それは職人気質を反映しているとも言える。途上国の人びとは、政治レベルから庶民レベルまで、そうした日本と日本人に「安心感」を抱いている。言うまでもなく、「安心感」は「信頼感」を醸成させる酵母になっている。東日本大震災で「日本人頑張れ!」という多くのメッセージには、我田引水かもしれないが、日本人への「安心感」と「信頼感」が折り重なりながら一つの底流をつくっているように感じる。
頼れる「経済開発型援助」
第3の視点は「経済開発型援助」であったこと。過去形的な言い回しであるが、それは世界の途上国ゾーンで飛躍的な経済発展を遂げたASEANを初めとするアジア地域で日本の経済協力が果たした役割が大きかったからである。その動機は、先にも述べたように冷戦時代における米国とのバードン・シェアリング(応分の分担)で東南アジアの経済発展に寄与することであったが、同時に、それは日本の海外市場の確保という点で最大の国益でもあった。米国との分担としての経済協力はASEANのみならず、今や世界第2の経済力を誇るようになった中国もその枠組みに入っていた。最初の対中援助は「開かれた中国」が政策目標になっていたからである。
とにかく、日本の援助は経済協力で真価を発揮した。まず、国造りの基本は経済・社会インフラ整備から、を援助方針にして経済発展の基礎づくりを行い、そのうえで貿易と民間投資を絡ませて、総合的な経済成長への基盤づくりに協力した。援助を実体経済と密接に関係させたという点では1960年代から70年代の日本の援助は欧米を圧倒していた。今になって欧米は援助の行き詰まりを打開するために「PPP=官民連携」を強調しているが、かつての日本の援助はアジアの経済発展に重きを置いた官民連携援助であった。
日本では経済協力が国益の追求の道具になっているという批判も聞けるが、途上国側に立ってみると、それは自国の経済発展を促してくれるもので、言うならばWin-Win(互恵)の関係にあるという。そうであれば、国家の主権を脅かされることもない。国民の援助への依存性も軽減できる。その意味で、欧米の政治的押し付け、体制・制度的な押し付けよりも、日本の援助は無害の存在だと見られている。だから、日本の援助には警戒心を抱かず、「安心感」を強く感じているのであろう。
途上国側に立ってそう考えてみると、日本の経済協力は途上国にとってより基本的な援助と言えるのではなかろうか。東日本大震災は日本人にとって大変不幸な出来事だったが、私たちに途上国との関係を改めて客観的にみつめるチャンスを与えてくれた。
※国際開発ジャーナル2011年7月号掲載