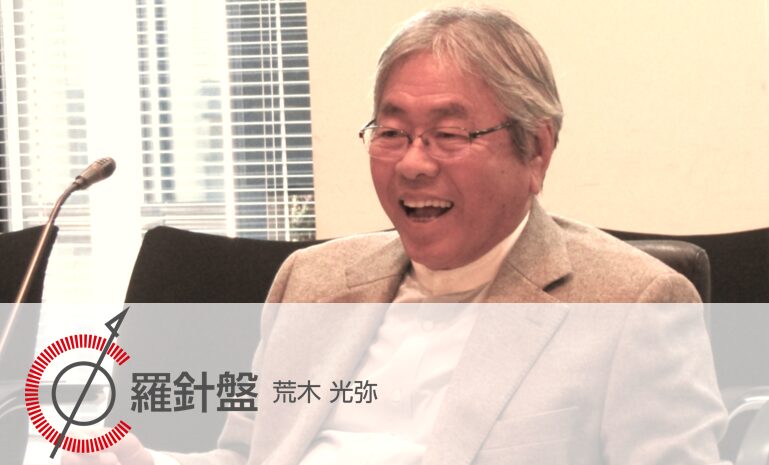謹賀新年
昨年は事業仕分けで明け暮れした感じであった。民主党政権の言い分では、それぞれの開発協力(ODA)の意義は認めるが、その予算の遣い方が問題であるという。私たちにとって意義が認められたということは政策的価値が認められたことになるので、将来に向かって少しは眺望が開けてきそうだ。
それにしても、事業仕分けはテレビで放映されたこともあって一般の人びとに与えた衝撃は大きく、開発協力のイメージにかなりのダメージを与えた。そこで、政府、とくに外務省では説明責任、情報開示を前面に押し出して「見える化広報」政策を実施しようとしている。しかし、私の40年以上の経験からみるといかにも“焼け石に水”の感じに映る。もう少し日本社会の意識構造、日本人の伝統的思想などに眼を向けて新たな対応を考えてみる必要があるのではなかろうか。そこで、次のようなテーマに絞って開発協力の国民への浸透政策などを探ってみた。
(1)社会的リーダー層の存在感
もう2、3カ月経っただろうか、かつて経済協力(当時はそう言った)の第一線で活躍していた旧友たちが訪ねてきて、「経済協力の社会的地盤が低下しているのは、社会的リーダー層の支持と支援が得られてないからではないか」と問いかけ、本誌の名付け親の大来佐武郎(元外相、元海外経済協力基金総裁、日本経済研究センター初代理事長など)のような人物の不在を嘆いていた。大来佐武郎は17年前に逝去されているので、今では想い出の中で追慕するしかない。
とにかく、大来佐武郎という人物は社会的リーダー層の重鎮だった。それは歴史をたどると明白だ。たとえば、終戦翌日には若くして「戦後問題研究会」を組織し、日本の再建を研究し、経済安定本部では「日本経済再建の道」を主査した。また、「吉田首相を囲む会」では白洲次郎らと共にブレーンとして参加している。この期間だけでも中山伊知郎(東京産業大)、東畑精一(東大)、有沢広巳(東大)、都留重人(東大)、蝋山政道(政治学者)、佐伯喜一(後の野村総研代表)、大内兵衛(東大)、石川一郎(初代経団連会長)、永野重雄(新日本製鉄会長)等々、数え切れない日本の社会的リーダーたちと知的交流を深めていた。大来は開発協力の嚆矢といわれた1964年開催の第1回国連貿易開発会議に政府代表の一員として出席し、60年代末には70年代の途上国開発政策を討議する、世銀による「ピアソン委員会」で日本代表を務めた。さらに、世界の賢人会議といわれた「ローマ・クラブ」に賢人の一人として選ばれ、今日の地球環境問題につながる報告書「成長の限界」の討議にも加わっている。
その人脈は内外にわたって政治家、学者、経済人、官僚などに深く根を下している。大来は途上国援助の問題でも日本の社会的リーダー層に対し慫慂(しょうよう)する力をもち、大来が「開発協力は日本にとって必要だ」と言えば、大来への信頼感からみんなも必要だと思うほどであった。「必要だ」という声が社会的リーダー層に充満してくると、多くの人びともその声に従って「必要だ」と思うようになってくる。その声が多くなれば政治を動かす。
現在、こういう社会的リーダーが存在せず、政府の開発協力は論調的に日々弱体化している。時代がそういう流れをつくっているといえばそれまでで、日本の将来にとって重要ならば、誰かが大きな声で「必要だ」と言わなければならない。しかし、それを言うには、その人物が人望のある社会的リーダーでなければ効力がない。今、そういう人物の不在が問題になっているのである。日本の将来に指針を与えられる社会的リーダー層が形成されていない悲しさがある。その不幸が政府の開発協力(ODA)を不幸にしているといっても過言でない。
(2)途上国援助は輸入思想か
1970年代に世界は二度のオイルショックに襲われたが、日本はその難局を切り抜けるのに成功した。その日本に比べ、ヨーロッパは80年代になっても経済の低迷が続き、途上国を援助する余力をなくし、いわゆるAid Fatigue(援助疲れ)に陥った。日本はそうしたヨーロッパを肩代わりするかのように、1990年代末から2000年にかけてトップドナー(世界一の援助国)へ登り詰めた。
ところが2000年以降、ヨーロッパの経済が元気になって再び開発援助が復活する。開発援助の純受取額(ネット)ベースでは、日本は米、独、英、仏に続く5番目の援助国へと脱落した。いつ回復するか定かではない。仮に経済が上向いたとしても果たしてヨーロッパのような復活が期待できるかどうか、それほど自信はもてない。なぜか。漠然とした見方だが、どうも社会の成り立ちの違いが原因しているかもしれないからだ。
1999年6月、ドイツのケルン・サミットで“ジュビリー2000”というクリスチャン・ソサエティーの市民運動が展開された。“ジュビリー2000”とは、モーゼの教えに従って50年ごとに奴隷を解放し借金を棒引きにしなければならないということで、現代は奴隷こそ存在しないが、貧しい国の借金は棒引きにする、という決議がなされた。仏教国の日本は最大の被害者で途上国の貸し付けの円借款などの債務約1兆円近くの棒引きを余儀なくされた。この時、サミット会場を取り囲むように約5万人の“人間の環”ができて、援助国に圧力をかけた。
まさにクリスチャン・パワーであり、これこそクリスチャン・ソサエティーのなせる業である。つまり、宗教的精神が支柱となって途上国援助の底流をなしており、経済が少しでも回復し、社会が活性化してくると、それが宗教的パワーとなって貧しい人びとへの援助活動を一気に押し進めていくという宗教的な紐帯力が発揮されていく。
それでは、日本にヨーロッパのような“援助復元力”があるかと聞かれれば、どう答えればよいだろうか。当然ながら日本はクリスチャン・ソサエティーでない。日本は戦後、ヨーロッパ型援助の形だけを取り入れてきた。日本の援助の源流をたどると、援助は賠償援助といい、国益的な手段として活用されることから出発している。もし、それが復活するならば援助の復元力は十分あると思う。
とにかく、ヨーロッパの援助は植民地時代の大罪は口にしないが(植民は文明化だと主張)、人道という面ではキリスト教を通して“血と肉”となっている。司馬遼太郎は著書「この国のかたち」で「日本人は思想は外から入ってくるものだと思っている」と語っているが、日本人はその輸入思想(とくに宗教)を“血と肉化”できない。たとえば、中国から韓国に入った儒教は韓国の人びとの血と肉となり生活そのものまでも支配する力をもつようになったが、日本に入ってきた儒教は“儒学”になって教材化された。
ここで何を言いたいかというと、ヨーロッパから日本に入った援助哲学も人びとの“血と肉”にならず、単なる援助学となり学生たちに「国際協力論」として教えられている。この状況はヨーロッパと社会的バックグランドが異なるので変わり様もない。そうであるならば、途上国援助を地球規模の問題と絡ませて、子どもたちの教育の中に根深く導入したほうが、将来への国民理解への早道になると思う。その教育効果は何百億円、何千億円の広報価値を有しているといえる。
(3)日本の援助哲学「自助努力」
自助努力は「ODA大綱」でも日本の援助哲学として書き込まれている。日本はDAC(OECD開発援助委員会)に日本の考え方として自助努力(Self-Help)をパートナーシップと共に提案した。すると、これをDACは「オーナーシップ(Ownership)」と解釈して公式化した。日本のいう自助努力は、人間の精神改革にまで及ぶ思想的背景を有していた。これはたぶんに念仏を唱えて人間のあり様を問う仏教的な教えを含んでいたにもかかわらず、ヨーロッパのクリスチャン・ソサエティーではそれが理解できず、アフリカにも理解できる「オーナーシップ」と定義したのではないだろうか。
明治時代には英国のプロテスタントであるサムニエル・スマイルズ(著述業)の自助論「Self-Help」を翻訳した中村敬宇の「西国立志編」が福沢諭吉の「西洋事情」に肉迫するベストセラーとなり木版刷の数十万部が売れた(司馬遼太郎著「明治という国家」から)。自助論では「独立心をもて」、「勤勉実直であれ」といった徳目が唱えられていたが、それは日本の社会的規範でもあった。
一方、札幌農学校で教鞭をとっていたクラーク博士のプロテスタント的な影響を受けた新渡戸稲造や内村鑑三らは、もともとは武士の出身であった。これは武士道がプロテスタントと合流できる同床的なスピリットを有していたことを意味している。
つまり、日本の「自助努力」の精神には、プロテスタントと同様に一種の宗教的背景をもっていたといえそうだ。しかし、これはクリスチャンのいう「慈悲の心」より厳しく自己鍛錬、自己改革を求めているので、途上国には援助依存心を捨てよ、ということになる。自分で立ち上がるならば日本は、資金的援助はもとより技術的な援助もしよう、というスタンスに立っている。このように日本は開発援助においてヨーロッパとスタートラインが異なっている。したがって、政府はその違いを深く認識する必要がある。
政府は国民の支持を得ようとすぐ考えつくのがマスコミ対策であるが、報道は社会的、政治・経済問題を追求することを旨としていて、教えを説くものではない。また、現実に国際協力を政治として報道するのか、経済として報道するのか、社会問題として報道するのか、報道の中に国際協力の居場所が定まらない。ジャンル分けした報道に収めきれないのが国際協力である。
私は、結論として第1に教育に立脚して、小学校の頃から日本が生きていく上で必要な思想としての国際協力を正規の教育に組み入れ教科書化していくこと、第2に日本経済の発展に必要欠くべからずの思想に立脚して、新しい社会的リーダー層を発掘し彼らの認知を得るよう努力することが開発協力復活への道だと考える。
※国際開発ジャーナル2011年1月号掲載