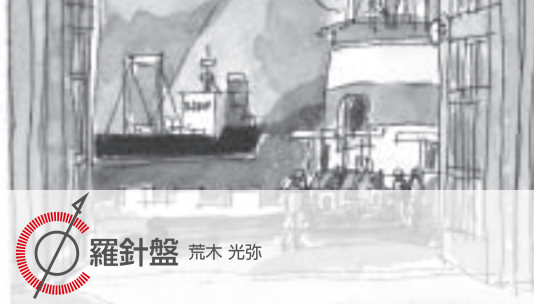「官民連携」は日本が元祖
「BeyondAid」(援助を超えて)が伝統的な援助国の新しい潮流として注目されている。
去る9月14日、ジョージワシントン大学で世銀のゼーリック総裁が講演したテーマは「BeyondAid」だった。同じ頃、英国とドイツを訪ねていたGRIPS(政策研究大学院大学)開発フォーラムの大野泉氏によると、両国とも従来の援助方式を変えていく「BeyondAid」へのトレンドを深めた政策へ転換しようとしている。
端的に言うと、両国ともに民間部門に軸足を置く援助政策へ完全シフトしようとしているのだ。その背景には第1に、国家の財政事情は言うまでもなく、経済開発をより効率的、効果的に進めるには民間の“企業力”と連携したほうが費用対効果が高く、経済開発のスピードアップも期待できるという事情があるようだ。
第2に、両国ともに発展著しい新興国をパートナーにした新しい援助方式を構築しようとしている。これは、新興国の台頭で生まれつつある新しい世界秩序への素早い対応であると言える。こうした傾向は、日本では第1に「官民連携」の援助方式、第2に、日本の過去の対アジアODAアセット(資産)を活用した「連携型国際協力」に該当しよう。
これは筆者の持論であるが、「官民連携」はなにも今始まったものではない。元祖は日本なのである。
少し歴史を遡ると、1950年代から1980年代初めぐらいの日本のODAは「経済協力」と呼ばれ、アジアの経済開発を「官民連携」による経済協力で進めていた。それは自然発生的であったが、まず貿易から始まり、次いで輸入代替という形で本邦企業のアジアへの企業進出が盛んになり、それをバックアップするように経済協力によって道路、港湾、電力などの経済インフラ部門が整備された。それをいわゆる“三位一体”の経済開発と呼んだ。
もっとも、この時の「官民連携」は、当時の国是とも言うべき輸出振興政策によってサポートされていた。だから、経済協力(円借款)も民意を重視したタイド(国産愛用)だった。
ところが、これにDAC(OECD開発援助委員会)が異論を唱えた。表向き批判は「日本の円借款協力は商業的援助である」であった。しかし、実際はOECD「貿易委員会」での欧米の反発がDACに持ち込まれたのである。そこには特に、ヨーロッパ諸国の日本の貿易力に対する脅威感、警戒感が満ち満ちていて、ヨーロッパ諸国はどうしたら日本のアジアへの輸出競争力を減退させるかに腐心していた。
そこで、貿易と援助をセパレートして、DACの中で“アンタイド化”(日本の国産品と連携させない援助論)を展開して、DACのニューフェイス日本を包囲攻撃した。これらは一種のヨーロッパの陰謀と言っても過言ではない。話は飛ぶが、こうした日本の歴史を勉強した新興国筆頭の中国は、DAC加盟の誘いに乗ることはないだろう。
長い冬の時代(アンタイド)
日本も新しい援助秩序づくりに向かって、DACルールなるものを修正するか、あるいは無効にしてもよいのではないだろうか。もっと大胆に言うならば、ここらでDACを解体してもよいのではないか。「アンタイドでなければ、円借款協力をODAとして認めない」というDAC原則にいつまで従っていくのか。
そもそも、従来のヨーロッパ援助国もギリシャではないが、財政難で苦しんでいる国が多くなった。第二次世界大戦後、ヨーロッパ復興を目指した地域開発機関OECD(経済協力開発機構)も1990年の東西冷戦の終焉で、政治的役割は基本的に終えている。
日本はここらで新興国、準新興国の多いアジア地域での経済協力のために新しいアジアDACを指向してもよいのではなかろうか。「BeyondAid」の流れはそういうことを示唆しているとも言える。
さて、誰が何を言おうと、「官民連携」は日本が元祖である。その元祖を批判してきた欧米諸国は、今になってやっぱり民間企業ベースを加えないと、少ない援助資金の費用対効果は上がらないと言い始めている。
その変心の背景には、大きく言って「奇跡的なアジアの経済発展」がある。アフリカ諸国は「アジアの経験をアフリカに」と唱え始めている。ただ、今では「アジアの中の中国の経験をアフリカへ」と潮目が変わっている。
「官民連携」の元祖日本はどうかというと、正直言って、過去の亡霊にとりつかれたままで、迷い子の状態と言ってもよいのではなかろうか。
第1に、1960~1970年代にかけて、「官民連携」は完璧だったが、日本への非難「エコノミック・アニマル」論も加わって、「官民連携」を修正し、むしろ“脱経済”、“脱民間企業”へと政策的流れを変えた。特に、1980年後期から1990年代にかけてのトップドナー(世界一の援助国)時代に、“脱経済”、つまり“脱国益”へと変身して、“根無し草”のような円借款論が美しい言葉で語られるようになった。
そこでは、ODAにとって経済は悪であり、国益論は否であるとの思考回路が整備された。それを財政難の今になって、国益論へ回帰させようとしても、たとえば、ODAとアジアの大型インフラ整備事業と連動させることのできる“官民連携人材”が育っていない、という現実に直面する。
それは、長い「官民連携」冬の時代(アンタイド時代)に、民間側の脱ODAが進み、ビジネスとODAを連携させるプロフェッショナルが育っていないからである。欧米の“アンタイド論”は援助においては正義であったかもしれないが、国の力を殺がれた日本にとっては疫病神であったと言える。
他方、援助の世界へ参入してくるニューフェイスたちは、リアリティーの薄い純粋援助論を大学でたたき込まれているので、いざ実践になっても「官民連携」に疑念を抱きがちである。援助機関のJICA(国際協力機構)にもそういう人種が多く見られる。
パートナーは新興国
そう考えると、一言で「官民連携」といっても、その道は遠い。欧米諸国の場合は、「官民連携」が新しい分野に映っているので、先入観なく参入できる。日本は、なまじっか「官民連携」を一時否定した歴史的経緯から、なんのためらいもなく参入できるものではない。だから、簡単に「BeyondAid」と言っても援助思想の再考、制度上の変更といった大手術が残されている。
英国とドイツの「BeyondAid」について簡単に現状を見ると、以下の通りである。
新興国とのパートナーシップについては、英国は「グローバル・デベロプメント・パートナーシップ・プログラム」(GDPP)を立ち上げて、中国、インド、ブラジル、南アフリカをパートナー重点国にしている。ドイツは「グローバル・デベロプメント・パートナー」国としてインド、ブラジル、インドネシア、南アフリカ、メキシコの5カ国をあげている。英国、ドイツはこうした新興国と組んで、他の途上国支援を行おうとしている。
筆者は早くから、かつて日本が重点的に援助したASEAN先発国と組んでアフリカ支援を行うべきだと唱えてきた。ASEANには日本の援助のアセットが今も健在で、日本との協力で、そのアセットを一層進化させたいと願っている人たちが多い。援助の費用対効果という面でも、新興国あるいはASEAN先発国との連携は避けて通れるものではない。
なかでもドイツの経済開発省は企業との連携を深めながら、たとえばマルチ(多国間援助)よりもバイ(二国間援助)を重視して、Win-Winを目指しながらもドイツへの国益還元を図ろうとする意図が見えてくる。
それを証左するものが、財政支援からプロジェクト型援助への政策転換である。その上、これまでのGTZ(ドイツ技術協力公社)を解体して、他の3つの技術協力機関を統合して、GIZ(ドイツ国際協力公社)を新設している。しかも、新GIZは経済協力省(BMZ)からの予算だけでなく、各省の海外協力を一手に引き受けて、1万7,000人体制へ移行している。GIZは技術協力、コンサルティング部門で内外の関心を集め、頼れる援助機関へと成長を遂げようとしている。日本も見習うべきだ。
※国際開発ジャーナル2011年12月号掲載