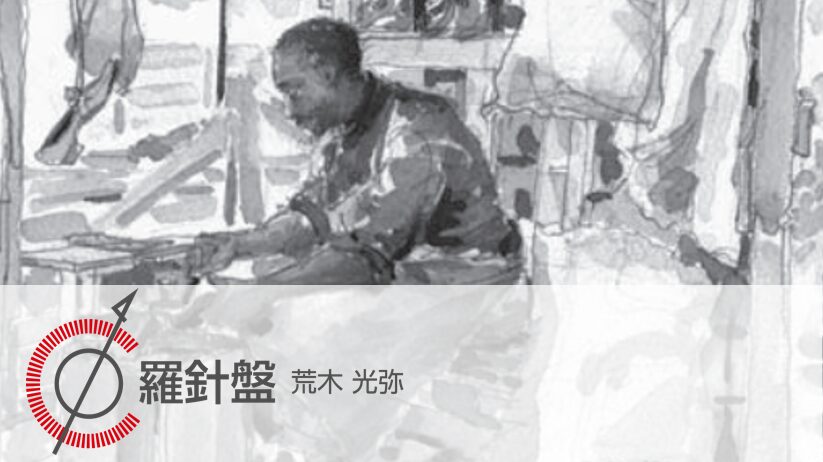古色蒼然としたDAC基準
開発援助における「官民連携」(PPP)インフラ事業は、少しずつ市民権を得ているようだ。だが、国際的にはまだ揺籃期にあると言えるかもしれない。
NGOからは、あれは援助ではなく、単なる民間投資促進ではないかという声も聞こえてくる。実施機関のJICA内でも官民連携は民間連携事業部に任せておけばよいという職員もいる。
国際的には、少なくとも国連筋はあまり気乗りがしていないようだ。なぜかというと、援助すべき先進国グループが景気低迷を理由に、国連ミレニアム開発目標を達成するために予定されている援助拠出額を、官民連携事業でカバーしようとしていることに不満を抱いているからだという。国連の開発途上国側は労使交渉ではないが、額面通り、きっちりと援助資金を先進国グループから獲得したいのだ。
国際社会は、これまでの援助される国から援助する国へ発展しているBRICSグループと、伝統的な開発援助委員会(DAC)援助グループを統合し、一つの統一した援助グループを確立するよう努力すべきではなかろうか。南北問題という歴史の相克はもう終わりにしてもらいたい。
また、第2次世界大戦後にヨーロッパの復興開発を目的に設立された経済協力開発機構(OECD)も古色蒼然としているが、その中に設けられたDACの考え方はもっと古い。限られたDAC職員にしか計算できないような政府開発援助(ODA)のグラント・エレメント(贈与比率)を振り回して、独自の援助基準をつくることで、自らの存在を担保しているように見える。
今や新興国グループが独自のBRICS開発銀行を船出させようとする中で、DAC独自の援助基準をつくっても自縄自縛で意味がないし、それはむしろ援助秩序を混乱させるだけである。
アフリカは企業進出を懇願
アフリカ諸国は官民連携でもよいから民間企業が進出して、地元の雇用を増やし、技術移転してもらいたいと訴えている。援助ベースで行政組織づくり、人材育成に時間をかけているうちに、肝心要の国民が疲弊し、若者たちの不満が爆発して暴動が頻発するようになる。こうした事態を避けるためにも、若者に職を与え、社会の安定を図らなければ経済の発展もない。その意味でも、官民連携による開発事業、企業進出は即効性が高い。
日本を初め外国の企業群もアフリカを地球最後のフロンティアとして捉え、将来へ向けての投資を考えている。その意味でも、ODAと連携した官民連携事業に期待するところが大きい。たとえば、モザンビークのように港湾、道路、工業用水の供給などの基礎インフラをODA資金で整備して、企業進出の投資環境を整える、ということも官民連携事業(電力、運輸、水供給など)をよりスムーズに進展させることになる。
かつて、東南アジアの経済成長を誘発させる大きな要因として、“三位一体の経済開発論”が語られたことがある。三位一体とは、貿易、投資、経済協力(ODA)を指し、これらが連結しながら経済発展を飛躍させたという考えである。
つまり、経済協力で港湾、道路、空港、通信などの国家の基礎インフラを整備するうちに投資環境が良くなって外国投資を呼び込み、最初は輸入代替産業の振興で、雇用が確保され、同時に人材も育成され、次は輸出産業へと発展した。外貨を稼ぐ対外貿易実績が積み上がった。国々の生活水準が上がり、国の近代化も前進した。こうして、今日に見るような東南アジア諸国連合(ASEAN)経済圏が誕生したのである。
今考えてみると、その頃から日本は官民が連携してASEAN経済圏づくりを続けてきたことになる。その点では、今日の官民連携は小粒ながら昔の伝統をプロジェクトベースで踏襲しているとも言える。
独善的な制度設計
ところが、現在の官民連携によるPPP協力でも、かつてDACに「円借款協力は商業援助だ」と批判され、アンタイド化されて日本の強味が骨抜きにされたように、今度は世銀など国際機関が制度設計に介在してきて、民間の創意工夫が生かされる官民連携のPPP事業を国際入札にかけるという法整備を進めている。昔の悪い夢を見せられているようだ。
PPPは政府主導型と民間提案型に分かれている。国際機関は制度構築と称して競争性、透明性確保を掲げて、端的に言えば、コラプション(汚職、ワイロ)を防止するために、政府主導型で、かつ事業権入札型の制度が導入されている。
他方、民間企業の技術やノウハウが生かされる企業提案型も存在しているが、政府による支援(保証など)が限られている。いずれにしても、価格競争になると、新興国の安値攻勢で日本企業の受注がむずかしくなろう。ただ、価格競争ではPPPの持ち味である民間企業の経営的知恵やノウハウ、技術の特性などが生かされなくなる。
それは、ODAでPPPを支援しているので、わが国ODAの官民連携という新しい芽が摘み取られることになる。コラプション防止ということだけで、PPP事業の真価が失われてよいものだろうか。経営を知らない国際機関が独善的にPPPの制度設計を行って、果たしてどこまでその実効性が担保されるのか、矛盾を感じてならない。
しかし、なぜそうなったのか。日本にも責任がある。PPP事業が始まると同時に、PPPの法制度の不備が明るみになった。PPPがODAの一環であるならば、少なくとも民間の知恵と経験を借りてODAで法整備協力を積極的に展開すべきであった。かつて、日本企業の東南アジアへの進出が始まった頃は、工業団地の造成はもとより、外国企業進出を奨励するパイオニア法の制定などにも知恵を貸した。日本は東南アジアの要望に応じて企業進出を戦略的に展開していたのである。
ODAに組み込まれた官民連携としてのPPP事業は、開発途上国側に立つと開発効果を発揮するが、日本の民間側に立つと海外投資のニュー・フロンティアである。現在のPPPはASEANが主な対象かもしれないが、いずれアフリカにも広がる可能性が高い。日本は官民連携して、PPP事業における投資受け入れ側と投資する側とのWin-Winの関係が成り立ち、かつ援助としての条件を満たし得る投資法整備に協力すべきであろう。どうも日本の国際展開には戦略性が欠落している。
※国際開発ジャーナル2014年12月号掲載