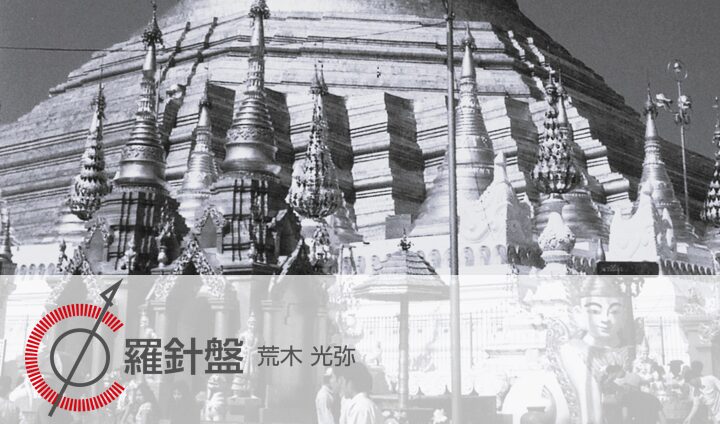官民一体の経済外交
安倍政権の打ち出した成長戦略にともない、日本の開発援助が大きく変貌しようとしている。
2月20日に開かれた日本貿易会第337回常任理事会で、経産省貿易経済協力局長の北川慎介氏は「官民一体の経済外交」をテーマに講演し、次の9点を強調した。
(1)インフラ・システム輸出の新展開。とくに「面的な開発」を重視していた。たとえば、今、話題のミャンマーでのティラワ経済特別区(SEZ)などに代表される総合的な工業団地造成、すでにご存知のインドネシア・ジャカルタ首都圏投資促進特別地域開発、インドのデリー―ムンバイ間産業大動脈構想など。言うなれば、アジアの広域地域開発を目指し、新しい経済開発空間を創造する発想だと言える。
(2)資源開発(原発停止の影響による代替エネルギー開発)。
(3)クールジャパン戦略(ファッション、食文化、アニメなど日本文化の世界進出)。
(4)中堅・中小企業の海外展開支援(すでにODAベースでも中小企業の海外展開を支援するプログラムが進行中)。
(5)BOPビジネス(目下、JICA投融資事業の一環として多くの調査が実施されている)。
(6)アフリカ・ビジネスの可能性(6月に横浜で開かれる第5回アフリカ開発会議での日本政府の方針が注目されているが、同時に動きの鈍い民間企業の進出動向が衆目を集めている)。
(7)人材のグローバル化(とくに国際的に活躍できる人材育成が待望されている)。
(8)新興国からの資金還流の促進。その一環としての(9)対日投資促進など。周知のように、安倍政権は「日本再生」のための“3本の矢”(金融緩和、財政支出、成長戦略)を提示。そのうちの成長戦略では「戦略市場創造プラン」として、医療・福祉分野、エネルギー分野、次世代インフラ分野を掲げている。これに対して、経産大臣は日本の“双発型エンジン”として「貿易立国」と「産業投資立国」を唱える。
新たな貿易立国論はこれまでのような単純なモノの輸出振興ではなく、先に述べた“面的な開発”を組み込んだインフラ・システム輸出、クールジャパン戦略輸出、中堅・中小企業の海外進出、BOPビジネス、アフリカ・ビジネスなどへと今日的な進化を遂げている。しかも、こうした輸出を産業投資として拡充していくことを新世代戦略にしよう、としているのが特徴的だ。
ただ、日本の貿易収支がマイナス7兆円であるのに対し、対外直接投資残高は約82兆円(対内直接投資残高は約17兆円)というように、今や金融面での進出が目立っている。国際協力銀行(JBIC)の融資実績を見ても、1960年代、70年代、80年代半ばまでの“輸出金融時代”が、90年代、2000年代以降では“投資金融時代”へと変化している。
こうした傾向は総合商社の海外展開でも顕著だ。かつてのトレーダー(貿易業者)から、今ではインベスター(投資家)へ変身している。これは余談だが、トレーダー時代にはODAビジネスの仕掛人としてプロジェクト発掘から形成までを手がける有能な商社マンが存在した。しかし、投資時代にはプロ級のODAビジネス仕掛人を必要としない。それがODA円借款の成約拡大を難しくしている一面でもあるようだ。
国益に貢献する開発援助
いずれにしても、日本のODAも今や日本の成長戦略に組み込まれた「官民一体の経済外交」に大きく貢献しなければならない立場にある。これまでODAのクライアントはすべて途上国であったが、これからのODAのクライアントは日本であり、日本国民にすべきだという考え方が台頭している。そうなると、協力対象も従来の途上国から新興国、中進国へ範囲を広げ、わが国ODAの重要なクライアントにカウントされる。
そういう考え方は、2月に公表されたECFA(海外コンサルティング企業協会)の提言の“視座”でも明確に提示されている。また、4月からは「日本の国益に対する貢献」をテーマに、日本の国際的プレゼンスを確実に高める援助政策のあり方を問う「援助政策研究:リアルポリティークとしての開発援助」(主査:平野克己氏=ジェトロアジア経済研究所地域研究センター上席主任調査研究員)がスタートする。
平野氏は、最近出版した「経済大陸アフリカ」(中公新書)の第4章「試行錯誤をくりかえしてきた国際開発」で、ODAは国際開発の手段たりえているか、と反問しながら、「国際開発の理想は足元のナショナリズムから接近するしかない。ドナー国の国民にとって利益となり、それが同時に開発途上国の国民を豊かにするという政策手法をつくりだすしかないのである」と述べている。これは、まさにWin-Win(互恵)型援助である。
さらに、ODA関係省間でも「ODAの国益裨益の強化」が検討されているようである。それは、タイド型円借款のみならず、海外投融資、円借款連携型技術協力、技術協力としてのマスタープラン(総合計画)のあり方など、ODAスキーム全般にわたって「国益に寄与するODA論」へと広がるものと見られている。
過去を振り返ってみると、60~70年代にはODAを経済協力と称して、わが国の経済成長に寄与する輸出振興政策に組み込まれ、円借款は“円クレ(クレジットの略)”と呼ばれて大型資本財やインフラ輸出に寄与した。産業構造不況の時も、不況産品の輸出を手伝った。
ところが、70年代後半から80年代に入ると、日本の外貨準備高は世界一となり、その独り占め状態が世界中のバッシングを受けた。そのために、政府は輸出抑制策に走りながら、資金を世界に還流させる政策展開を図った。
斜陽の「国際貢献論」
その時のODAに関する考えは、ただ一途に「国際貢献論」が主流となり、政策的に「国益還元論」が消されてしまった。こうしてODAの「国際貢献」政策の流れが出来上がった。この時から、ODAの国益無視の貢献論が主流となり、途上国をクライアントにするODA論が大きな力を得た。
たとえば、74年にODA技術協力の実施機関OTCA(海外技術協力事業団)と海外移住事業団を母体に農林省の海外農林業開発公団構想、通産省の海外貿易開発協力公団構想を抱き込んでJICA(国際協力事業団)が創設された。その時の創設の動機は国家主導による開発輸入事業を興すことであった。その第1号が今ではアフリカの半乾燥農業に寄与するまでに成長したブラジルのセラード農業開発協力であった。当時は需要旺盛な大豆量産を計画したものだった。その頃は世界的な天候異変で、農産物の世界的な需給バランスが崩れていた。
これは一つのエピソードだが、時の総理大臣田中角栄氏は「国際協力事業団とは良い名前だ。オーストラリアで牛を飼い、カナダで小麦を生産すればいいな」と語った。それほどに当時の日本は資源の開発輸入に奔走していた。
ところが、97年にはODA量が頂点に達し、世界のトップドナーになると、ODAの「国際貢献論」がますます燃え盛り、国益追求が邪道視されるようになった。この時から「純粋援助論」が大きな勢力を得て、それをアカデミズムとジャーナリズムが優良格付けしたことなどで、反国益のODA論がまかり通るようになった。
そうした時代に育った援助関係者には、今でも「官民連携」にさえ反論する人を見かける。急激な政策転換に戸惑っているようだ。
しかし、時代は止まらない。一方的な献身的ODA論は日本の置かれた現在の情況に応じて、昔のような輸出振興政策とは一味違う、新しい海外投資時代に応じた新しいODAのあり方へと変身しなければならなくなった。現在の安倍政権の打ち出した国家戦略に沿って、ODAの考え方、あり方を改める時代へ向かっている。
※国際開発ジャーナル2013年5月号掲載