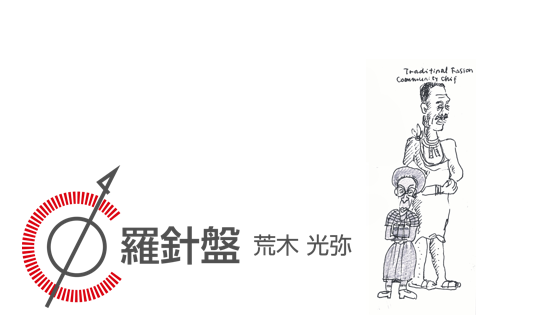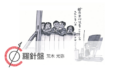必要な優先順位
日本は対アフリカ援助(ODA)を2012年までに倍増し、18億ドルにすることを国際公約している。18億ドルとは、2003~2007年の5年間の平均9億ドルを倍増するという計算。
日本は東日本大震災にかかわらず、去る5月1~2日にセネガルのダカールで開催された第3回TICAD閣僚級フォローアップ会合でその実行を約束し、世界の賞賛を受けた。つまり、“律儀に約束を守る国”というイメージを高めたのである。
これは、日本人に自信と勇気を与えてくれることになるので、ODAの納税者には歓迎すべき外交成果だと思う。しかし、これは苦情になるかもしれないが、一般の人びとのみならず、勉強不足の筆者にも、日本のアフリカ開発援助の全体像が見えてこない。また、日本はどの分野に得意な知識、技術、ノウハウを投入しているのか、情報が不足している。
JICAの分野別方針によると、インフラ、貿易・投資、観光、農業、コミュニティー開発、教育、平和構築(グッド・ガバナンス=良い統治)、気候変動、水と衛生、南南協力というように、クリスマスツリーの飾り物のようにバラバラに見える。恐らく、各国ごとに重点分野を決めて援助していると思うが、一見すると、一国のすべての開発課題を手がけているような感じを与えている。
また、援助分野が分散すると開発資金が分散し、プロジェクトも小型化して開発効率が落ちる。JICAの分野別方針を見ると、いかにもJICAのすべての開発課題部ごとの仕事を並べたように映っている。
もう少し計画の選択と集中を図り、資金と人材の効率的で効果的な運用を目指してはいかがだろうか。少ない資金で最大の効果を上げるには、一カ国ごとに援助分野のプライオリティー(優先順位)を決めて、資金と人材の集中投入を図るべきではなかろうか。
必要な円借款の工夫
たとえば、今のアフリカでの最重点分野は、国境をまたぐ物流道路、さらに沿海部の港までの物流道路などの建設だと見られているが、その資金規模は一ケタ違うほど小さい。
インフラ関連の今の予算規模は無償を中心に、全アフリカを対象にせいぜい370億円である。平成20~21年度に結ばれたE/Nの全アフリカ道路案件は円借款が5件、無償が11件、技術協力が3件で、基本的に無償中心のインフラ整備といっても過言ではない。
多くのアフリカ諸国はその置かれた経済状況から、返済しなくても済む無償資金を頼りにする。だから、返済を求める円借款協力によるインフラ整備は難しいと考える。また、援助する方もそう思っている。
しかし、それでは鉱物資源や農業開発の飛躍的な発展は期待できない。外国からの投資インセンティブも高まらない。たとえば、道路沿線上での地下資源開発計画のみならず、農村地帯での大規模農産品開発計画、アグロインダストリー新興計画などを絡ませた市場性の高いマスタープラン(総合計画)を担保に、資金規模の大きい円借款を導入することは出来ないものだろうか。
それなりの規模の道路開発にはそれなりの開発資金が必要になる。短期的な収益、経済性だけを計算していては、国家の根幹となる道路開発は前進しない。それには、資金規模の大きい円借款の活用しか残されていない。なんらかの形で返済を担保できる工夫が図られれば、アフリカの道路開発はかなりのスピードで進展すると考える。
そうなると、最近内需の大幅減少から急速に競争力を落としてきたわが国建設界の復活を図る一助になるかもしれない。恐らく、日本の建設界は東北の復興で体力回復を図られると見られるが、その力をアフリカの地で発揮できるよう、円借款協力制度に画期的な工夫を加える必要があろう。
読者の皆さんはお忘れかもしれないが、賠償絡みで建設したフィリピンのルソン島を縦貫する日比友好道路(マルコス大統領によって名称変更された)は最初の頃、せいぜい水牛の歩道だと非難された。しかし、10年も経たないうちに道路の沿線に町が建設され、いろいろな産業も生まれ、いつの間にか水牛の代わりに自動車が走るようになった。道路とは、そういうものである。道路がないと、何も産まれない。
もう一つのエピソードを紹介しよう。1960~70年代のタイでは、米軍と隣国のベトナム、カンボジアとの戦いで、それらの国境に向けて米軍の軍用道路が戦争目的で建設された。
タイ農民は、バンコクに通じるこの軍用道路沿いにメイズ(とうもろこし)を栽培し、バンコク港へ積み出した。それで、これらの軍用道路は別名「メイズ・ロード」と言われるようになった。道路が地域開発の特効薬であることを証明したのである。
必要な開発輸入の再生
アフリカの国家建設で道路・港湾に次いで重要な部門は農業である。単純に言うと、農業が発展し、アフリカの食糧価格を引き下げてくれないと、給与所得に占める食糧代が下がらず、アフリカにおける労働力の国際的比較優位は低くなる。
つまり、外資が進出して、アフリカの地で産業を興すにしても、賃金がアジアより高ければ彼らはアジアに留まる。今や、生活費に占める食糧経費の高いことがアフリカにおける産業振興のアキレス腱になっている。
これを根本的に改革するならば、麦、コメ、とうもろこしといった主要農産品の国際競争力を高めることだと言われている。しかし、現実にはWTOの農産品の輸入自由化で、未成熟なアフリカ農業を横目に、大量の農産品が安く輸入され、もともと政府により保護されていない農業は衰退の一途を辿ることになった。
もし、アフリカ農業を振興させるとすれば、一時的にもアフリカへの農産品の輸入自由化を抑え、その間に、政府は国産食糧品の一定の買い上げで農村振興を図り、農村が発展への起爆剤になるようなシナリオが必要になる。
その国のガバナンスがしっかりしていれば、農業基金を設け、そこに援助国が資金を投入して、一部、政府の農産品買い上げ補助金にすることも考えられる。これは、特定目的の資金投入であって、欧米の言う何でも入れて何にでも使うバスケット方式とは違う。
しかし、農業先進国はむしろアフリカを食糧輸出の草刈場にして、「アフリカは駄目だ」と言う。米国は援助分野においても余剰農産物を買い上げて、食糧不足の途上国へ援助する制度を持っている。それはPL480号という法律である。
こうした先進国は一種の国際的な“食糧マフィア”と呼ばれる存在で、WTOなど国際的な枠組みをつくって、食糧輸出を合法化している。そこを鋭く突いてくるのが中国で、中国はアフリカで国策として食糧の開発輸入を行いながら、アフリカ農業の後進性を打破して、途上国のリーダー国家としての政策目的を果たそうとしている。
だが、よく考えてみると、そもそも開発輸入というWin-Winの経済協力は、日本のお家芸だったはずである。
日本の定義は、資本、技術、経営の一体化した経済活動を通じて、途上国の潜在的な資源を開発し、市場を与え、これを輸入することにより、わが国の必要な資源の安定供給確保に資するもの、としている。その元祖が没落して、後発中国がこれを対外援助の重要な手法として利用している。日本こそ資源のない島国で、海外に資源を求めざるを得ない条件下に置かれているはずである。
温故知新ではないが、日本もかつて高度成長の契機にもなった開発輸入システムをアフリカの地で再現させてみたいものだ。そのためには、すべてを民間リスクにせず、政府がリスク・ヘッジするぐらいの決意で臨まないと、民間はついてこない。
対アフリカODAの場合でも、それなりのリスクを背負ってもアフリカで農業開発事業、鉱山開発事業に取り組みたいという企業を“一社支援”はできないと言っている間は、アフリカでの官民連携は進展しない。
それには国の安全保障の一環としての食料安全保障を内外一体化して、どうしたらアフリカでの民間のリスク・ヘッジができるかを検討していく必要がある。それはODAの内外一体化に通じることになる。
※国際開発ジャーナル2011年8月号掲載