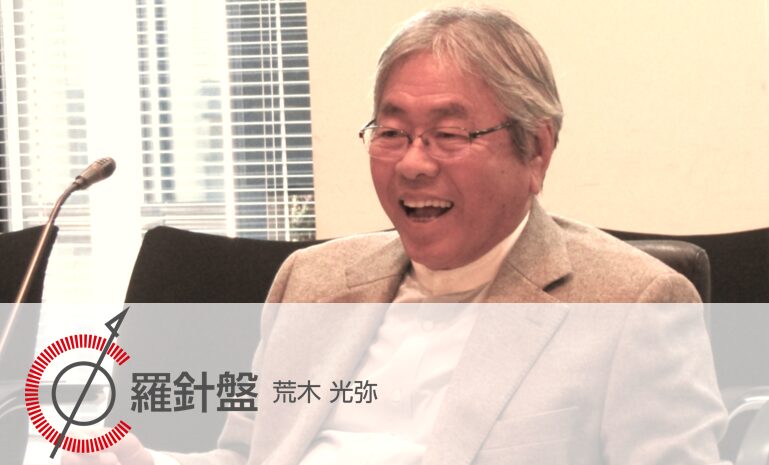失業が社会不安の元凶
アフリカでは25歳以下が全人口の3分の2を占めている。だから、若年労働者の失業率は35%にも達している。
ところが、若年労働者は現金収入を求めて、地方から都市へ大挙して集まってくるので、都市部の若年失業率は一気にはね上がる。ところが、都市には増大する失業者を吸収できる産業群が存在しない。だから、都市には若者たちの不安と不満が膨張し、一触即発の社会状況を生み出すことになる。
“アラブの春”の民主化市民運動もエジプトの首都カイロの市民運動(暴動とも言える)を見ても、最初はカイロ大卒の失業者たちが発火点になった。こうしたインテリ組は説得力においても組織力においても市民のリーダー格になり得る。ところが、大学卒のインテリ組の失業率は、そうでない者よりも3倍も高い。「大学は出たけれど」とはこのことである。アフリカの大学卒業生たちは「大学は失業者をつくる所だ」と嘆く。
いつの世も革命は知識階級から始まると言われている。たとえば、中国の社会主義革命も、農村部の毛沢東にしろ、都市部の周恩来にしろ、教養の高い中産階級に属していた。キューバ革命のチェ・ゲバラも大学で医学を学んだ。民主化運動も同じである。
その意味で、アフリカの都市部で知識階級に属する失業者が群れると、失業への不満が体制への不満となって、不安定な社会状況を創り出すことになる。
しかし、多くのアフリカ諸国には独自に大量の失業者を救済する力も能力も備わっていない。だから、暴力的な社会不安は国家の不安定に直結する。そのことは、アフリカの為政者、指導者グループも心得ている。だから、彼らは「援助よりも投資を」と言い、外国援助よりも外国からの民間企業の投資を歓迎し、現地雇用の増大を求めている。
したがって、アフリカの第1の国家的ニーズは社会的安定につながる“雇用創出”である、といっても過言ではない。その点で、これまでのアフリカ開発援助が国家の発展と安定にとって効果的であったかどうか、再検討してみる必要があろう。
理詰めで国を造るには、先進国の経験に照らして、政府を創り、社会インフラ、経済インフラを整備し、法律を制定し、というように一つの先進国的パターンに沿うよう求められてきた。しかし、「ないないづくし」のアフリカで、一つひとつ先進国的な手順通りに国造りを進めていては、時間がかかり過ぎる。
一刻も早い国家のテイクオフ(離陸)のためには、これまでのアフリカ開発の壁を打ち破る必要があろう。その意味で「雇用創出」に一点集中して援助する側の政府と民間の一体化、いわゆる「民官連携」が重要なテーマになるべきだと考える。あえて「官民連携」と言わなかったのは、民間を政府がバックアップする連携を強調したかったからである。
突破口になる民間投資
しかし、そうは言っても投資する側にとってみれば、経営戦略的にリスクを考えなければならない。それが投資の条件と深く関わってくる。リスクの最大なるものは非道なアルジェリア事件のように、治安問題である。アフリカ開発をテーマにする時は、治安問題、もっと言えば政府の統治能力が問われる。
国際社会がアフリカ開発を議論する時は、ミレニアム開発目標(MDGs)だけでなく、先に社会の安定を確保できる統治能力を討議する必要がある。それは、これまでの開発援助におけるガバナンスよりもその能力がもっと厳しく問われなければならない。こうしたことがより現実的に議論されずに、開発援助(資金の流れ)だけを約束しても、民間投資にとっては“現実的なバックアップ”にはなり得ない。
さらに、投資環境とひと口で言っても、時間と費用のかかるものばかりである。たとえば、関税をはじめとする課税制度、外国投資法やその手続き、行政システム、労働法などの法整備などをはじめ、行政マン、企業人、産業人材育成といったソフト部門のみならず、空港、港湾、道路、電力、通信といったインフラのハード部門においても未整備の国がアフリカに多い。
そのうえに、投資企業にとってみれば、経営の基本とも言える市場(マーケティング)を検討しなければならない。マーケティングも投資対象によって異なる。たとえば、地下資源なのか地上の農業資源なのか、それとも労働集約型産業、地場市場充足型産業なのかによって、目指す国々も異なる。だから、対アフリカ投資は投資対象分野によって、投資先の国も異なる。そこに、その国最大の開発ニーズがある、と言えないこともない。その開発ニーズ分野には、当然ながら雇用創出の可能性も包含されている、と見てもよいだろう。
こうした民間投資のマーケティングから、当然ながら数多いアフリカ諸国への投資の選択と集中が行われるので、日本の開発援助もその動きと連動して対象国を決める必要がある。
これは筆者の持論であるが、日本のODAはアフリカ50数カ国すべてを網羅することはできないので、いかに選択と集中で日本の旗の立つ(フラッグシップ)のモデル対象国を選び、まずその国の国造りを成功させて、その成功の秘訣を他へ移転させていく、という戦略的な工夫があってもよいのではないかと考える。その時の国選びの基準は、これまで述べてきた民間の投資市場、貿易市場の判断が優先されるべきだと言いたい。
「民官連携」のマスタープラン
次に強調したいことは、「民官連携」のあり方である。
開発の要になるものは、マスタープラン(総合計画)づくりである。ところがODAベースの多くの場合、マスタープランづくりは相手国の要請ベースで始まる。それを可能な限り提案型にして、そこに民間の投資計画も盛り込んで、プランの成熟度を高める。
現在のODAベースの広域インフラ計画には、民間投資を想定したり、民間投資を呼び込むような試みがなされていない。アフリカのどの政府も民間投資を包含した地域開発マスタープランを大いに歓迎するに違いない。アフリカでの「民官連携」はここから始まらなければ、その完成度を高めることはできないのではなかろうか。
たとえば、アフリカのある国で地下資源開発あるいは農業開発の民間投資があれば、その物流のための道路インフラ、そして積み出し港インフラをODAでカバーし、その道路沿線で地域開発、農村開発を支援し、もし輸出産品が出てくれば輸出する。道路にしろ港にしろ、その付加価値は一段とアップする。こうした夢を可能にするには、市場を見据えた民間投資のマーケティングが必要になる。
もし、このような「民官連携」が可能ならば、減少するODAの効果的な活用が可能になり、民間投資のリスク・ヘッジにもなるので、民官補完型の有効な開発モデルにもなる。
実を言うと、こうしたアフリカ開発モデルは、かつてのアジア型の「三位一体」経済開発モデルを参考にしているのである。
三位一体とは、貿易、投資、経済協力が混然一体となってアジアの経済発展に貢献したことを意味している。ただ、アジアの場合は、輸入代替企業進出から始まり輸出産業になり、技術が定着し、大きな雇用創出効果を出すまでには四半世紀という時を刻んでいる。アフリカにアジア・モデルをあてはめるには、時間を短縮し、集中度を高める必要がある。そのためには、「民官連携」を徹底的に推進し、民間投資や貿易を優先し、それらをODAでバックアップする協力体系を構築する必要があろう。
とにかく、アフリカの開発協力は実体経済を定着させて、雇用の拡大を図り、社会を安定させ、国力をつけて、民主化を実現し、自らの力で教育と国民の社会福祉の充実に取り組むべきであろう。
そのためには日本の援助哲学でもある「自立」、「自助努力」の精神が芽生え、民族国家の完成度を一層高める必要がある。これが、日本的開発協力の理想型だと言えるが、その推進力になるのが経済の発展である。それには民間の経済活動が必要である。それをODAが底支えできれば、アフリカに新たな地平が見えてくる。
※国際開発ジャーナル2013年3月号掲載